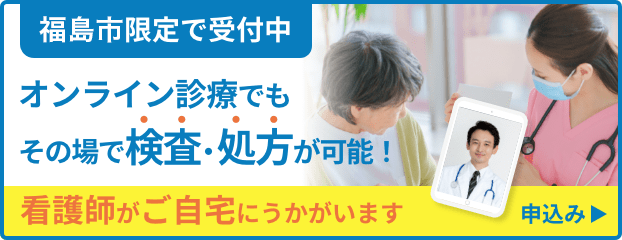糖尿病の分類と、それぞれの原因や治療方法について解説
糖尿病はその成り立ちによって4つに分類されることをご存じでしょうか。特に1型糖尿病と2型糖尿病は原因が異なるため、治療や発症のタイミングに違いがあります。
生活習慣病として有名な糖尿病ですが、
「生活習慣が良くないと糖尿病になってしまう?」
「両親が糖尿病だから自分も発症しないか心配」
などと不安に思う方も多いでしょう。
本記事では糖尿病の分類や発症の原因、予防や治療法について解説しています。糖尿病の人や家族に糖尿病をもつ人は、ぜひ参考にしてみてください。

名倉 義人 医師
○経歴
・平成21年
名古屋市立大学医学部卒業後、研修先の春日井市民病院で救急医療に従事
・平成23年
東京女子医科大学病院 救急救命センターにて4年間勤務し専門医を取得
・平成27年
東戸塚記念病院で整形外科として勤務
・令和元年
新宿ホームクリニック開院
○資格
救急科専門医
○所属
日本救急医学会
日本整形外科学会
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
糖尿病の分類 4つ?5つ?
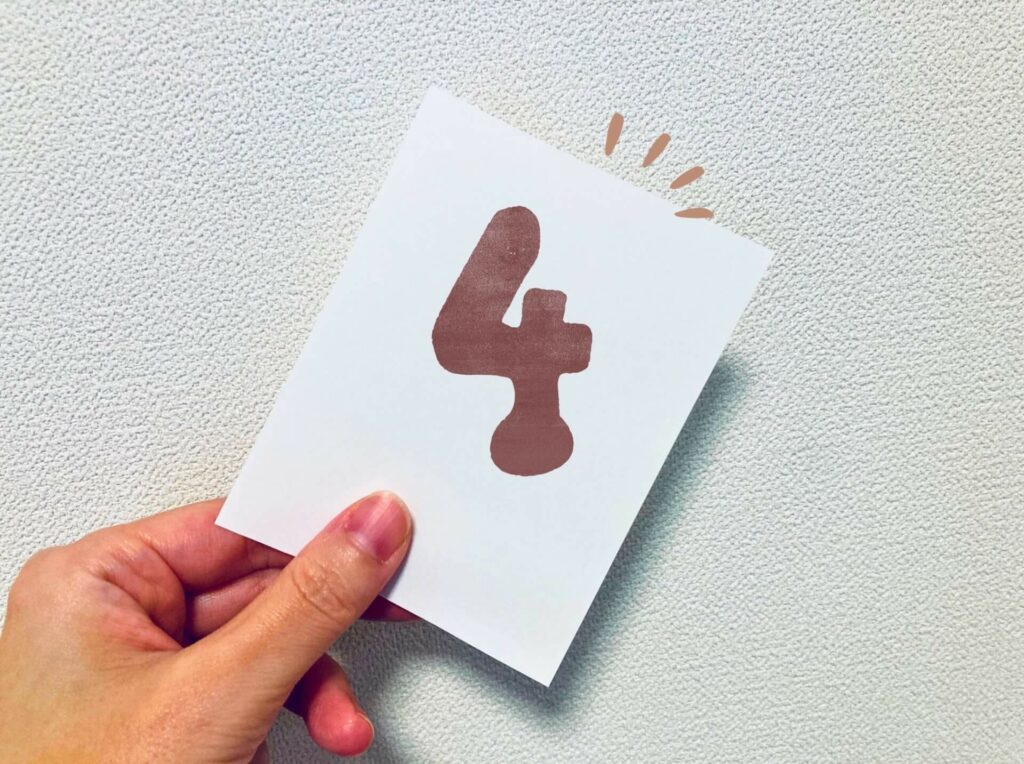
糖尿病は原因によって4つに分類されます。
- 1型糖尿病
- 2型糖尿病
- その他の特定の機序、疾患によるもの
- 妊娠糖尿病
1型糖尿病はもともと体内で血糖を下げるホルモンである、インスリンを生成できない病気です。そのため、外からインスリンを補充する必要があります。
2型糖尿病は後天的に生成できるインスリンの分泌量が少なくなったり、インスリンに対する抵抗性が上がることで相対的にインスリンが不足する病気です。食生活や喫煙、運動など生活習慣が原因の一つといわれています。
その他の糖尿病は「単一の遺伝子異常によっておこるもの」と「その他の病気や薬剤に伴って起こるもの」に分けられます。
遺伝子異常は膵β機能にかかわるものと、インスリンの伝達機能にかかわるものが多いです。膵炎や膵がんなど膵臓自体に起きる病気はインスリンを分泌する力が低下し血糖値が高くなります。また慢性肝炎や肝硬変では食後の血糖値が上昇しやすいため、糖尿病になりやすいです。
妊娠糖尿病は妊婦さんの7〜9%に起こるといわれており、肥満や2型糖尿病の家族がいる人、高齢出産、妊娠中に高血糖になったことがある人に多いです。軽度の高血糖でも早産や巨大児などの合併症のリスクが高いため、糖尿病に至っていない高血糖を「妊娠糖尿病」と診断します。
糖尿病の分類表

| 1型糖尿病 | A 自己免疫性 | 膵β細胞の破壊、絶対的インスリン欠乏 |
| B 特発性 | ||
| 2型糖尿病 | A インスリン分泌低下 | |
| B インスリン抵抗性があがることで、インスリンの相対的不足を伴う | ||
| その他の特定機序、疾患によるもの | A 遺伝因子として遺伝子異常がみられるもの | ・膵β機能に関わる遺伝子異常 ・インスリン作用の伝達機能に関わる遺伝子異常 |
| B ほかの疾患、条件に伴うもの | ・膵外分泌疾患 ・内分泌疾患 ・肝疾患 ・薬剤や化学物質によるもの ・感染症 ・免疫機序による稀な病態 ・その他の遺伝的症候群で糖尿病を伴うことの多いもの | |
| 妊娠糖尿病 | 妊娠中に初めて発見または発症した糖尿病に至っていない高血糖 |
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
糖尿病は何系疾患?原因は?

糖尿病はインスリンの作用不足により、高血糖状態が慢性的に継続する病気です。ここでは、1型糖尿病と2型糖尿病それぞれの原因について解説します。
1型糖尿病の原因

1型糖尿病は膵臓のランゲルハンス島に炎症が起こり、インスリンをつくるβ細胞が破壊される病気です。そのためインスリンが体内で作られなくなり、血液中の糖分が細胞に取り込まれないことで高血糖になります。原因ははっきりしていませんが、誘因といわれているのは遺伝因子やウイルス感染などです。
肥満や生活習慣は関係なく、細菌やウイルスから体を守る機能である免疫細胞が体内のβ細胞を標的にして破壊してしまいます。
2型糖尿病の原因

2型糖尿病はインスリンが効きにくい状態(インスリン抵抗性)やインスリンの分泌が少ない状態をおこす遺伝的要因と、食べ過ぎや運動不足、肥満、ストレスなどの生活習慣の加齢が加わることで起こる病気です。
インスリン抵抗性は肥満がある人や脂質異常症、高血圧、痛風を合併する人に多いです。また内臓脂肪型の肥満がある人もインスリン抵抗性が起き、2型糖尿病を発症しやすくなります。
食べ過ぎなどで高血糖になると、正常範囲内に血糖値を保とうとしてインスリンを通常より多く分泌しますが、持続的に高血糖状態が続くと膵臓が疲れてしまいインスリンを分泌する能力が低下しやすいです。特に欧米人と比べて、日本人などのアジア人にインスリンの分泌低下が起きやすいことが知られています。
糖尿病の症状は?分類別に解説
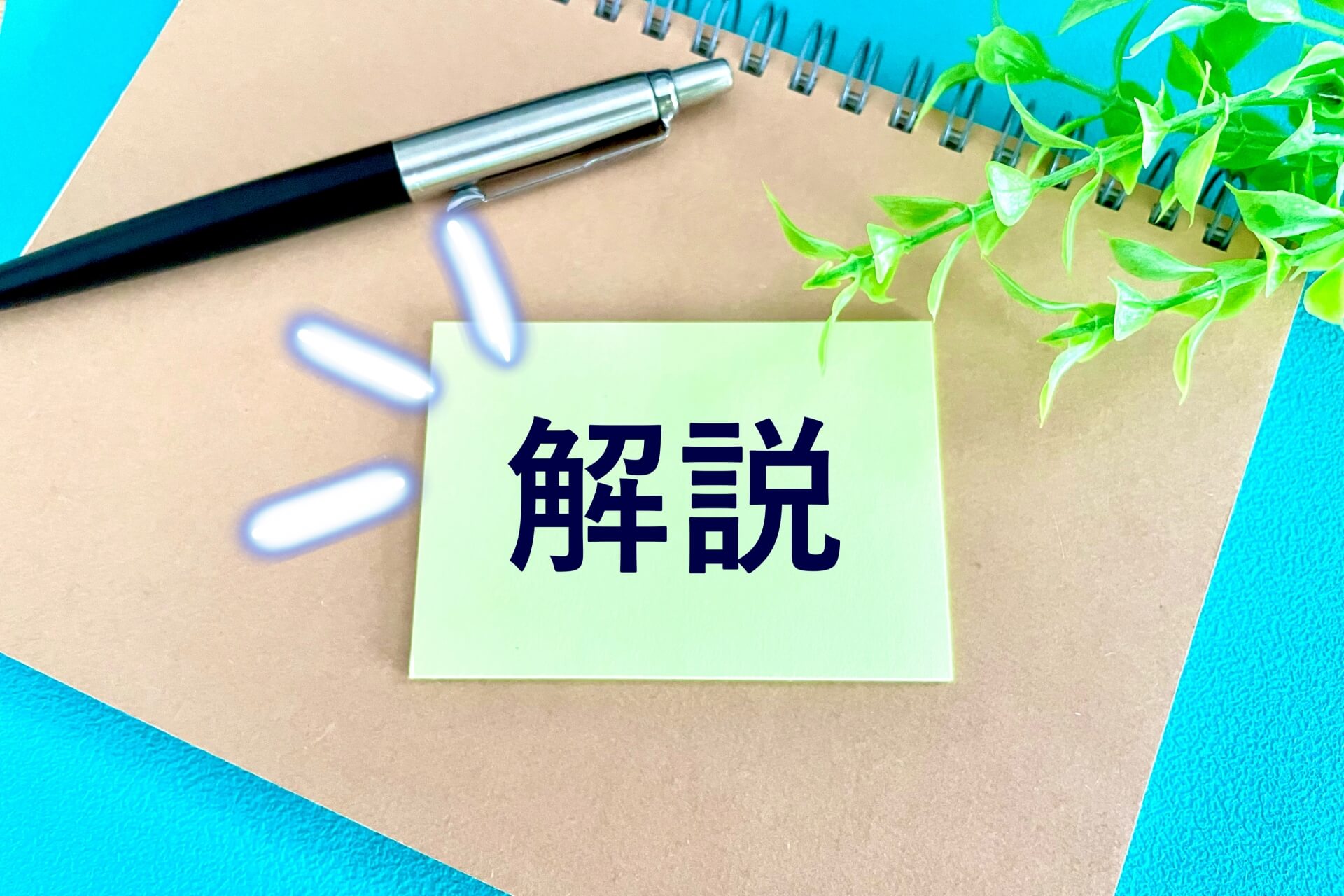
ここでは、糖尿病にみられる自覚症状と、合併症によってあらわれる症状について解説します。
糖尿病の自覚症状
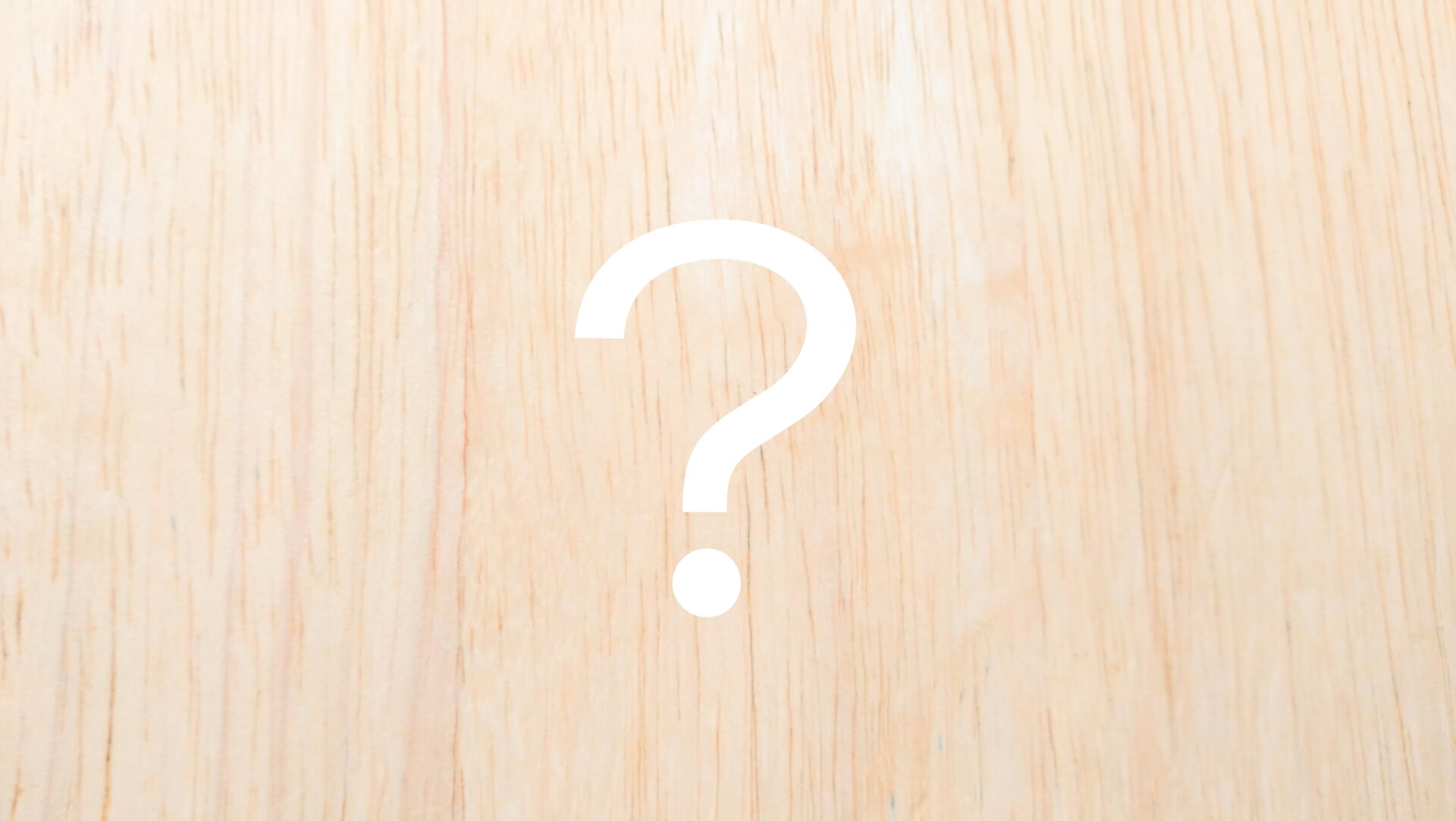
糖尿病初期はほとんど自覚症状がみられません。高血糖が持続するようになると、次のような症状が現れます。
- 尿の量が多くなる(多尿)
- のどがよく乾く(口喝)
- 水をよく飲む(多飲)
- 疲れやすい、だるい
- よく食べているのに体重が減る
糖尿病の合併症による症状

糖尿病が進むと、合併症による症状がみられます。
- 目がかすむ、視力が低下する
- 足がむくむ
- 足がしびれて痛い
- 立ち眩みが起きる
- 傷が治りにくい、化膿しやすい
糖尿病患者に特有の合併症として、「3大合併症」と呼ばれるものがあり、糖尿病性網膜症と糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害の3つです。
糖尿病性網膜症により網膜が高血糖で障害され、目がかすんだり、視力が低下したりします。症状が進行すると失明に至る場合もあり、糖尿病で失明する人は毎年3,000人以上と多いです。
糖尿病性腎症の進行により足がむくみます。この症状が出るころには腎臓の機能がかなり低下しており、血圧のコントロールやたんぱく質の管理を厳格に実施しなければなりません。症状が進行して腎不全になると透析療法が必要です。
糖尿病性神経障害により末端神経が障害されて手足がしびれたり、痛みが出たりします。痛みや熱さに鈍くなる、ひどいたちくらみが起こるなどの症状もみられます。
また高血糖は免疫機能も低下させるため、感染症にかかりやすいです。その結果傷が治りにくくなり、化膿しやすいという症状が出ます。かぜやインフルエンザ、肺炎、結核、膀胱炎、水虫などによりいっそう注意が必要です。
糖尿病は治る?
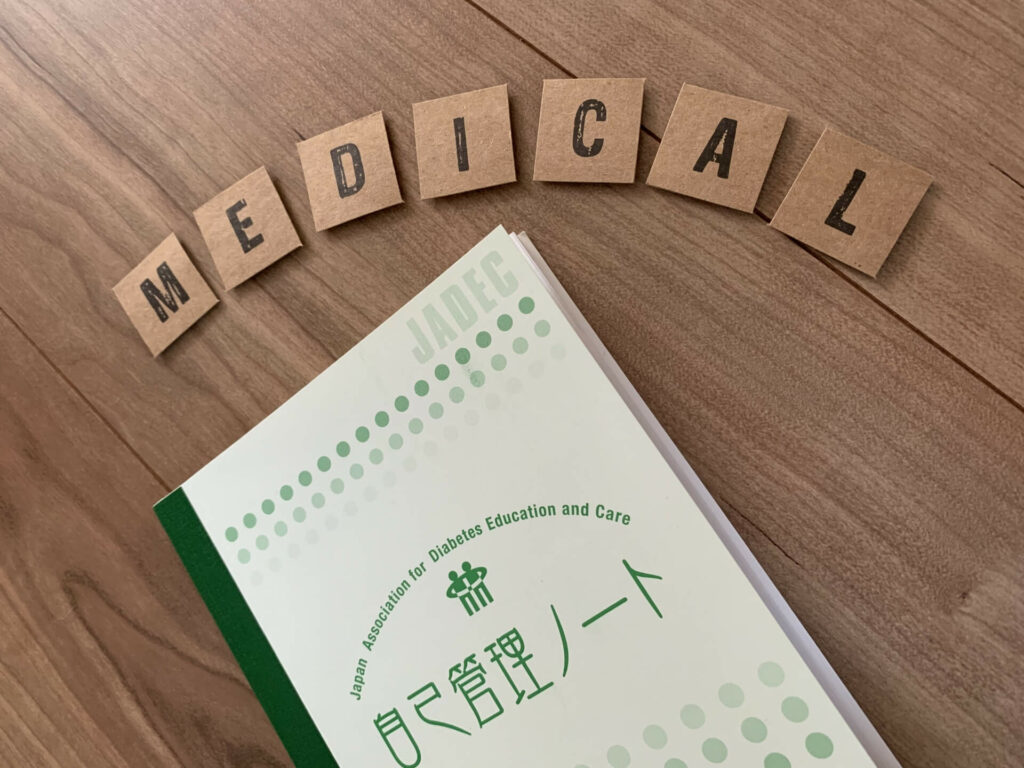
糖尿病の治療の目標は、血糖や体重、血圧、脂質の適切な状態を維持することで糖尿病の合併症を予防し、健康な人と同じような日常生活や充実した人生を送ることです。
糖尿病の合併症は糖尿病性合併症である網膜症や腎臓の病気、神経障害と、動脈硬化症と呼ばれる心筋梗塞や脳梗塞、足壊疽に分けられます。これらの合併症を予防するために重要だと言われていることが以下の5つです。
●合併症を防ぐために大切なこと
- 早期に治療を開始すること
- 低血糖や体重増加が頻回に起きないようにすること
- 食後の高血糖を持続させないこと
- 膵臓のβ細胞が疲弊しないように生活習慣を改善すること
- 高血圧や脂質異常症など、他のリスクに対しても注意すること
2型糖尿病の治療
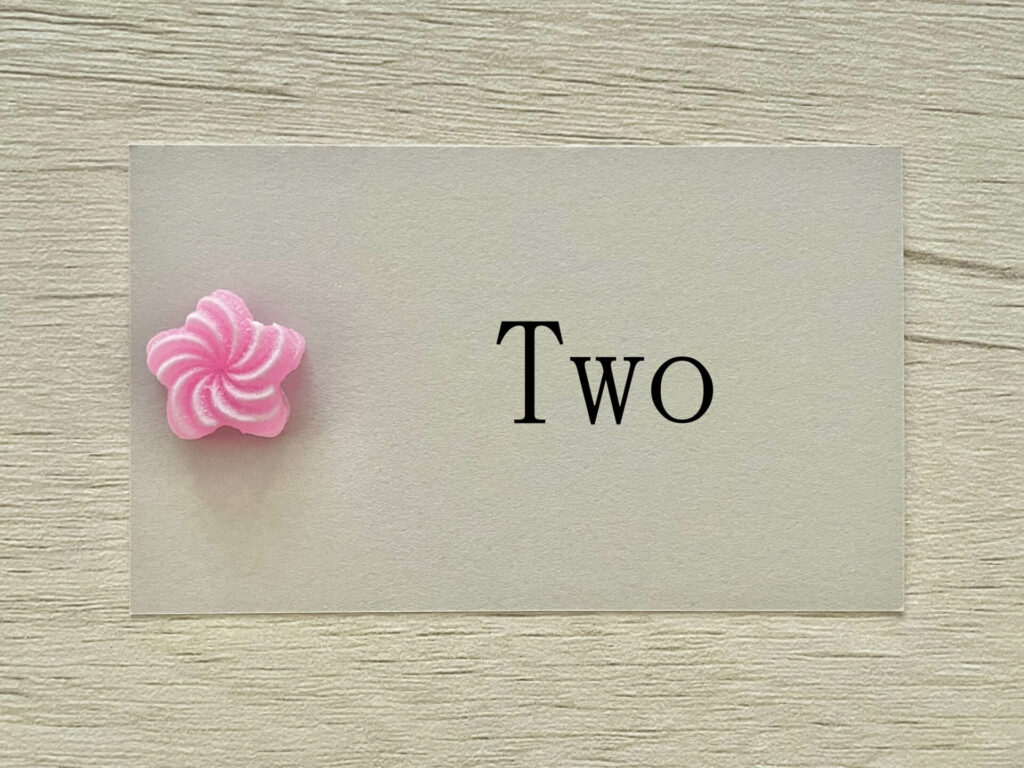
糖尿病はインスリンの働きが弱くなる「インスリン抵抗性」と、インスリンの分泌量が低下する「インスリン分泌不全」が原因で発症します。糖尿病の治療は「インスリン抵抗性」と「インスリン分泌不全」を改善することであり、食事療法と運動療法、薬物療法が主に適用されます。
食事療法
食事療法はすべての糖尿病患者にとって基本的な治療方法です。
食事療法のポイントをまとめましたので、チェックしてみてください。
- 適正なエネルギー量を知りましょう。
摂取エネルギー量(kcal)=標準体重(kg)×身体活動量(kcal/kg/標準体重)
*標準体重:[身長(m)]の2乗×22
*身体活動量
25~30:軽い労作(デスクワークが多い仕事)
30~35:普通の労作(立ち仕事が多い仕事)
35~:重い労作(力仕事が多い仕事)
食事で適切なエネルギー量を摂取することでインスリンの分泌量が改善され、インスリンの働きも良くなるため血糖が下がりやすいです。
食事以外にもお菓子やジュースなどの清涼飲料水は糖を多く含み、血糖や中性脂肪を上昇させやすいため摂取を控えるようにしましょう。
食事の回数は1日3回を原則とし、4〜5時間の間隔を空けましょう。1日1回や2回の食事でまとめ食いをすると、インスリンを分泌する膵臓のβ細胞に過剰な負担をかけてしまい、糖尿病の悪化につながります。
反対に、極端な摂取エネルギー量の制限は継続が難しく、必要な栄養素も不足するため避けましょう。まずは過剰な分の食事を減らして、体重の変化を確認しながら徐々に食事量を調整してみてください。
- 健康を保つために必要な栄養素
エネルギーのもととなる炭水化物や脂質、たんぱく質をバランスよく摂取しましょう。割合としては炭水化物をエネルギー量の50〜60%、たんぱく質を標準体重1㎏あたり1〜1.2g、残りを脂質で摂ると良いです。
食後の血糖値は主に炭水化物に含まれる糖質によって決定するため、炭水化物の量を把握する必要があります。しかし極端に糖質を制限することで相対的にたんぱく質や脂質の摂取率が高まります。その結果長期的に糖尿病性腎症や動脈硬化が進行する恐れがあるため、バランスのよい食事を心がけましょう。
たんぱく質は筋肉や臓器などを構成するほかにも様々な働きをしています。動脈硬化を予防するためにも大豆製品などの植物性たんぱく質を積極的に摂取するようにしましょう。
カルシウムなどのミネラルは、骨や歯を形成する働きがあります。野菜は1日350gを目標に摂取し、多くの食物繊維やビタミンを摂るようにしましょう。食物繊維はほとんど消化吸収されないため食後の血糖値を上げないだけでなく、腸の中で糖質の吸収を妨げて血糖の上昇を抑える働きがあります。
- 外食するときに血糖を上げ過ぎない工夫
外食やお惣菜は、一般的にエネルギー量が高く、カロリーが過剰になりやすいです。また味付けが濃いため塩分や砂糖を摂りすぎてしまい、野菜やミネラルが不足しがちになります。普段からお店のメニュー表などにある摂取カロリーを確認するようにしましょう。
また外食の機会が多いと食物繊維が不足しがちになるため、家の食事で野菜や海藻類、キノコ類を積極的に摂取してください。麺類や丼もの、ファストフードは避け、和食中心の食事が理想的です。
運動療法
定期的に運動することでブドウ糖や脂肪をエネルギーに変えやすくなり、筋肉や肝臓などでエネルギーを消費できる体になります。その結果インスリンの働きが高まることで「インスリン抵抗性」が改善され、膵臓の負担も軽減し効率よく血糖値を下げられるでしょう。
食事療法と組み合わせることで効果が上がり、生活習慣病の改善と心筋梗塞や脳梗塞などの心血管病の予防もできます。
では、どのような運動を行うとよいのでしょうか。
一般的にはややきついと感じるが、他人とおしゃべりできる程度の運動を約20〜60分継続できる有酸素運動が推奨されています。
有酸素運動とはウォーキングやジョギング、ラジオ体操、自転車、水泳などの息を吸い込みながら持続的に全身の筋肉を使う運動です。体調を崩さないように徐々に運動の強さと量を増やしていくようにし、体調不良を感じたらすぐに主治医に相談しましょう。運動の前後に準備体操や整理運動を行うことも大切です。
運動による血糖値への効果は12〜72時間継続しますが、1週間でほとんどなくなってしまうため週3回以上実施できると良いでしょう。
薬物療法
1型糖尿病の人や、食事療法・運動療法で改善がみられない人は薬物療法が必要です。
薬物療法には血糖値を下げる飲み薬で血糖値をコントロールする方法と、注射薬でインスリンを補う方法があります。
飲み薬はインスリンを出しやすくしたり、糖の吸収を抑えたり排泄を高めるものです。
注射薬はインスリン注射と呼ばれ、患者さん自身でおなかや太ももに注射し、体内に足りていないインスリンを補充して血糖値をコントロールします。
糖尿病は遺伝する?
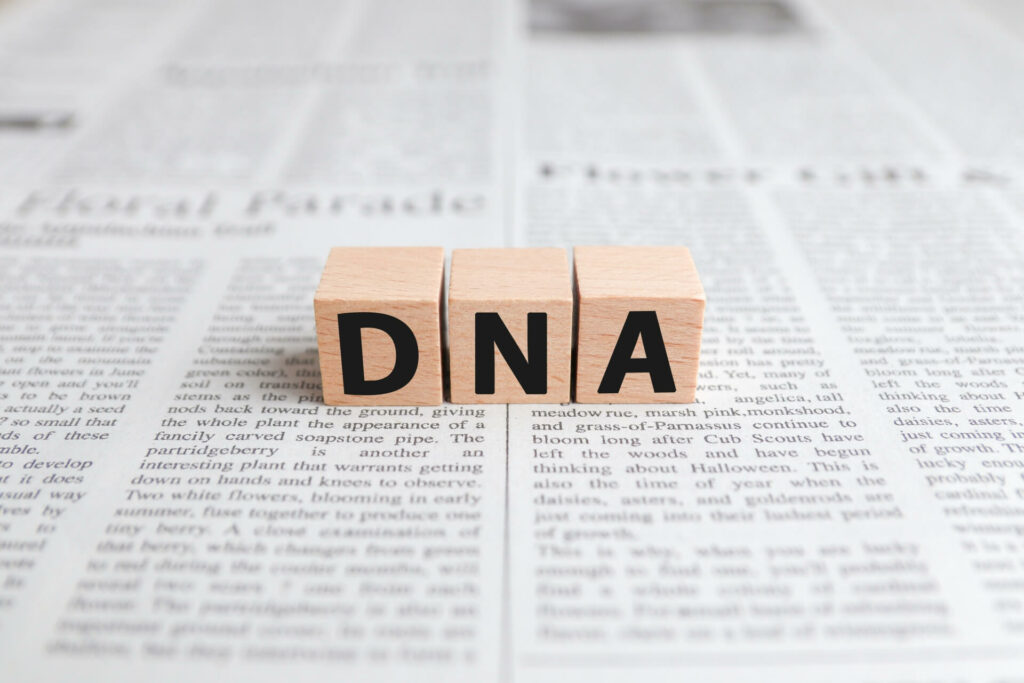
2型糖尿病は遺伝傾向があり、両親ともに糖尿病であった場合、40〜50%の確率で発症するといわれています。1型糖尿病の場合は両親ともに1型糖尿病の人の発症率は3〜5%、どちらか一方が1型糖尿病の人の発症率は1〜2%です。
糖尿病になりやすい体質が遺伝すると考えられており、さらに生活習慣などの環境因子が加わることで糖尿病を発症します。そのため、両親が糖尿病の人は生活習慣を意識することが糖尿病の予防につながります。
Q&A

糖尿病は4つに分類されますが、それぞれは?
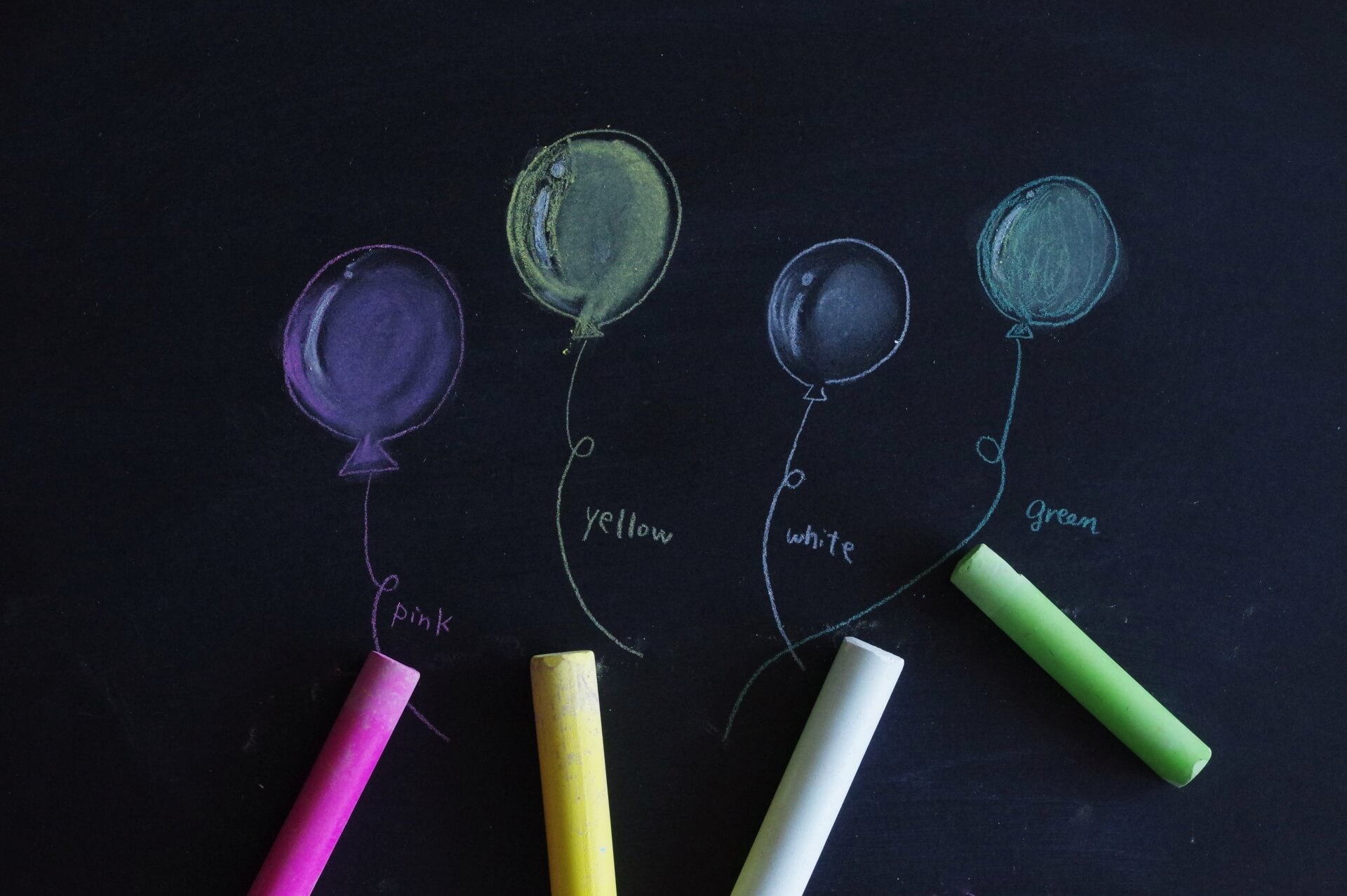
1型糖尿病は先天的にインスリンの分泌量が少なく、高血糖状態が続く病気です。
2型糖尿病は生活習慣によって高血糖が続いた結果、インスリンの分泌量が低下したりインスリン抵抗性が高くなることで高血糖になってしまいます。
その他の病気による糖尿病は遺伝子異常や膵炎、膵がんによってインスリンが分泌できなくなり、糖尿病になります。
妊娠糖尿病は肥満や2型糖尿病の家族がいる人、高齢出産、妊娠中に高血糖になったことがある人に多いです。軽度の高血糖でも早産や巨大児などの合併症のリスクが高いため、糖尿病に至っていない高血糖を「妊娠糖尿病」と診断します。
糖尿病の1型と2型の違いはなんですか?

1型糖尿病は先天的に膵臓のβ細胞が破壊されたり、消失していたりするためインスリン分泌が少なかったり、なくなったりします。そのためインスリンを補充するインスリン療法が必要です。また1型糖尿病は小児から思春期に発症することが多いです。
2型糖尿病は過食や運動不足、肥満などからインスリン分泌低下やインスリン抵抗性が生じます。そのため食事療法や運動療法で生活習慣を改善することで症状が緩和される可能性があります。2型糖尿病は加齢に伴って発症しやすく、中高年から高齢者に多いです。
1型糖尿病はどのように分類されますか?

急性発症、劇症、緩徐進行の3つに分類されます。
- 急性発症:インスリンを生成する膵臓のランゲルハンス島に対して攻撃する免疫が陽性であることが多いです。高血糖症状が出て3か月以内にケトーシスやケトアシドーシスになってしまい、インスリン療法が必要となります。
- 劇症:自己免疫の関与が不明です。高血糖症状出現後1週間以内にケトーシスやケトアシドーシスになるなど重症化しやすいためすぐにインスリン治療を開始する必要があります。
- 緩徐進行:自己免疫が陽性であることが多いが、診断されても進行がゆっくりであるためインスリン療法を必要としません。
糖尿病の分類と割合は?

糖尿病患者の90%以上が2型糖尿病であり、1型糖尿病患者は5%以下です。
まとめ
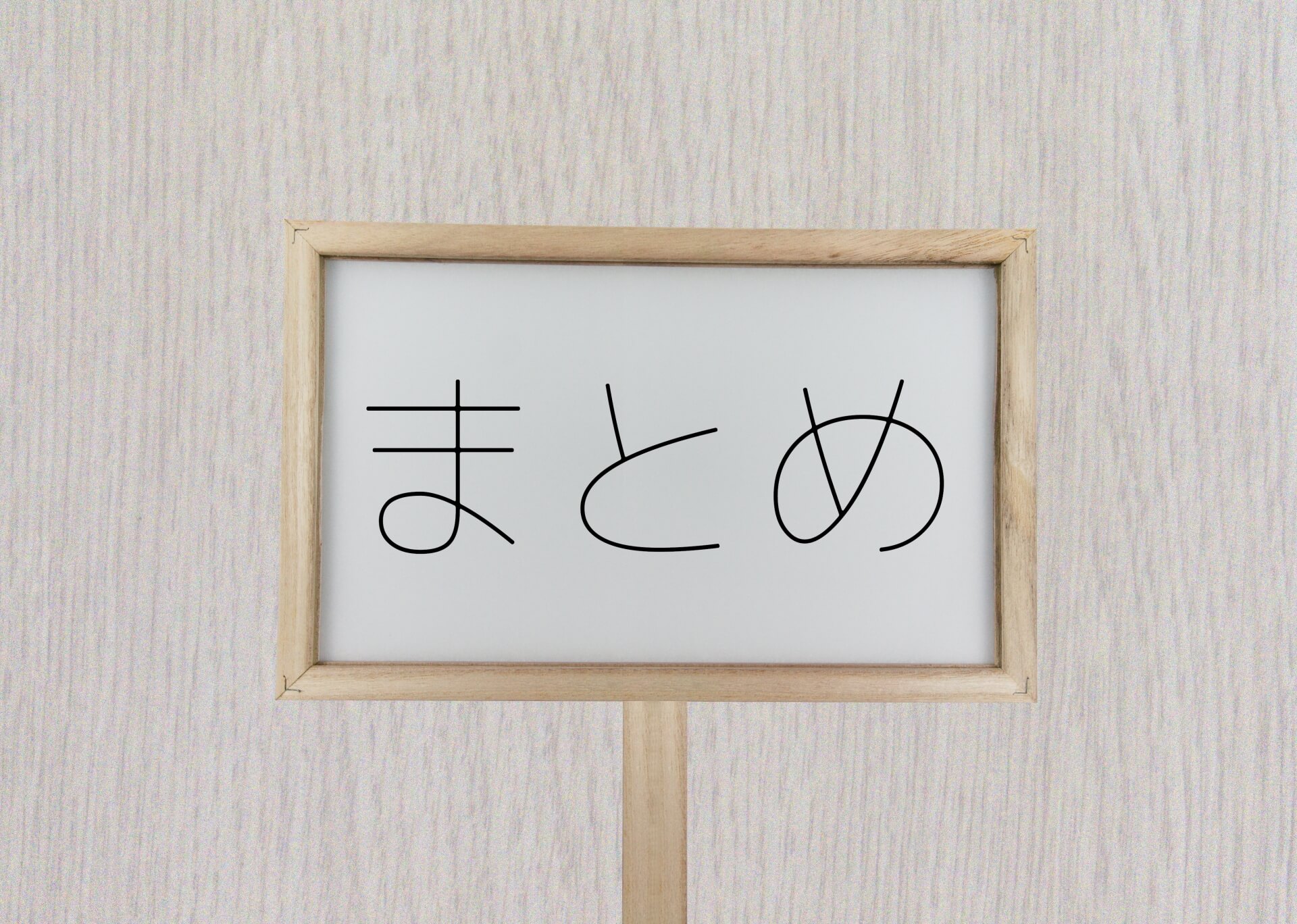
いかがでしたか?
今回は糖尿病の分類とそれぞれの原因や治療法についてまとめました。
糖尿病は以下の4つに分類されます。
- 1型糖尿病
- 2型糖尿病
- その他の遺伝子異常や疾患によるもの
- 妊娠糖尿病
本記事を読めばそれぞれ原因が異なり、治療法や診断基準、発症時期が違うことがわかるでしょう。
特に糖尿病患者の90%以上を占める2型糖尿病は、生活習慣病と呼ばれ誰でも発症する可能性があります。家族で糖尿病を発症している人がいる場合は、自分が発症するリスクが高いと考え、生活習慣を見直して予防に努めましょう。