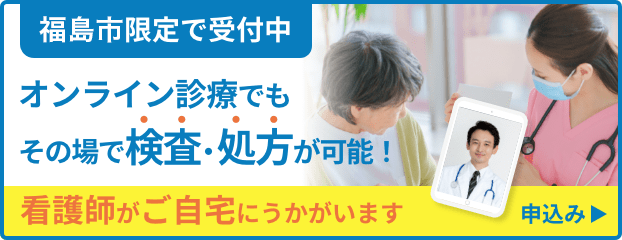糖尿病薬の副作用は?低血糖に注意!糖尿病は血糖コントロールが大切
糖尿病は、血糖値のコントロールが求められる病気です。糖尿病患者が良好な状態を保つためには、生活習慣の改善や薬物治療が欠かせません。
しかし、そのために服用する糖尿病薬には、副作用のリスクも存在します。特に注意が必要なのは、血糖値を下げる薬による「低血糖」という副作用です。
低血糖は、血糖値が異常に低くなることで引き起こされます。
症状は意識障害やけいれんなど身体にさまざまな症状をもたらします。
日常生活に影響を与えるだけでなく、危険な状態になりかねません。
本記事では、糖尿病薬の副作用について紹介し、糖尿病の血糖コントロールの方法も紹介します。

名倉 義人 医師
○経歴
・平成21年
名古屋市立大学医学部卒業後、研修先の春日井市民病院で救急医療に従事
・平成23年
東京女子医科大学病院 救急救命センターにて4年間勤務し専門医を取得
・平成27年
東戸塚記念病院で整形外科として勤務
・令和元年
新宿ホームクリニック開院
○資格
救急科専門医
○所属
日本救急医学会
日本整形外科学会
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
糖尿病薬で注意したい副作用は低血糖

薬によって副作用は異なりますが、多くの糖尿病の薬で共通して起こる副作用が「低血糖」です。
「低血糖」とは、血糖値が正常範囲以下に低下した状態のことを指します。
低血糖の症状

重篤な低血糖では意識を失うことがあり、最悪の場合、死に至るような重大な副作用と言えます。
低血糖の症状は以下の通りです。
- 発汗
- 動悸
- 手の震え
- 空腹感
- 顔面蒼白
- 意識が朦朧とする
- 異常行動
- けいれん
このような症状が出た場合は、低血糖を疑いましょう。適切な対処が必要です。
低血糖の原因

低血糖を起こす原因として、以下のようなものが考えられます。
- 不規則な食事
- 薬の飲み間違い
- 激しい運動
- 飲酒
スルホニル尿素薬を使用していたり、インスリン注射を使用していたりする人は、特に低血糖に注意しましょう。
低血糖時の対処法
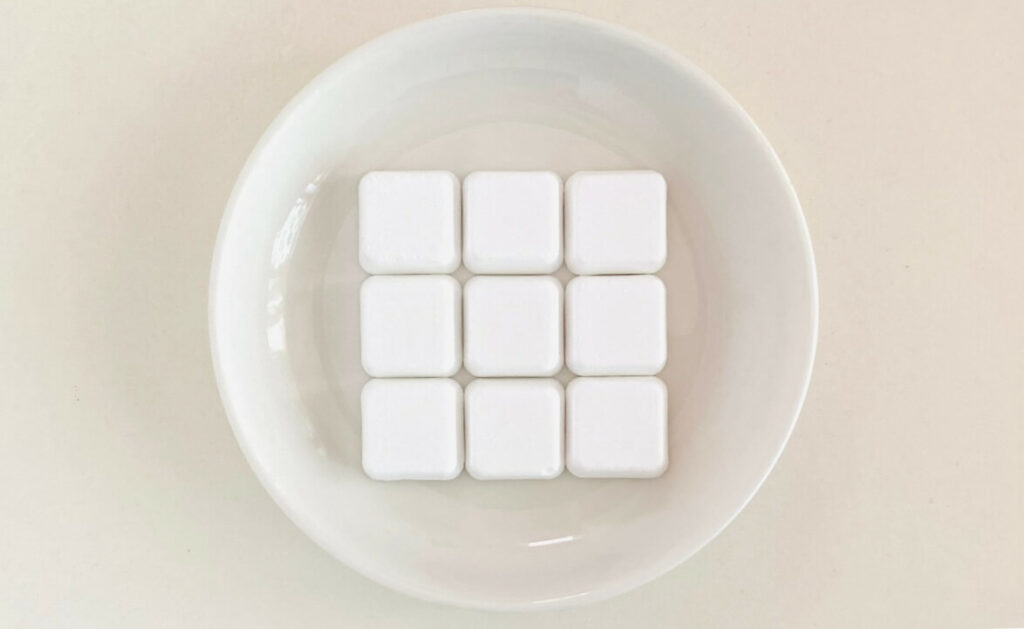
低血糖は血糖値が下がった状態なので、速やかにブドウ糖を摂取します。
以下の量は、低血糖時に摂取するブドウ糖の目安です。
- ブドウ糖(10g)
- ブドウ糖を含む清涼飲料水(150〜200mL)
- 砂糖(20g)
ブドウ糖摂取後はしばらく安静にします。15分ほどしても症状が改善しない場合には、再度ブドウ糖を摂取します。
主治医に、低血糖時に必要なブドウ糖の量を確認しておきましょう。常備しておくか、常に手の届くところに置いておくと安心です。
ブドウ糖を準備しておくだけでなく、周囲の人や家族にも低血糖の症状や対処法を知っておいてもらいましょう。
また、糖尿病患者用IDカードを身につけておくと低血糖になってしまった時の対策になります。
このカードは、日本糖尿病協会が発行しており、自分が糖尿病の治療中であることを示すカードです。
緊急時に、周囲の人や医療関係者に糖尿病であることを知らせることができ、適切な処置を促します。
血糖値を下げる飲み薬にはどんな薬がある?
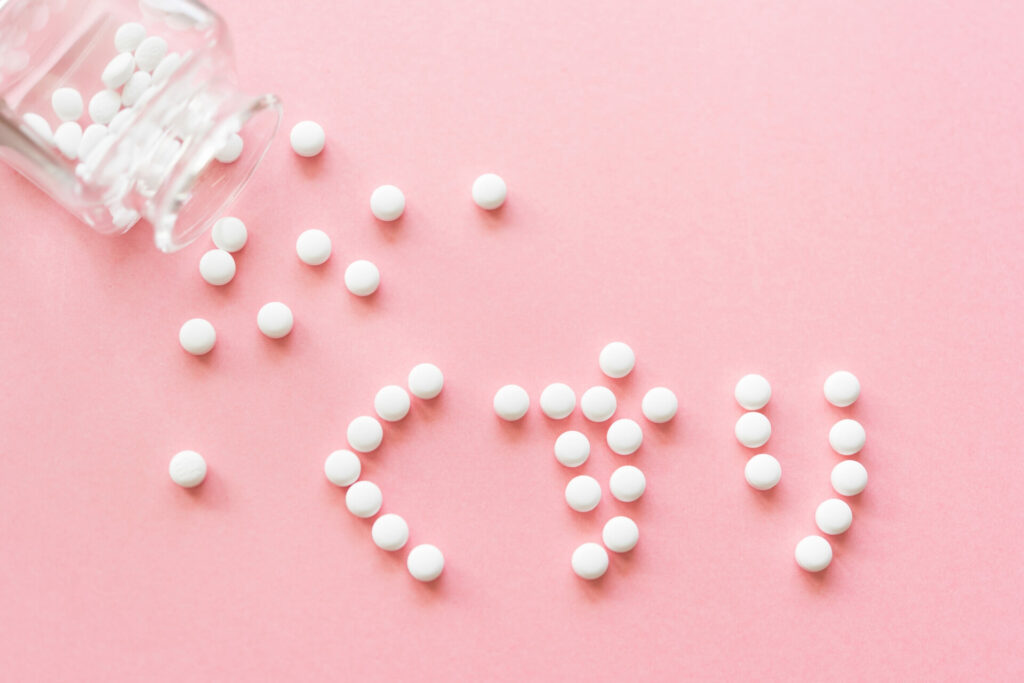
血糖値を下げるための薬には、3つの種類があります。
- インスリンを出しやすくする薬
- インスリンを効きやすくする薬
- 糖の吸収や排泄を調節する薬
糖尿病に使われる主な薬を紹介します。
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
インスリンを出しやすくする薬

インスリンを出しやすくする薬の作用は、膵臓のβ細胞に働きかけてインスリンの分泌を促します。
インスリン不足を補う薬です。
スルホニル尿素薬
経口血糖下降薬の中では、最も古い薬です。確実な血糖下降作用を持つため、低血糖に注意しましょう。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 効能・効果 | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| グリメピリド | アマリール | ・成人では1日0.5〜1mgより開始 ・1日1〜2回(朝又は朝夕)食前又は食後に経口投与 ・維持量は通常1日6mgまで | インスリン非依存型糖尿病成人型糖尿病 | ・低血糖 ・貧血 ・白血球減少 ・LDH上昇 ・γ−GTP上昇 ・BUN上昇 ・嘔気 ・嘔吐 ・心窩部痛 ・下痢 |
| グリクラジド | グリミクロン | ・成人では1日40mgより開始 ・維持量は通常1日40〜120mg | インスリン非依存型糖尿病成人型糖尿病 | ・低血糖 ・脱力感 ・高度空腹感 ・発汗 ・心悸亢進 ・振戦 ・頭痛 ・知覚異常 ・不安 ・興奮 |
| グリベンクラミド | オイグルコン錠ダオニール錠 | ・1日量1.25mg〜2.5mgを経口投与 ・1日最高投与量は10mg | インスリン非依存型糖尿病(食事療法・運動療法で十分な効果が得られない場合のみ | ・低血糖 ・脱力感 ・高度空腹感 ・発汗 ・そう痒感 ・脱毛 ・精神障害 ・意識障害 ・低血糖症状 ・動悸 |
(参考:日経メディカルより)
速効型インスリン分泌促進薬
内服後からすぐに効き始め、短時間でインスリンの分泌を促し、食後の高血糖を改善する効果があります。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 効能・効果 | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| ナテグリニド | スターシス錠 | ・1回90mgを1日3回毎食直前に経口投与 ・経過を十分に観察しながら1回量を120mgまで増量できる ・本剤の投与は毎食前10分以内(食直前)とすること | 2型糖尿病における食後血糖推移の改善(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・低血糖 ・低血糖症状 ・空腹感 ・冷汗 ・めまい ・ふらつき ・動悸 ・脱力感 ・気分不良 ・ふるえ |
| ファスティック錠 | ・1回90mgを1日3回毎食直前に経口投与 ・経過を十分に観察しながら1回量を120mgまで増量できる ・本剤の投与は毎食前10分以内(食直前)とすること | 2型糖尿病における食後血糖推移の改善(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・低血糖 ・低血糖症状 ・空腹感 ・冷汗 ・めまい ・ふらつき ・動悸 ・脱力感 ・気分不良 ・ふるえ | |
| ミチグリニドカルシウム水和物 | グルファスト錠 | ・1回10mgを1日3回毎食直前に経口投与 ・本剤の投与は毎食直前(5分以内)とすること | 2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・低血糖 ・低血糖症状 ・めまい ・空腹感 ・振戦 ・脱力感 ・冷汗 ・意識消失 ・発汗 ・悪寒 |
| レパグリニド | シュアポスト錠 | ・1回0.25mgより開始し1日3回毎食直前に経口投与 ・1回量を1mgまで増量することができる ・本剤の投与は毎食直前(10分以内)とすること | 2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・低血糖 ・低血糖症状 ・めまい ・ふらつき ・ふるえ ・空腹感 ・冷汗 ・意識消失 ・肝機能障害 ・血清カリウム上昇 |
(参考:日経メディカルより)
DPP-4阻害薬
食事を取った時に、膵臓からのインスリンの分泌を調整し、血糖値を下げる薬です。
他の薬と併用しなければ低血糖を起こしにくく、体重を増やしにくいことも特徴です。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 効能・効果 | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| アログリプチン安息香酸塩 | ネシーナ錠 | ・25mgを1日1回経口投与 ・腎機能の程度に応じて、投与量を適宜減量すること | 2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・低血糖 ・腹痛 ・便秘 ・過敏症 ・発疹 ・そう痒 ・じん麻疹 ・鼓腸 ・胃腸炎 ・頭痛 |
| オマリグリプチン | マリゼブ錠 | ・25mgを1週間に1回経口投与 ・本剤の服用を忘れた場合、気づいた時点で1回分を服用 | 2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・低血糖 ・便秘 ・下痢 ・湿疹 ・ALT増加 ・グリコヘモグロビン増加 ・血中ブドウ糖増加 ・低血糖症状 ・意識消失 |
| サキサグリプチン水和物 | オングリザ錠 | ・5mgを1日1回経口投与 | 2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・低血糖 ・腹痛 ・浮腫 ・腸閉 ・便秘 ・腹部膨満 ・嘔吐 ・めまい |
| シタグリプチンリン酸塩水和物 | グラクティブ錠ジャヌビア錠 | ・50mgを1日1回経口投与 | 2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・低血糖 ・腹痛 ・便秘 ・浮動性めまい ・感覚鈍麻 ・糖尿病網膜症悪化 ・回転性めまい ・上室性期外収縮 ・心室性期外収縮 ・動悸 |
| テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | テネリア錠 | ・20mgを1日1回経口投与 ・経過を十分に観察しながら40mg1日1回に増量できる | 2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・低血糖 ・腸閉塞 ・便秘 ・腹部膨満 ・腹痛 、 腹部不快感 ・悪心 ・鼓腸 |
(参考:日経メディカルより)
GLP-1受容体作動薬
GLP-1は、もともと私たちの体にあるホルモンです。GLP-1受容体作動薬は、GLP-1を補うための薬です。注射薬と内服薬があります。
血糖値が高いときにインスリンの分泌を促し、血糖値を上げるホルモンのひとつであるグルカゴンの分泌を抑制し、血糖値を下げます。
低血糖を起こしにくいとされている薬ですが、SU薬やインスリンと併用する場合には、注意しましょう。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 効能・効果 | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| セマグルチド | リベルサス錠 | ・1日1回7mgを維持用量とし経口投与 ・1日1回3mgから開始し、4週間以上投与した後、 ・1日1回7mgに増量 | 2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・悪心 ・下痢 ・急性膵炎 ・嘔吐 ・腹痛 ・食欲減退 ・浮動性めまい ・味覚異常 ・糖尿病網膜症 |
(参考:日経メディカルより)
インスリンを効きやすくする薬

インスリン抵抗性を改善し、インスリンが効きやすくする薬です。
ビグアナイド薬
ビグアナイド薬は、肝臓での糖新生抑制作用があります。
その他にも、インスリン抵抗性改善による糖取り込み促進作用、小腸での糖吸収抑制作用といった複数の作用があります。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 効能・効果 | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| メトホルミン塩酸塩 | メトグルコ錠 | ・1日500mgより開始し、1日2〜3回に分割して食直前又は食後に経口投与 ・1日最高投与量は2250mgまで | ・2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) ・多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発 | ・低血糖 ・脱力感 ・高度空腹感 ・発汗 ・下痢 ・悪心 ・食欲不振 ・腹痛 ・嘔吐 |
| ブホルミン塩酸塩 | ジベトス錠 | ・1日量100mgより開始し、1日2〜3回食後に分割経口投与 ・1日最高投与量は150mgまで | インスリン非依存型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・肝機能異常 ・全身倦怠感 ・頭痛 ・頭重 ・眠気 ・低血糖症状 ・食欲不振 ・悪心 ・嘔吐 ・下痢 |
(参考:日経メディカルより)
チアゾリジン薬
インスリンに対する体の感受性を高める薬です。
インスリンの効きを改善し、糖の取り込みや糖利用の改善、糖の放出を抑える効果があります。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 効能・効果 | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| ピオグリタゾン塩酸塩 | アクトス錠 | ・15〜30mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与 ・(インスリン製剤を使用する場合)15mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与 | インスリン抵抗性が推定される場合の2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・浮腫 ・CK上昇 ・LDH上昇 ・AST上昇 ・ALT上昇 ・Al−P上昇 ・貧血 ・白血球減少 ・血小板減少 ・血圧上昇 |
(参考:日経メディカルより)
両方の効果がある薬

インスリンを効きやすくする効果と出しやすくする効果と、二つの作用をもつ薬があります。
グリミン薬
ミトコンドリアへの作用により、インスリンの分泌を促したりインスリンの抵抗性を改善したりする薬です。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 効能・効果 | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| イメグリミン塩酸塩 | ツイミーグ錠 | ・1回1000mgを1日2回朝、夕に経口投与 | 2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・低血糖 ・ 膀胱炎 ・食欲減退 ・糖尿病網膜症 ・糖尿病性網膜浮腫 ・糖尿病性黄斑浮腫 ・悪心 ・下痢 ・便秘 ・嘔吐 |
(参考:日経メディカルより)
糖の吸収や排泄を調節する薬

糖の吸収をゆっくりにして食後の急激な血糖値の上昇を抑える薬や、余分な糖を排泄する作用のある薬です。
α-グルコシダーゼ阻害薬
腸での糖の吸収を遅らせて、食後の急激な血糖値の上昇を抑えます。
糖尿病の治療をし、合併症の進行を抑える薬です。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 効能・効果 | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| ミグリトール | セイブル錠 | ・1回50mgを1日3回毎食直前に経口投与 ・経過を十分に観察しながら1回量を75mgまで増量できる | 糖尿病の食後過血糖の改善(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・腹部膨満 ・鼓腸 ・下痢 ・腹痛 ・便秘 ・腸雑音異常 ・嘔気 ・食欲不振 ・口渇 ・消化不良 |
| ボグリボース | ベイスン錠 | ・1回0.2mgを1日3回毎食直前に経口投与 ・1回量を0.3mgまで増量できる | ・耐糖能異常の2型糖尿病の発症抑制 ・糖尿病の食後過血糖の改善 | ・腹部膨満 ・放屁 ・下痢 ・腹痛 ・便秘 ・軟便 ・腹鳴 ・食欲不振 ・悪心 ・胸やけ |
(参考:日経メディカルより)
SGLT2阻害薬
尿として糖の排泄を増やすことで、血液中の糖の量を減らす薬です。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 効能・効果 | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| イプラグリフロジンL−プロリン | スーグラ錠 | ・50mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与 ・経過を十分に観察しながら100mg1日1回まで増量できる | ・1型糖尿病 ・2型糖尿病 | ・頻尿 ・低血糖 ・腎盂腎炎 ・脱水 ・口渇 ・多尿 ・血圧低下 ・貧血 ・糖尿病網膜症 ・便秘 |
| ルセオグリフロジン水和物 | ルセフィ錠 | ・2.5mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与 ・経過を十分に観察しながら5mg1日1回に増量できる | 2型糖尿病(1型糖尿病患者には投与しないこと) | ・低血糖 ・腎盂腎炎 ・脱水 ・口渇 ・多尿 ・頻尿 ・血圧低下 ・膀胱炎 ・性器カンジダ ・尿路感染 |
| ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 | フォシーガ錠 | ・2型糖尿病には5mgを1日1回経口投与 ・1型糖尿病にはインスリン製剤と併用し5mgを1日1回経口投与 | ・慢性心不全 ・1型糖尿病 ・2型糖尿病 ・慢性腎臓病(末期腎不全又は透析施行中の患者を除く) | ・性器感染 ・腟カンジダ症 ・尿路感染 ・膀胱炎 ・体液量減少 ・ケトーシス ・食欲減退 ・多飲症 ・便秘 ・下痢 |
(参考:日経メディカルより)
血糖値を下げる注射薬にはどんな種類がある?

血糖値を下げる注射薬は、大きく分けて2種類あります。
- GLP-1受容体作動薬
- インスリン製剤
GLP-1受容体作動薬

GLP-1受容体作動薬は、体の中でインスリンを出しやすくする作用があります。
主に膵臓に作用し、2型糖尿病の人が使う注射薬です。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 効能・効果 | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| リキシセナチド | リキスミア | ・20μgを1日1回朝食前に皮下注射 ・投与は朝食前1時間以内 ・食後の投与は行わないこと | 2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・低血糖 ・脱力感 ・倦怠感 ・高度空腹感 ・冷汗 ・顔面蒼白 ・動悸 ・振戦 ・頭痛 ・めまい |
| エキセナチド | バイエッタ | ・1回5μgを1日2回朝夕食前に皮下注射 ・投与は原則として朝夕食前60分以内 ・食後の投与は行わないこと | 2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・低血糖 ・低血糖症状 ・脱力感 ・高度空腹感 ・冷汗 ・顔面蒼白 ・動悸 ・振戦 ・頭痛 ・めまい |
| セマグルチド | オゼンピック | ・週1回0.5mgを維持用量とし、皮下注射 ・投与を忘れた場合、次回 ・投与までの期間が2日間(48時間)以上であれば気づいた時点で直ちに ・投与 | 2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・嘔吐 ・食欲減退 ・悪心 ・下痢 ・便秘 ・リパーゼ増加 ・腹痛 ・胃腸炎 ・浮動性めまい ・腹部不快感 |
| デュラグルチド | トルリシティ | ・0.75mgを週に1回、皮下注射 ・1回投与する薬剤であり、同一曜日に投与 ・投与を忘れた場合は、次回投与までの期間が3日間(72時間)以上であれば気づいた時点で直ちに投与 | 2型糖尿病(食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合) | ・便秘 ・下痢 ・悪心 ・浮腫 ・腫脹 ・急性膵炎 ・腹痛 ・心拍数増加 ・食欲減退 |
(参考:日経メディカルより)
インスリン製剤

インスリン製剤は、インスリンそのものを補填するための薬です。自分で十分なインスリンを分泌できない人は、インスリン製剤を使用し補う必要があります。
超速効型インスリン製剤
インスリンの追加分泌を補います。そのため、食事ごとの注射が必要です。
注射後すぐに効き始め、最も作用時間が短いのが特徴です。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 注射のタイミング | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| インスリン アスパルト | ノボラピッド | 初期は1回2〜20単位を毎食直前に注射 | 速効型より作用発現が速いため食直前に投与 | ・多汗 ・低血糖 ・脱力感 ・倦怠感 ・高度空腹感 ・冷汗 ・顔面蒼白 ・動悸 ・振戦 ・頭痛 |
| フィアスプ | 初期は1回2〜20単位を毎食事開始時に皮下投与。必要な場合は食事開始後の投与もできる | ノボラピッド注より作用発現が速いため食事開始前の2分以内に投与 | ・発疹 ・糖尿病網膜症の顕在化 ・糖尿病網膜症増悪 ・リポジストロフィー ・皮下脂肪萎縮 ・皮下脂肪肥厚 ・アレルギー性皮膚疾患 ・じん麻疹 ・皮膚そう痒 ・注射部位反応 | |
| インスリン リスプロ | ルムジェブ | 1回2〜20単位を毎食事開始時に皮下注射 | ヒューマログ注と比べて作用発現が速いため、食事開始前の2分以内に投与 | ・注射部位反応 ・発赤 ・炎症 ・疼痛 ・出血 ・そう痒感 ・リポジストロフィー ・皮下脂肪萎縮 ・皮下脂肪肥厚 ・低血糖 |
| ヒューマログ | 1回2〜20単位を毎食直前に皮下注射 | 食直前(15分以内)に投与 | ・蕁麻疹 ・代謝異常 ・高血糖 ・血糖値上昇 ・低血糖 ・脱力感 ・倦怠感 ・高度空腹感 ・冷汗 ・顔面蒼白 |
(参考:日経メディカルより)
速効型インスリン製剤
インスリンの追加分泌を補います。そのため、食事ごとの注射が必要です。
注射後30分程度で効き始め、超速効型に比べゆるやかに効果が出るのが特徴です。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 注射のタイミング | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| インスリンヒト | ノボリンR | 初期は1回4〜20単位を一般に毎食前に皮下注射 | 毎食前に皮下注射 | ・疼痛 ・発赤 ・腫脹 ・硬結 ・リポジストロフィー ・皮下脂肪萎縮 ・皮下脂肪肥厚 ・低血糖 ・脱力感 ・倦怠感 |
| ヒューマリンR | 初期は1回4〜20単位を一般に毎食前に皮下注射 | 毎食前に皮下注射 | ・そう痒感 ・発赤 ・低血糖 ・脱力感 ・倦怠感 ・高度空腹感 ・冷汗 ・顔面蒼白 ・動悸 ・振戦 |
(参考:日経メディカルより)
中間型インスリン製剤
インスリンの基礎分泌を補うため、食事のタイミングに関わらず1日の中で決まった時間に注射が必要です。
注射後ゆっくりと効果が出始め、空腹時血糖の上昇を抑えます。ほぼ1日効果が持続するのが特徴です。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 注射のタイミング | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| インスリンヒト | ノボリンN | 初期は1回4〜20単位を朝食前30分以内に皮下注射 | 朝食前30分以内 | ・疼痛 ・発赤 ・腫脹 ・硬結 ・リポジストロフィー ・皮下脂肪委縮 ・皮下脂肪肥厚 ・低血糖 ・脱力感 ・倦怠感 |
| ヒューマリンN | 初期は1回4〜20単位を朝食前30分以内に皮下注射 | 朝食前30分以内に皮下注射 | ・そう痒感 ・発赤 ・低血糖 ・脱力感 ・倦怠感 ・高度空腹感 ・冷汗 ・顔面蒼白 ・動悸 ・振戦 |
(参考:日経メディカルより)
持効型溶解インスリン製剤
インスリンの基礎分泌を補います。食事のタイミングに関わらず、1日の中で決まった時間に注射が必要です。
空腹時血糖の上昇を抑え、1日の血糖値の上昇を全体的に下げる働きがあります。
ほとんどピークがなく、ほぼ1日安定した効果が見込め、中間型よりも長く効果があるのが特徴です。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 注射のタイミング | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| インスリンデテミル | レベミル | 初期は1日1回4〜20単位を皮下注射 | 注射時刻は夕食前又は就寝前のいずれでもよいが、毎日一定とする | ・アナフィラキシーショック ・呼吸困難 ・血圧低下 ・頻脈 ・発汗 ・全身発疹 ・発疹 ・血管神経性浮腫 ・浮腫 ・そう痒感 |
| インスリングラルギン | ランタス | 初期は1日1回4〜20単位を皮下注射 | 注射時刻は朝食前又は就寝前のいずれでもよいが、毎日一定とする | ・低血糖 ・脱力感 ・倦怠感 ・高度空腹感 ・冷汗 ・顔面蒼白 ・動悸 ・振戦 ・頭痛 ・めまい |
| インスリンデグルデク | トレシーバ | 初期は1日1回4〜20単位を皮下注射 | 注射時刻は毎日一定とする | ・糖尿病網膜症の顕在化 ・糖尿病網膜症増悪 ・注射部位反応 ・疼痛 ・血腫 ・結節 ・熱感 ・リポジストロフィー ・皮下脂肪萎縮 ・皮下脂肪肥厚 |
(参考:日経メディカルより)
混合型インスリン製剤(中間型との混合)
インスリンの追加分泌と基礎分泌を補います。食事に合わせて注射が必要です。
超速効型や速効型など短く作用するインスリンと長く作用する中間型インスリンを混合しています。
製剤によって配合の割合が異なるため、注射のタイミングが変わります。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 注射のタイミング | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| インスリンアスパルト | ノボラピッド30ミックス | 初期は1回4〜20単位を1日2回皮下注射 | ・1日2回朝食直前と夕食直前 ・1日1回の場合は朝食直前 | ・アレルギー ・体重増加 ・低血糖 ・脱力感 ・倦怠感 ・高度空腹感 ・冷汗 ・顔面蒼白 ・動悸 ・振戦 |
| インスリンリスプロ | ヒューマログミックス25 | 1回4〜20単位を1日2回皮下注射 | ・1日2回朝食直前と夕食直前 ・1日1回の場合は朝食直前 | ・低血糖 ・脱力感 ・倦怠感 ・高度空腹感 ・冷汗 ・顔面蒼白 ・動悸 ・振戦 ・頭痛 ・めまい |
(参考:日経メディカルより)
配合持効溶解製剤(持効型との混合)
インスリンの追加分泌と基礎分泌を補います。食事に合わせて注射が必要です。
持続型インスリン製剤と超速効型インスリン製剤を混合した製剤です。
| 一般名 | 商品名 | 用法・用量 | 注射のタイミング | 主な副作用 |
|---|---|---|---|---|
| インスリン デグルデク/インスリン アスパルト配合剤 | ライゾデグ配合注 | 初期は1回4〜20単位を1日1〜2回皮下注射 | ・1日1回投与の場合、主たる食事の直前に投与し、毎日一定とする ・1日2回投与の場合、朝食直前と夕食直前に投与する | ・そう痒 ・糖尿病網膜症の顕在化 ・糖尿病網膜症増悪 ・注射部位反応 ・疼痛 ・硬結 ・低血糖 ・脱力感 ・倦怠感 ・高度空腹感 |
(参考:日経メディカルより)
そもそも糖尿病とは?

糖尿病とは、生活習慣病のひとつです。インスリンの作用不足により、高血糖が慢性的に続く病気です。
診断は尿糖ではなく、空腹時血糖値やブドウ糖負荷試験などの血液検査の結果で判断します。
1型糖尿病と2型糖尿病の違いは?

糖尿病は、1型と2型に分けられます。
| 1型糖尿病 | 2型糖尿病 | |
|---|---|---|
| 型 | インスリン依存型 | インスリン非依存型 |
| 原因 | ・自己免疫疾患 ・インスリン分泌のための膵臓細胞を破壊 | ・遺伝的な要因 ・過食 ・運動不足 |
| 年齢 | 若い人から幅広い年代 | 成人の発症がほとんど |
| 治療 | インスリンの自己注射 | ・食事療法 ・運動療法 ・薬物療法 |
2型糖尿病は最も多いタイプで、一般的に「糖尿病」と言うと、2型の糖尿病を指すことが多いです。
糖尿病の症状は?

1型と2型では、症状が少し異なります。
| 1型糖尿病 | 2型糖尿病 | |
|---|---|---|
| 特徴 | ・症状は突然あらわれる | ・初期の段階では、全く症状がない場合が多い ・症状はゆっくり少しずつあらわれる |
| 症状 | ・普段より喉が乾く ・ひどい疲れ ・頻尿 ・急激な体重減少 | ・疲労感 ・皮膚の痒み ・手足の感覚の低下 ・感染症にかかりやすくなる ・頻尿 ・目のかすみ ・性機能問題(ED) ・傷が治りにくい ・空腹感 ・喉の乾き |
糖尿病の原因は?

1型と2型では、原因が異なります。
| 1型糖尿病 | 2型糖尿病 | |
|---|---|---|
| 特徴 | ・はっきりとした原因は分かっていない | ・遺伝性による場合がある ・40歳以上 |
| 原因 | ・体質 ・何らかの原因で膵臓の一部が破壊されている | ・肥満 ・糖尿病の人が家族にいる ・運動不足 ・乱れた食習慣 |
糖尿病の合併症は?
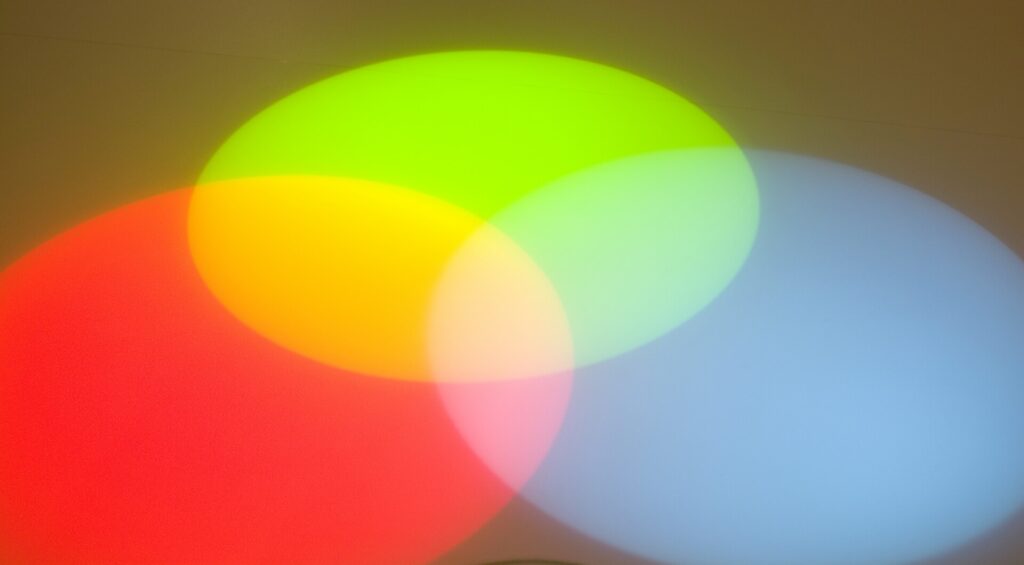
糖尿病は進行すると、合併症を起こすリスクがあります。
糖尿病にはさまざまな合併症がありますが、代表的なものは3つあり「3大合併症」と言われています。
- 糖尿病神経障害
- 糖尿病網膜症
- 糖尿病腎症
3大合併症の特徴を、以下の表にまとめました。
| 糖尿病神経障害 | 糖尿病網膜症 | 糖尿病腎症 | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | ・高血糖が続くことで神経の働きが障害される | ・高血糖が続くことで網膜の毛細血管に障害が起きる ・失明の原因になる ・末期になるまで自覚症状はほとんどない | ・高血糖が続くことで腎臓の糸球体に障害が起きる ・進行するにつれて尿たんぱくが増加 ・人工透析が必要になることもある |
| 症状 | ・足のしびれ ・冷え ・つる ・立ちくらみ ・排尿障害 ・勃起障害 ・足潰瘍 ・足壊疽 | ・網膜剥離 ・眼底出血 ・失明 | ・全身のむくみ ・血圧の上昇 ・尿毒症 |
3大合併症以外にも、糖尿病は動脈硬化の原因となるため、心臓病や脳卒中のリスクが上がります。
また、歯周囲の血管ももろくなるため歯周病が進行し、歯を失う原因にもなります。
糖尿病の症状チェックリスト

自分の生活習慣や日常生活を振り返り、チェックしてみましょう。
- 昔に比べ太った(20歳代より10㎏以上増えている)
- 尿の量が多い気がする
- すぐに疲れてしまう
- 体がいつもだるい
- いつも喉が乾いている
- 運動不足
- 脂っこい食事をすることが多い
- 3食きちんと取っているのに体重が減る
- ストレスの多い生活をしている
- アルコールをよく飲む
- 家系に糖尿病の人がいる
- 健康診断で血糖値が高いと言われた
以上の項目で当てはまるものが多ければ、糖尿病のリスクがあります。生活習慣を改め、糖尿病の予防をしましょう。
心配な症状がある場合、医療機関を受診しておくと安心です。
血糖コントロールの方法は?

糖尿病では、血糖のコントロールが重要になります。
血糖をコントロールするには、以下の3つの方法があります。
- 食事療法
- 運動療法
- 薬物療法
食事療法

食事療法の基本は、栄養のバランスを取りながら、カロリーを制限することです。
食事療法のポイントを紹介します。
- 適正カロリーを守る
- 栄養バランスのとれた食事をする
- 1日3食規則正しい時間に食べる
- 脂質の適量を摂取する
- 食物繊維を積極的に摂取する
- 塩分を控える
- 間食を控える
- アルコールを控える
偏食をせず、正しい食習慣を意識しましょう。
適正な食事量は、年齢や性別、体格、体を動かす程度などによって人それぞれに異なります。主治医や栄養士と相談し、決めましょう。
運動療法

適切な運動をすることは糖尿病の人だけでなく、健康な生活を送る上で大切です。
運動療法は以下の効果があります。
- 血糖コントロールの改善
- インスリン感受性の増加
- 脂質代謝の改善
- 血圧低下
- 心肺機能の改善
- 肥満の解消
- インスリンの働きを妨害する物質の減少
運動の種類は、ジョギングやウォーキング、水泳などの有酸素運動がいいとされています。
また、腕立て伏せや腹筋、スクワットなどの抵抗負荷に対して動作を行うレジスタンス運動も効果的です。
一般的に中等度の運動強度(運動時心拍数が50歳未満で100-120拍/分、50歳以降で100拍/分以内)を目安に行うことが勧められています。
心拍数が指標にできない場合、自覚的運動強度として、「ややきつい」または「楽である」を目安にするといいでしょう。
運動持続時間は、20分以上の持続が望ましいとされています。
紹介した内容は、日本糖尿病学会のガイドラインで一般的に推奨されている内容です。
しかし、実際に運動療法を取り入れる場合、年齢や糖尿病以外の疾患、内服の状況によって人それぞれ異なります。
主治医に相談してから始めましょう。
薬物療法

食事療法と運動療法を行っても、血糖コントロールが不十分な場合は薬物療法も併用します。
薬物療法は、内服薬とインスリン注射薬があります。異なる内服薬を組み合わせたり注射薬を併用したりと薬物治療の方法は様々です。
病態や血糖コントロールの状況によって、使われる薬剤を決めたり変更したりします。
糖尿病は予防できる?

1型の糖尿病は予防できませんが、2型の糖尿病は予防できます。そのためには、正しい食習慣と適度な運動習慣を身につけましょう。
食事のポイントは以下の5つです。
- 3食しっかり食べる
- よく噛んでゆっくり食べる
- 食物繊維を多くとる
- 腹八分目でやめる
- 寝る前に食べない
運動のポイントは以下の3つです。
- 軽い運動から始め徐々に運動量を増やす
- 体調に合わせ無理をしない
- なるべく毎日できるような運動を選ぶ
食事と運動以外に、ストレスをため過ぎないようにすることも大切です。
ストレスで精神状態が悪くなると、過食や飲酒が増えがちになります。ストレスを上手く発散することも、糖尿病の予防には重要です。
Q&A

糖尿病についてよくある質問を紹介します。
糖尿病の一番の原因は?

1型糖尿病と2型糖尿病では、原因が異なります。
1型糖尿病の原因は以下の通りです。
- 体質
- 何らかの原因で膵臓の一部が破壊されている
2型糖尿病の原因は以下の通りです。
- 肥満
- 糖尿病の人が家族にいる
- 運動不足
- 乱れた食習慣
詳しくは、糖尿病の原因は?の項目を参照してください。
糖尿病の人はトイレ何回?尿の色は?
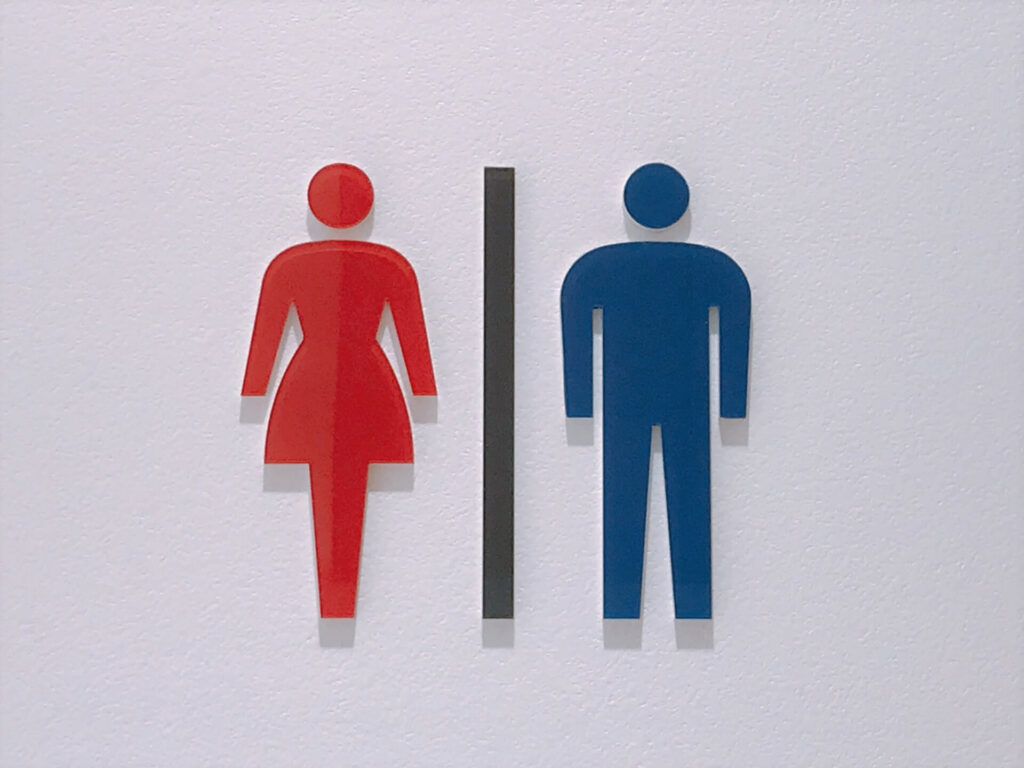
糖尿病の症状で、頻尿があります。血糖値が高いとき、血液はドロドロの状態です。
その時に体の防御反応が働くため、喉の渇きを感じ、水分摂取を促します。水分を多くとると、必然と尿の量が多くなり、トイレの回数が増えます。
1日に8回以上トイレに行く方、夜間1回以上トイレに起きる方は、頻尿であると考えられます。
糖尿病の人は尿量が増えることで尿が薄くなり、尿の色はほぼ透明になります。
また、糖尿病で糖やタンパク質が出る人の尿は、粘度が高く、泡立ちやすい傾向です。
糖尿病腎症のステージごとの症状は?
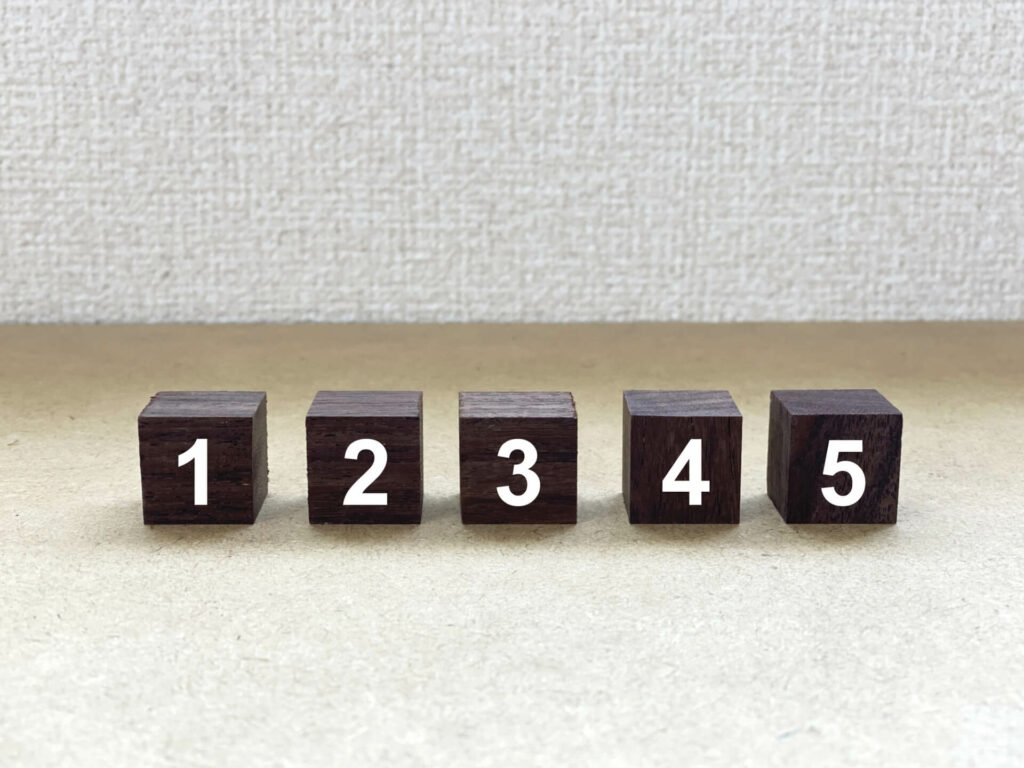
糖尿病腎症は5つのステージに分類されています。
症状や治療法は、以下の表の通りです。
| ステージ1 | ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | ステージ5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 腎症前期 | 早期腎症期 | 顕性腎症期 | 腎不全期 | 透析療法期 | |
| 基準値 | ・尿タンパク(g/gCr):正常(30未満) ・eGFR(ml/分/1.73㎡):30以上 | ・尿タンパク(g/gCr):微量アルブミン尿(30~299) ・eGFR(ml/分/1.73㎡):30以上 | ・尿タンパク(g/gCr):顕性アルブミン尿(300以上) ・eGFR(ml/分/1.73㎡):30以上 | ・尿タンパク(g/gCr):問わない ・eGFR(ml/分/1.73㎡):30未満 | ・透析療法中 |
| 症状 | 自覚症状なし | 自覚症状はほとんどないが微量のタンパク質が出る | ・むくみ ・息切れ ・胸の苦しさ ・食欲不振 | ・顔色が悪い ・嘔気 ・嘔吐 ・筋肉の硬直 ・つりやすい ・手足のしびれや痛み | ・ステージ4と同様の症状 |
| 治療法 | 食事療法を基本とした血糖コントロール | 食事療法を基本とした血糖コントロールと血圧コントロール | 食事療法と運動療法で血糖値と血圧をコントロール | 血圧のコントロールをし低タンパク食。透析療法の検討 | 透析療法や腎移植の検討 |
(参考:全腎協)
糖尿病は治る?

糖尿病の完治はできません。
しかし、2型の糖尿病に関しては正しい食事療法や運動療法、薬物療法で糖尿病の状態を改善できます。
血糖値の上手なコントロールは、糖尿病の進行を抑え、合併症の発症リスクを下げます。
糖尿病でも、健康な人と変わらない生活を送ることが可能です。
糖尿病の初期症状は?前触れはある?

糖尿病の初期症状は以下の通りです。
- のどの渇き
- 多飲
- 多尿
- 体のだるさ
- 体重減少
初期の段階では目立った症状がなく、糖尿病になっていることに気づかないケースもあります。
糖尿病を早期に発見するためには検診を受け、定期的にチェックすることが重要です。
糖尿病の自覚症状で手遅れなものは?

糖尿病で、以下の自覚症状がある場合、合併症を発症している可能性があります。
- むくみ
- 手足のしびれ
- 視力の低下
- 動悸
- 息切れ
- めまい
上記の症状は一部ですが、気になる症状がある場合、早めに受診しましょう。
放置していても良くなりません。
早めに治療をスタートさせられると、手遅れにならず進行を遅らせ、合併症を予防できます。
糖尿病の初期症状は治る?

糖尿病は一度発症すると治ることはありません。
しかし、初期段階で治療に取り組み、生活習慣を改善できれば、健康な人と変わらない生活を送ることができます。
糖尿病の初期症状で爪の症状は?

高血糖が続くと血管が細くなります。さらに末端の血流が悪くなり、栄養が行き届かなくなります。
糖尿病で起こる爪の変化は、足の爪が白く濁ったり白い線ができたりといった症状です。
また、以下のような爪の状態になる場合は注意が必要です。
- 巻き爪、陥入爪
- 爪白癬
- 爪肥厚
ひどい場合は治療が必要となります。
糖尿病の人は、爪の観察やケアをして、爪の切り方にも注意したほうがいいでしょう。
コーヒーは血糖値を下げる?

コーヒーは糖尿病の発症予防に効果があるとされています。
コーヒーに含まれる、カフェインやクロロゲン酸、マグネシウムの作用が糖尿病予防に効果が期待できるという報告があります。
(参考:厚生労働科学研究成果データベース『コーヒーと糖尿病の疫学』)
ミルクや砂糖が入ったコーヒーは、血糖値を上昇させるのでブラックコーヒーにしましょう。
しかし、すでに糖尿病を発症している人には、逆に血糖値を上昇させる可能性があります。
コーヒーを飲めば「血糖値が下がる」「糖尿病にならない」のではありません。あくまで、「糖尿病の予防に軽い効果がある」程度だと考えていた方がいいでしょう。
まとめ
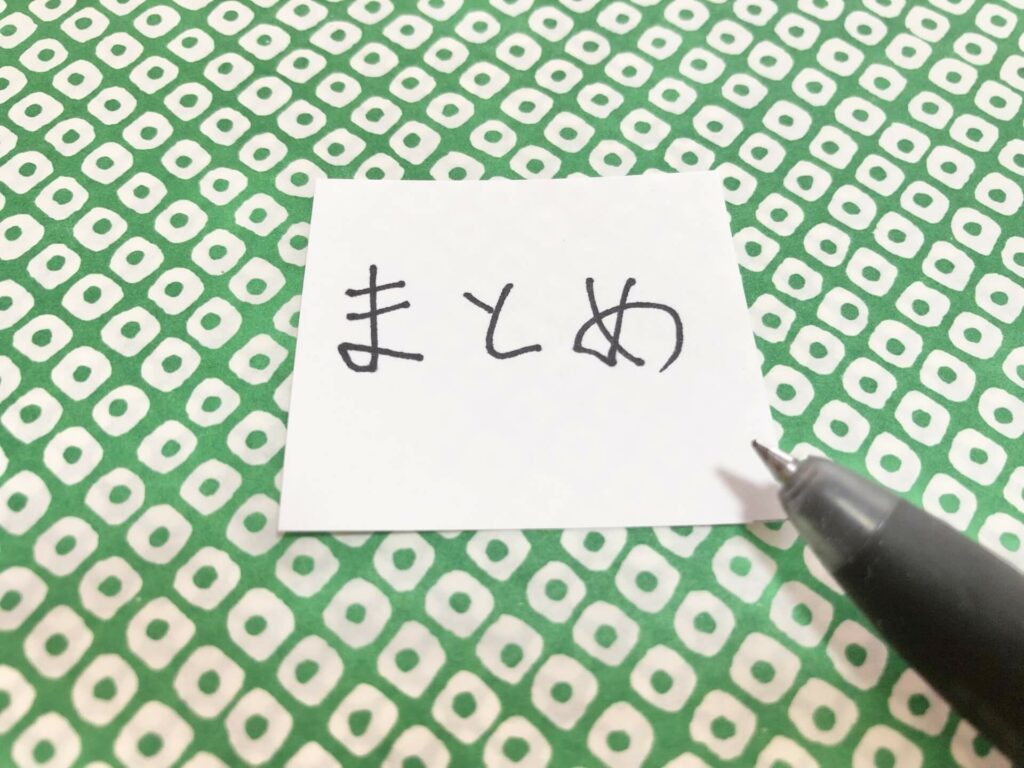
糖尿病で使われる薬を中心に、糖尿病についてお伝えしました。
多くの糖尿病薬の副作用で注意すべきは、「低血糖」です。
しかし、低血糖について理解し適切な対応をすれば、たとえ低血糖になったとしても危険な状態を回避できる可能性があります。
糖尿病は完治が難しい病気ですが、薬の効果や副作用を理解して、血糖値をうまくコントロールしましょう。
糖尿病の進行を遅らせることができ、合併症のリスクを下げることにも繋がります。
まずは、自分の使っている薬の副作用や特徴を理解できるよう、分からないことは主治医に相談してみましょう。