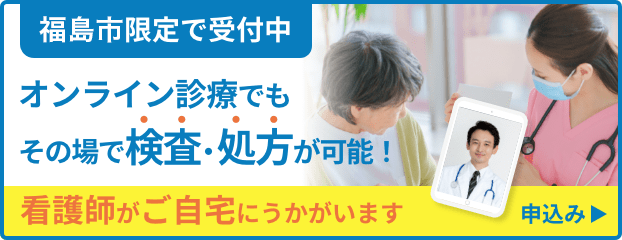GLP-1受容体作動薬とは?特徴や気になる副作用を解説!
GLP-1(glucagon-like peputide-1)受容体作動薬って何だろう?
「GLP-1ダイエット」という言葉が広がり、GLP-1受容体作動薬について耳にすることが増えたのではないでしょうか。
GLP-1受容体作動薬は、日本で2型糖尿病に用いられる薬です。
「GLP-1ダイエット」といわれる言葉があるように、血糖値を下げるだけではなく、体重減少効果が期待できます。
しかしGLP-1受容体作動薬は医薬品であり副作用があるため、正しく用いることが必要です。
本記事では、GLP-1受容体作動薬が体の中でどのように作用するのか、注意すべき副作用などとあわせて解説します。
GLP-1ダイエットについても触れますので、参考にしてみてください。

名倉 義人 医師
○経歴
・平成21年
名古屋市立大学医学部卒業後、研修先の春日井市民病院で救急医療に従事
・平成23年
東京女子医科大学病院 救急救命センターにて4年間勤務し専門医を取得
・平成27年
東戸塚記念病院で整形外科として勤務
・令和元年
新宿ホームクリニック開院
○資格
救急科専門医
○所属
日本救急医学会
日本整形外科学会
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
GLP-1とは?

GLP-1は、食べ物を食べたときに小腸などの消化管から分泌されるホルモンの一つです。
体内の血糖値が高いときに、GLP-1が膵臓に働きかけてインスリンの分泌を促します。
インスリンは、体内の血糖を下げる働きを持つ物質です。
このような働きから、GLP-1受容体作動薬は2型糖尿病に用いられます。
GLP-1受容体作動薬とは?

GLP-1はDPP-4(di-peptidyl peptidase-4)という酵素によって、体内で速やかに分解されます。
GLP-1受容体作動薬は、上記のGLP-1の機能を保ちながら、体内で分解されにくいように改良された薬です。
GLP-1受容体作動薬とDPP-4阻害薬の違いは?

GLP-1受容体作動薬に関連して、DPP-4阻害薬という薬があります。
こちらも2型糖尿病に用いられる薬です。
DPP-4阻害薬は、DPP-4の働きを抑え、体内のGLP-1濃度を高めます。
その結果、インスリンの分泌を促し血糖を下げることができる薬です。
DPP-4阻害薬は、GLP-1受容体作動薬よりも血糖を下げる効果が弱いですが、その分副作用が少ないと知られています。
なお、DPP-4阻害薬とGLP-1受容体作動薬は、基本的に一緒に使うことはありません。
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
GLP-1受容体作動薬は、体の中でどうやって働くの?

GLP-1受容体作動薬の作用機序について、さらに詳しく説明します。
主な作用は以下の3点です。
- 膵臓でインスリンの分泌を促す
- 胃の働きを抑える
- 中枢神経に作用して食欲を抑える
膵臓でインスリンの分泌を促す

1点目は、膵臓のB細胞に作用してインスリンの分泌を促し、血糖を下げる働きです。
さらにインスリンの分泌により、血糖を上げる作用のある「グルカゴン」が抑えられるので、血糖の上昇も抑えます。
またGLP-1は、体内の血糖が高いときだけインスリンの分泌を促すため、低血糖になりづらいといわれています。
胃の働きを抑える
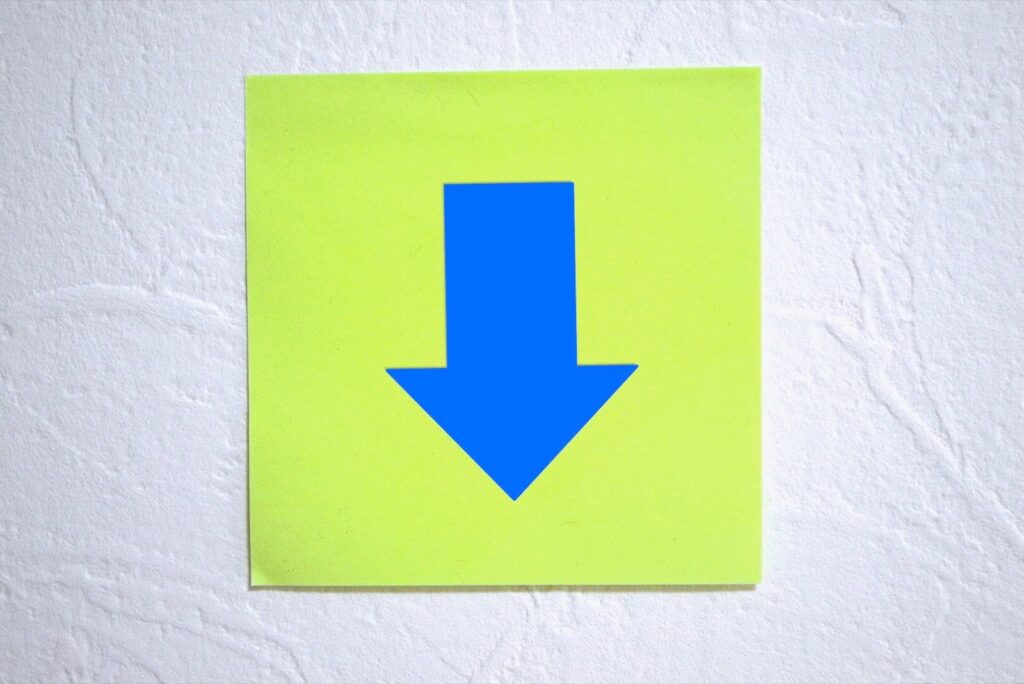
2点目は、胃の働きを抑える作用です。
これによって、食べ物を腸に送り出すのが遅くなり、食後の血糖値が急に高くなるのを防ぎます。
さらに食事中の満腹感が得られるため、食事量の減少も期待できます。
中枢神経に作用して食欲を抑える

3点目は、脳の摂食中枢に作用して食欲を抑える働きです。
空腹を感じにくくなり、間食や1回あたりの食事量が減るため、体重の減少が期待できます。
GLP-1受容体作動薬の一覧と使い分け

現在、日本で承認されているGLP-1受容体作動薬は、飲み薬1種類と注射薬6種類です。
| 商品名 | 一般名 | 用法 | |
| 飲み薬 | リベルサス | セマグルチド | 1日1回起床時 |
| 注射薬 | オゼンピック | セマグルチド | 週1回 |
| トルリシティ | デュラグルチド | 週1回 | |
| ビクトーザ | リラグルチド | 1日1回 | |
| リキスミア | リキシセナチド | 1日1回朝食前 | |
| バイエッタ | エキセナチド | 1日2回食前 | |
| マンジャロ | チルゼパチド | 週1回 |
(参考文献:各薬剤の添付文書)
GLP-1受容体作動薬の飲み薬:リベルサス(一般名:セマグルチド)

GLP-1受容体作動薬の飲み薬、リベルサスについて解説します。
リベルサスは、GLP-1受容体作動薬における世界初の飲み薬です。
リベルサスを服用する際は、以下の3点に注意する必要があります。
- 服用前に、食事や飲水をしない→1日1回起きてすぐ服用する
- 120ml以下の少量の水で服用する
- 服用後は最低30分間は飲食しない
服用時は、お茶やジュースではなく水で服用しましょう。
服用方法を守らないと、薬が体に吸収されず期待している効果が現れなくなります。
GLP-1受容体作動薬の注射薬

注射薬はすべて皮下注射であり、自分で注射する薬です。
使用する薬によって投与頻度や用量、注射器の形などが異なるので、患者さんに合った薬が選択されます。
注射というと、インスリン注射を連想するかもしれませんが、全く異なります。
インスリン注射は、体の中の足りないインスリンを補うために必要な注射です。
インスリンを出せない1型糖尿病や、膵臓が疲れてインスリンを充分に出せなくなった2型糖尿病に用いられます。
インスリン注射では、1日あたり3〜5回注射をするのが一般的です。
一方、GLP-1受容体作動薬の注射は、膵臓からインスリンを出すように促すための注射です。
GLP-1受容体作動薬では、週に1回注射する製剤がよく用いられます。
オゼンピック(一般名:セマグルチド)
オゼンピックは、週に1回注射します。
自分で注射しやすいペン型の注射器で、1回使い切りタイプと複数回使えるタイプの2タイプあります。
1回使い切りのタイプは、注射器に針があらかじめ装着されており、注射器を皮膚に押し付けるだけで注射できるので簡単です。
複数回使えるタイプは自分で針を装着しますが、針が細く痛みが少ないという特徴があります。
オゼンピックの成分は、飲み薬のリベルサスと同じ成分です。
トルリシティ(一般名:デュラグルチド)
トルリシティは、週に1回注射します。
注射器を皮膚に当て、ボタンを1回押すだけで注射できる「アテオス」という注射器を用います。
自ら針を抜き差ししなくてよいので、簡単に使えるのが特徴です。
トルリシティはGLP-1受容体作動薬の中で、体重減少が比較的ゆるやかといわれています。
ビクトーザ(一般名:リラグルチド)
ビクトーザは、1日1回注射します。
注射する単位を毎回設定して使う、ペン型の注射器です。
日本で初めて、GLP-1受容体作動薬として承認された薬です。
リキスミア(一般名:リキシセナチド)
リキスミアは、1日1回朝食前1時間以内に注射します。
注射する単位を毎回設定して使う、ペン型の注射器です。
同じく1日1回注射するビクトーザと比較して、朝食後の血糖値を抑えることができます。
バイエッタ(一般名:エキセナチド)
バイエッタは、1日2回朝夕食前に注射します。
注射する単位を毎回設定して使う、ペン型の注射器です。
食後の血糖値を抑える効果が期待できます。
マンジャロ(一般名:チルゼパチド)
マンジャロは、2023年4月に新発売された、世界初のGLP-1/GIP受容体作動薬です。
GLP-1受容体作動薬と異なる点があるため、簡単に説明します。
GLP-1と同様に、インスリンの分泌を促すGIPというホルモンがあります。
マンジャロはGLP-1とGIPの2種類のホルモンにより、血糖を下げる薬です。
オゼンピックやトルリシティと比較して、血糖を下げる効果が高いと分かっています。
マンジャロは、週に1回注射します。
注射器は、トルリシティと同じ「アテオス」を採用しているので、注射するのが簡単です。
GLP-1受容体作動薬で気を付けたい副作用は何?

GLP-1受容体作動薬の副作用について解説します。
主な副作用は以下の2つです。
- 消化器症状
- 低血糖症状
消化器症状(吐き気や便秘・下痢)

GLP-1受容体作動薬の副作用には、吐き気や便秘、下痢などの消化器症状があります。
先述したように、GLP-1受容体作動薬には胃の働きを抑える作用があるためです。
薬の使い始めに生じることが多く、徐々に落ち着くといわれていますが、症状がつらい場合は医師に相談しましょう。
消化器症状の中には、腸閉塞や急性膵炎といった重大な副作用が隠れていることがあり、注意が必要です。
腸閉塞とは、腸がふさがり食べ物や水分などの内容物が溜まった状態です。
症状としては、持続する腹痛や便秘、おなかの張り、発熱があげられます。
また、急性膵炎は膵臓に炎症が生じた状態です。
嘔吐を伴う激しい腹痛が現れた場合、急性膵炎が疑われます。
腸閉塞や急性膵炎の場合は、薬が中止になる場合もあるため、これらの症状が現れたらただちに医師に相談してください。
低血糖症状

GLP-1受容体作動薬は、他の糖尿病治療薬と比べて低血糖になりづらいですが、低血糖症状には注意が必要です。
低血糖の初期症状として、以下の症状があります。
- 異常な空腹感
- 冷や汗
- 手の震え
- 吐き気
- 体のだるさ
このような症状を感じたら、すぐに飴やジュースなど甘いものを摂って安静にしてください。
また、普段から飴やブドウ糖などを持ち歩くようにしましょう。
GLP-1ダイエットに関するQ&A

GLP-1ダイエットについてQ&A形式で解説します。
GLP-1受容体作動薬はなぜ痩せるの?

胃の働きや食欲を抑える作用があり、食事量が減少するためです。
その結果、体重減少効果が期待できます。
GLP-1ダイエットは保険適用されている?

現在日本で使われているGLP-1受容体作動薬は、全て2型糖尿病に対する適応のため、ダイエットに対して保険適用されていません。
GLP-1ダイエットで使われる薬は、全て自費診療となります。
しかし、2023年3月27日にGLP-1受容体作動薬の「ウゴービ」が肥満症治療薬として承認されました。
発売開始日は未定ですが、以下に該当する患者が適応となります。
【ウゴービの適応】
肥満症
ただし、高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、以下に該当する場合に限る。
- BMIが27kg/m2以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する
- BMIが35kg/m2以上
単なるダイエット目的では使えないので、注意してください。
GLP-1ダイエットの危険性は?

GLP-1ダイエットにGLP-1受容体作動薬が使われることについて、国や糖尿病学会から警告が出ています。
【PMDAからのお知らせ】
GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬については、2型糖尿病のみを効能・効果として製造販売承認を取得しているものであり、それ以外の目的で使用された場合の安全性及び有効性については確認されておりません。
(参考:GLP-1 受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用に関するお知らせ(2023年6月1日))
先述したように、GLP-1受容体作動薬の使用により、吐き気や便秘、下痢、低血糖などの副作用が現れることがあります。
重篤な場合は入院も要する副作用です。
もしダイエットのためにGLP-1受容体作動薬を使用して副作用が現れても、自己責任となります。
つまり国の補償制度である、医薬品副作用被害救済制度を使うことはできません。
さらに、ダイエット目的で薬を使う人が増えると、本当に薬を必要とする2型糖尿病患者に薬が届かない事態にもなりえます。
さまざまな危険性が潜んでいるので、GLP-1ダイエットに取り組む際は、よく考えて選択しましょう。
Q&A

GLP-1受容体作動薬の気になる質問について答えます。
GLP-1受容体作動薬は何の薬?

GLP-1受容体作動薬は2型糖尿病の薬です。
体内の血糖が高いときに膵臓からのインスリン分泌を促し、血糖を下げる働きがあります。
胃の働きや食欲を抑え、食事量が減ることで、体重減少の効果も期待できます。
GLP-1受容体作動薬の用法は?

GLP-1受容体作動薬の用法は、薬剤によって異なります。
| 商品名 | 一般名 | 用法 | |
| 飲み薬 | リベルサス | セマグルチド | 1日1回起床時 |
| 注射薬 | オゼンピック | セマグルチド | 週1回 |
| トルリシティ | デュラグルチド | 週1回 | |
| ビクトーザ | リラグルチド | 1日1回 | |
| リキスミア | リキシセナチド | 1日1回朝食前 | |
| バイエッタ | エキセナチド | 1日2回食前 | |
| マンジャロ | チルゼパチド | 週1回 |
(参考文献:各薬剤の添付文書)
まとめ
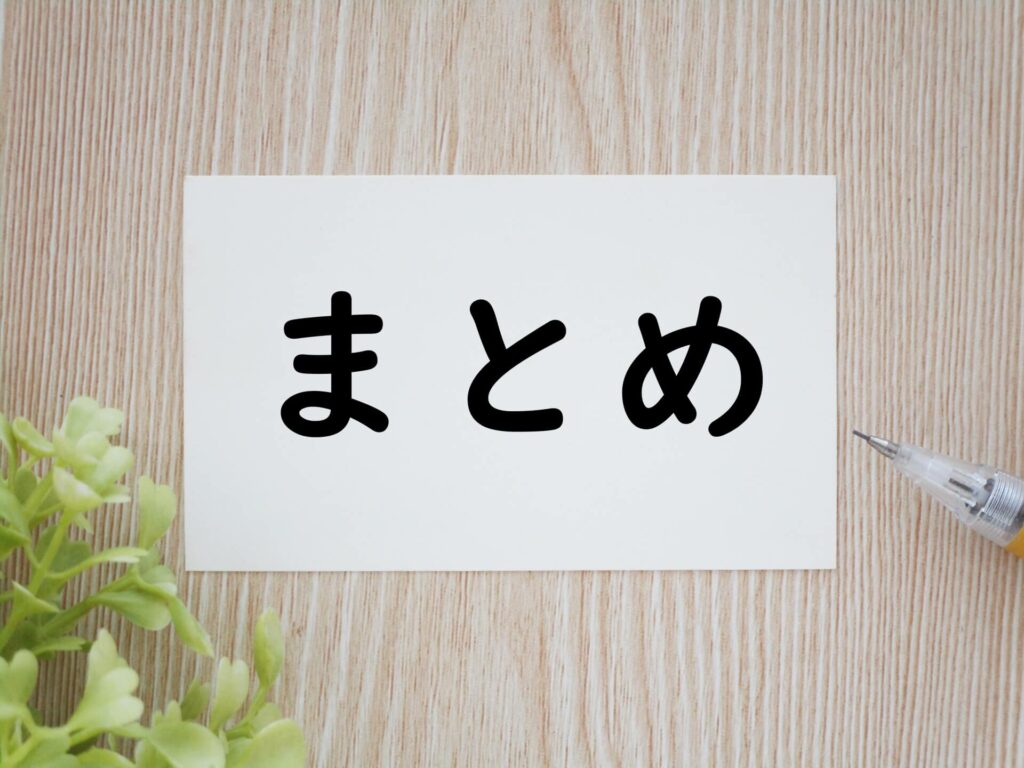
本記事では、GLP-1受容体作動薬の働きや副作用について解説しました。
GLP-1受容体作動薬の働きをまとめると、以下の通りです。
- 膵臓でインスリンの分泌を促す
- 胃の働きを抑えることで食後高血糖を抑える
- 食欲を抑えることで食事量を減らす
薬の使い始めは、吐き気や便秘、下痢の副作用が現れることがあります。
また、空腹感や手の震え、冷や汗といった低血糖症状にも気を付けましょう。
GLP-1受容体作動薬は、GLP-1ダイエットの影響で危険なイメージもあるかもしれません。
しかし医師の指導のもと正しく使えば、2型糖尿病にとって効果的な治療薬です。
治療で不安なことがあれば、医師や薬剤師に相談してみましょう。