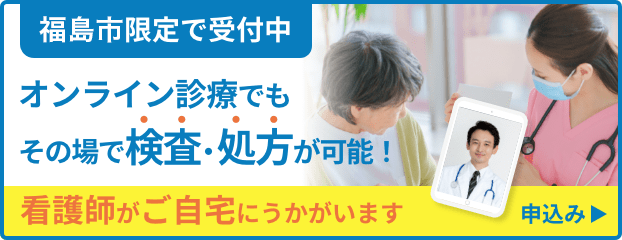糖尿病における食事療法の目的と実際の方法を解説|カロリー計算とレシピも紹介
糖尿病は生活習慣病といわれています。
日々の暮らしの中で、食事内容や運動不足が重なり、糖尿病になると考えられています。
そのため食事療法は、糖尿病治療の中でもとても重要です。
この記事では、糖尿病における食事療法の目的と実際の方法を解説していきます。
ぜひ、最後までお読みください。

名倉 義人 医師
○経歴
・平成21年
名古屋市立大学医学部卒業後、研修先の春日井市民病院で救急医療に従事
・平成23年
東京女子医科大学病院 救急救命センターにて4年間勤務し専門医を取得
・平成27年
東戸塚記念病院で整形外科として勤務
・令和元年
新宿ホームクリニック開院
○資格
救急科専門医
○所属
日本救急医学会
日本整形外科学会
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
糖尿病における食事療法の目的とは?
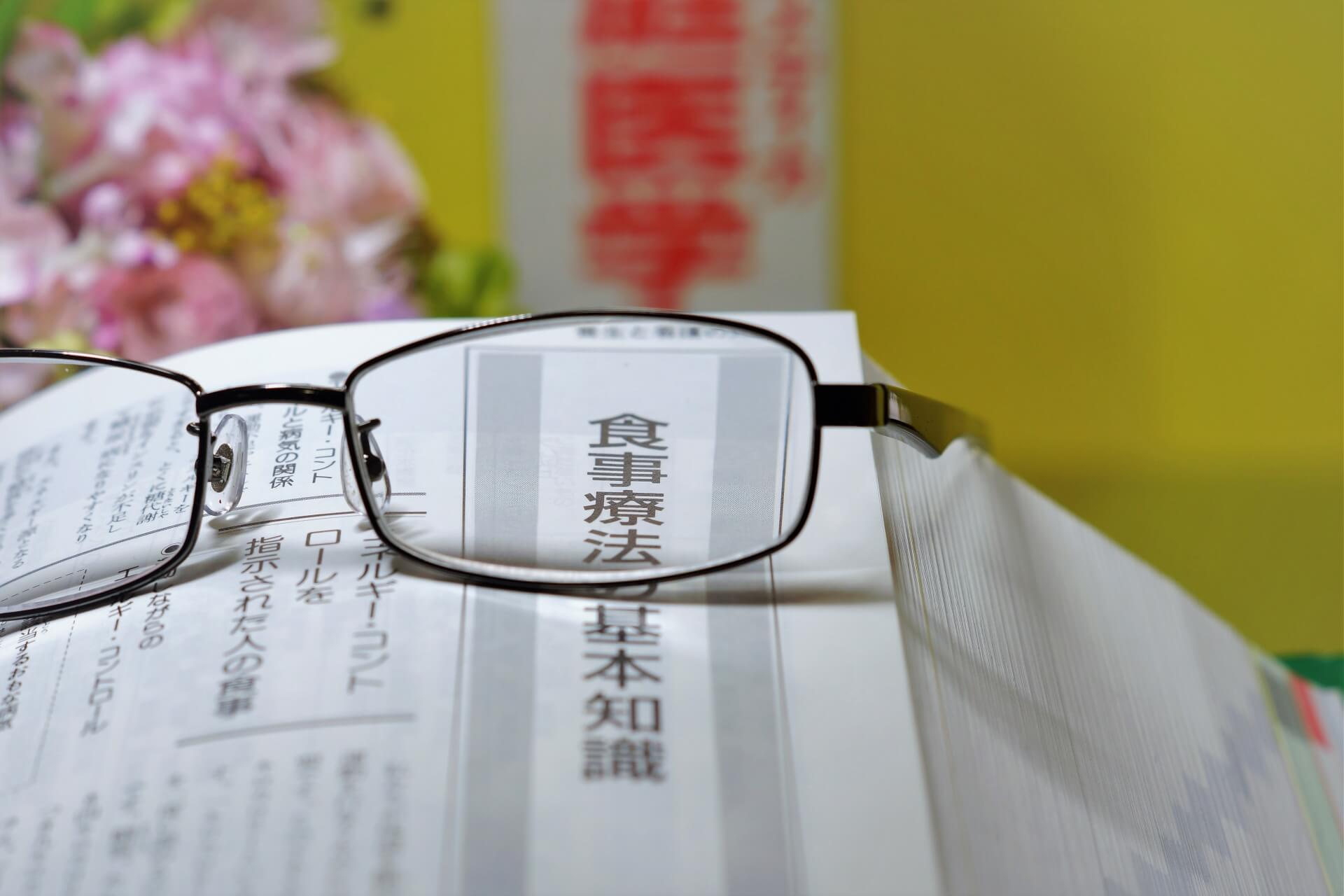
糖尿病の食事療法は、血糖値をコントロールし安定させる効果があります。
高血糖が続くと血管や神経に障害をきたし、重大な合併症につながる可能性が高くなります。
糖尿病治療の第一選択肢でもある食事療法で、糖尿病の進行を防ぎましょう。
糖尿病ガイドラインから見る食事療法の重要性

糖尿病診療ガイドラインは、エビデンスに基づき3年ごとに改訂されています。
ガイドラインには、糖尿病治療に重要な役割である、食事療法について書かれています。重要なポイントを紹介しますのでご参照ください。 [1]
- 糖尿病の管理には、食事療法を中心とする生活習慣の改善することが有効
食事と運動を中心に積極的に生活習慣の改善を促した場合には、体重の減少とともにHbA1cの低下と血圧や中性脂肪の低下し、心血管疾患のリスク低下が認められている。
- 食事療法の実践において、管理栄養士による指導が有効である
食事療法は早期から行うことで、血糖値の改善をもたらすとされている。
管理栄養士による指導は、医師や他の医療スタッフが行うよりもHbA1cの改善や体重減少に有効だと認められている。
- 総エネルギーを設定する際に、患者の年齢を考慮した体重を目標としてエネルギー量を決めていくが、その都度代謝状態を考慮して変更する
- 栄養素摂取比率は、身体活動量や合併症の状態、年齢、嗜好に考慮し柔軟に対処する
糖質・タンパク質・脂質のバランスは個々の病態に合わせる 。
成人の基準として糖質は50〜60%、タンパク質は13〜20%、脂質は20〜30%としている。
また、食物繊維は20g/日摂取を推奨している。
- 炭水化物の摂取量は糖尿病管理にどう影響する?
炭水化物量と糖尿病発症リスク、糖尿病の管理状態との関連性は確認されていない。
ショ糖を含んだ甘味やジュースは、血糖コントロールの悪化やメタボリックシンドロームを招く可能性があり、控えるべきである 。
インスリン療養中の患者に、カーボカウントを指導することは血糖コントロールに有効である 。
GIに基づいた食品選択の糖尿病管理における有用性は、確認されていない 。
低GI食品は、糖尿病発症リスクは低くなるとしているが、糖尿病患者の食事療法に積極的に取り入れるかは現時点では十分な根拠があるとはいえないとしている 。
- 20%を超えるタンパク質摂取については、動脈硬化性疾患を増加きたす可能性があり長期的な安全性は確認されていない
- 総脂質量と糖尿病発症リスクとの関係は明らかではないが、動物性脂質(不飽和脂肪酸)の摂取は糖尿病発症のリスクとなる
- 食物繊維は糖尿病状態の改善に有効であり、炭水化物量とは無関係に20g/日以上の摂取を促す
- 規則的に3食摂取することが糖尿病の予防に有効である
糖尿病の食事療法|実際の方法を詳しく解説
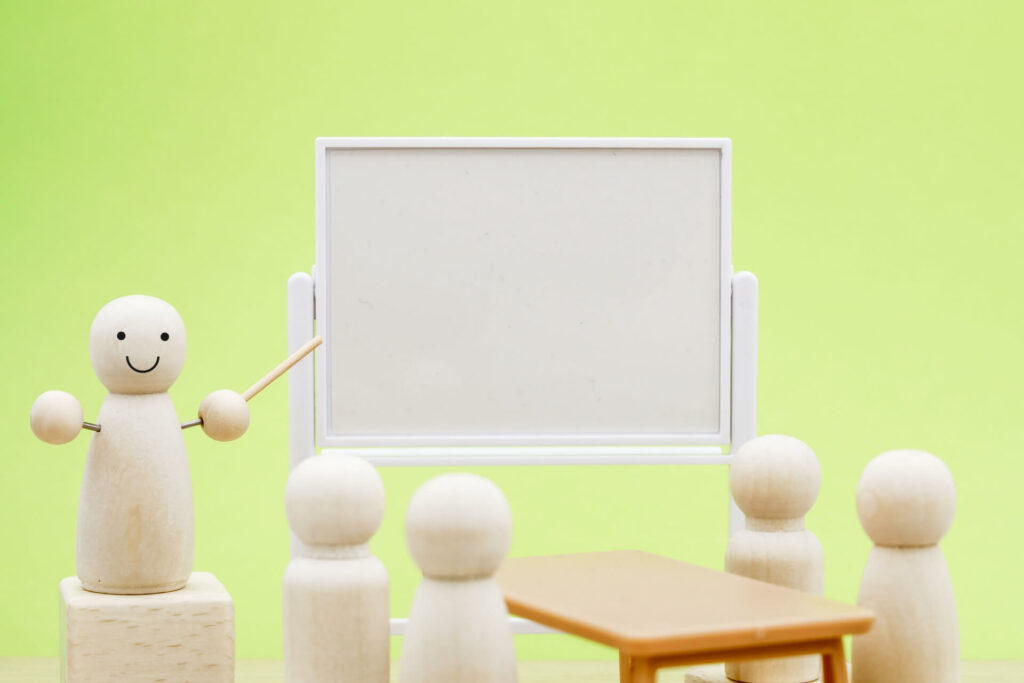
糖尿病の食事療法とは、カロリー制限や食べれない食事があると思われがちですが、そんなことはありません。
調理方法を少し工夫することや、日々の心がけで血糖値に変化が表れます。
ここからは実際の食事療法を詳しく解説していきます。
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
糖尿病の食事療法のコツは?

糖尿病の食事療法を継続していくためには、少しの心がけが大切になります。
糖尿病の食事療法には、5つのコツがあります。
- ゆっくり、よく噛んで食べる
- 朝・昼・夕3食規則正しく食べる
- バランスよく食べる
- 食事は腹八分目でストップする
- 夜遅く、寝る前には食べない
長く続けるコツは、気負い過ぎないことです。
毎日絶対に守らなくてはならないと、いうわけではなくたまにはご褒美で好きなものを食べる日があってもいいとされています。 [2]
食事を摂る際の食べる順番に気をつけて
食事の食べる順番で、血糖値に変化があります。
ベジファーストという言葉を聞いたことありますか?
ベジファーストは、野菜をはじめに食べるという意味です。食物繊維が豊富な野菜から食べ始めると、血糖値は緩やかに上昇することがわかっています。
また、主食や主菜から食べるより、汁物を先に食べることがおすすめです。
汁物は空腹をやわらげ、糖質や脂質が多めの主食や主菜を一気に食べるのを防止します。
野菜をたっぷり入れた味噌汁なら、食物繊維もとれて一石二鳥です。
食事は食べ方を工夫するだけで血糖値に変化がある
食事の回数は1日に3回規則正しく食べると良いでしょう。
1食抜いてしまうと、次の食事をとった後に血糖値が上がりやすくなります。
毎日同じ時間に3食とるように心がけましょう。
食事はよく噛んで食べると、少ない量でも満腹感を得られ、血糖の急上昇を防ぐことができます。
血糖値を緩やかに上昇させる食品を知っておく
血糖値を緩やかに上げる食品を知っておくと、血糖値をコントロールしていくのに役立ちます。
血糖値が穏やかに上昇することで、インスリンの過剰な分泌が抑制され、脂肪が蓄えられるのを防げます。
GI値(グリセミックインデックス)は血糖値の上がり方を示す指標になり、このGI値が低いほど血糖値を緩やかに上昇させる食品です。
いくつか事例を紹介します。
| GI値が低い食品 | GI値が高めの食事 | ||
|---|---|---|---|
| ライ麦パン | 58 | 食パン | 95 |
| 玄米 | 56 | 精白糖 | 84 |
| さつまいも | 54 | じゃがいも | 90 |
| プリン | 50 | ショートケーキ | 82 |
GI値の低い食品ばかりを選んで食べればいいわけではなく、置き換えて食品を選ぶ時の目安にしてみるのがいいでしょう。 [3]
一日の摂取カロリーの計算方法

年齢や体格と活動量から1日の摂取カロリーを計算し、適正なエネルギー量を割り出します。
1日の適切なエネルギー量(kcal)=目標体重(kg)×エネルギー係数
目標体重は、年代により計算式が異なります。
- 65歳以下:身長(m)×身長(m)×22
- 65歳以上:身長(m)×身長(m)×22~25
エネルギー係数
- 軽い労作(大部分が座位の静的活動):25~30(kcal/kg目標体重)
- 普通の労作(通勤
・家事
・軽い運動を含む):30~35(kcal/kg目標体重) - 重い労作(力仕事
・活発な運動習慣):35~(kcal/kg目標体重)
例)身長160㎝で座って仕事をすることが多い人の場合
目標体重=1.6(m)×1.6(m)×22=56.3(kg)
エネルギー係数=軽い労作となるため、エネルギー係数は25〜30のため、1日の食事で摂取した方がよい適切なエネルギー数は下記の式から割り出せます。
56.3㎏×25~30(kcal/kg目標体重)≒1,400~1,700kcal
となります。[2]
バランスの良い食事の割合と調理のポイント

バランスの良い食事とはどのようなものでしょうか? 具体的な例を紹介します。
栄養素別に分類して、配分は以下の通りです。
| 栄養素 | 摂取エネルギーの配分 |
|---|---|
| 炭水化物(主食:ごはん、パン、麺類など) | 40~60% |
| タンパク質(良質なタンパク質を含む肉や魚、大豆製品) | 20%まで |
| 脂質(オイルやバターなど) | 20~30% |
調理のポイントを4つ紹介します。
- 食物繊維をたくさんとることを意識しましょう
食物繊維を多く含む根菜類は、急激な血糖値の上昇を抑えます。 また、低カロリーで満腹感を得ることができるのも特徴です。
- 肉類の脂肪分をできるだけ取り除くようにしましょう
鶏肉の皮や豚肉の白い脂身は脂質が多いので、取り除くか調理方法を煮る
・網で焼く
・蒸すことによって余分な脂肪分は落ちます。
- 料理に使う油は植物性を選びましょう
調理に使う油は不飽和脂肪酸(植物や魚に多く含まれるもの)を選び、オリーブオイルやサラダ油を使うことで動脈硬化予防になります。
- 減塩しましょう
近年では減塩志向の方のために、味噌や醤油も減塩商品が多く販売されています。 酢やだしで味をつけると塩分少なめに調理できるでしょう。
食べたほうがいい食品とは?

積極的に食べるといい食品があります。
血糖値の急激な上昇を避け、動脈硬化の予防になるおすすめの食品を紹介します。
- 青魚
サバやイワシなどに含まれるDHA、EPAは動脈硬化の予防に効果があります。
缶詰のサバやイワシで手軽に食べることができますが、味噌煮や醤油で味付けしたものは、塩分が多いので水煮缶をおすすめします。
- 玄米やもち麦
白米に比べ食物繊維が豊富で血糖値の急激な上昇を妨げます。
- きのこ類
低カロリーで食物繊維が豊富です。
- 葉野菜
キャベツやレタスなどの葉野菜も食物繊維が豊富で血糖値の上昇には効果的です。
糖尿病の食事療法|実際のメニューとレシピを紹介

1日のメニュー例を紹介していきます。
1,600kcal/日の場合
- 朝食 ロールパン2個 目玉焼き1つ サラダ(ノンオイルドレッシング) リンゴ1/4個 牛乳200ml
- 昼食 サバの焼うどん(※レシピあり)キウイフルーツ3/4個 調整豆乳200ml
- 夕食 玄米ご飯150g キノコスープ タンドリーチキン ほうれん草の胡麻和え
サバの焼うどんレシピ 材料(1人前)
- うどん200g
- サバ水煮缶65g
- キャベツ2枚
- にんじん1/5本
- ピーマン1個
- しょうが2/3かけ
- ごま油 大さじ1/2
- A鯖缶の汁
- 大さじ2
- A酒 大さじ1
- Aめんつゆ(3倍濃縮) 大さじ1/2
- Aこしょう 少々
作り方
- フライパンにごま油とショウガを炒め、野菜をくわえてさらに炒める。
- 野菜に火が通ったら、水気を切った鯖缶とうどんをくわえて炒める。
- Aを合わせたものをくわえて少し炒めたら出来上がり。[2]
食事療法中の気になる外食や間食とお酒の注意点とは

1人暮らしや時間が不規則な仕事の人には、外食やコンビニの食事が手軽で利用される方も多いのではないでしょうか?
基本的に、外食は塩分や脂質が多く、食事療法中には適していません。しかし、種類や食品の選び方で血糖値をコントロールしていくことは可能です。
お酒に関しても仕事や友人の付き合いがある方は、どうすればいいか考えてしまいますよね。
ここからは外食時や間食、お酒について解説していきます。
外食時の注意点は何?

仕事上や友人との付き合いで外食をすることがありますよね。
そんな時はメニューの選び方に注意しましょう。知っておきたい注意点を紹介します。
- 単品より定食を選ぶ
野菜や汁物、肉や魚のタンパク質がそろっていてバランスのいい食事をとるのに定食は適しています。
丼物やうどんやラーメンの単品を選ぶ場合は、サラダをつけるなど工夫しましょう。
- 魚料理を選ぶ
魚は肉に比べて不飽和脂肪酸が多く、動脈硬化予防に効果があります。
家庭料理より外食の方が油分を多く含んでいる傾向にありますので、焼き魚や煮魚などを選ぶといいでしょう。
- 中華料理や洋食よりも和食を選ぶ
中華料理や洋食に比べて和食は、脂質が少ないメニューが豊富です。 コンビニでの食事も手軽で忙しい時には、利用される方も多いでしょう。
- 炭水化物は1つまで
おにぎりと麺類を選ぶより、1品はサラダや魚の塩焼きなどを選ぶといいでしょう。
- お弁当は、品数の多いものを選びましょう
幕の内弁当は品数も多く、野菜もとることができるのでおすすめです。
コンビニのご飯はカロリーや、栄養成分なども表示しているので成分を見ながら購入できますが、糖質や脂質の多い食品を選びがちなので注意しましょう。
糖尿病の食事療法中にお酒やお菓子は禁止?

食事療法中のお酒や間食は、絶対に禁止というわけではありません。 しかし、お酒や間食をとるには、ある程度ルールを決めることが大切です。
ここからは、お酒と間食をとるときのポイントを解説します。
- お酒を飲む場合
お酒は少量であればストレス解消の働きもありますが、たくさん飲むと自制心がきかなくなり、暴飲暴食につながることがあります。
糖尿病の薬物治療中の人は、お酒を飲むことで血糖値が下がるため低血糖になる可能性があります。 お酒を飲む場合は、必ず主治医に相談をしましょう。
- 間食について
1日の適正な摂取カロリー内で食べるようにして、時間は午後3時頃に食べましょう。
食べる食品は、カロリーの高いスナック菓子やケーキは避け、ナッツ類や果物を選ぶと血糖値の上昇を防げます。
糖尿病の食事療法に活用する食事交換表

食事交換表は、糖尿病の食事療法を簡単に行えるように作られた表です。
ここから、実際の使い方を解説します。
食事交換表のグループ分けの見方は?
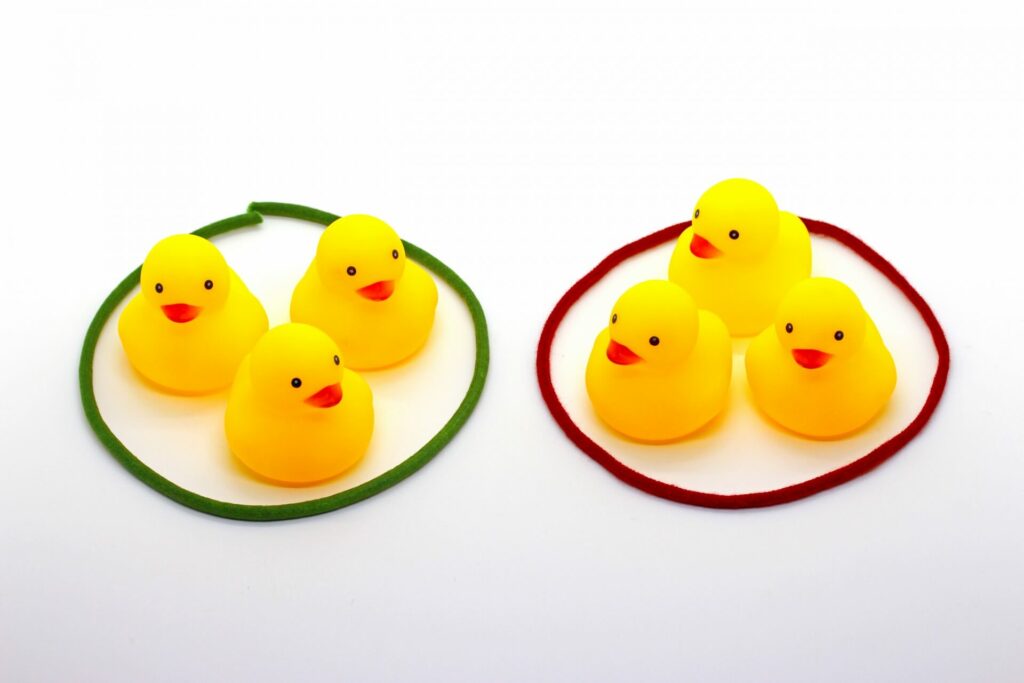
食品交換表の特徴として、栄養素が似ているものをグループ分けしています。
主に炭水化物を含む食品 | 表1 | ・穀物 ・イモ類 ・炭水化物の多い野菜と種実、豆(大豆を除く) |
| 表2 | ・くだもの | |
主にタンパク質を含む食品 | 表3 | ・魚介 ・肉 ・卵 ・チーズ ・大豆と大豆製品 |
| 表4 | ・牛乳 ・乳製品(チーズを除く) | |
| 主に脂質を含む食品 | 表5 | ・油脂 ・脂質の多い種実 ・多脂性食品 |
| 主にビタミン ・ミネラルを含む食品 | 表6 | ・野菜(炭水化物の多い一部の野菜を除く)海藻 ・キノコ類 ・こんにゃく |
食品交換表|実際の使い方
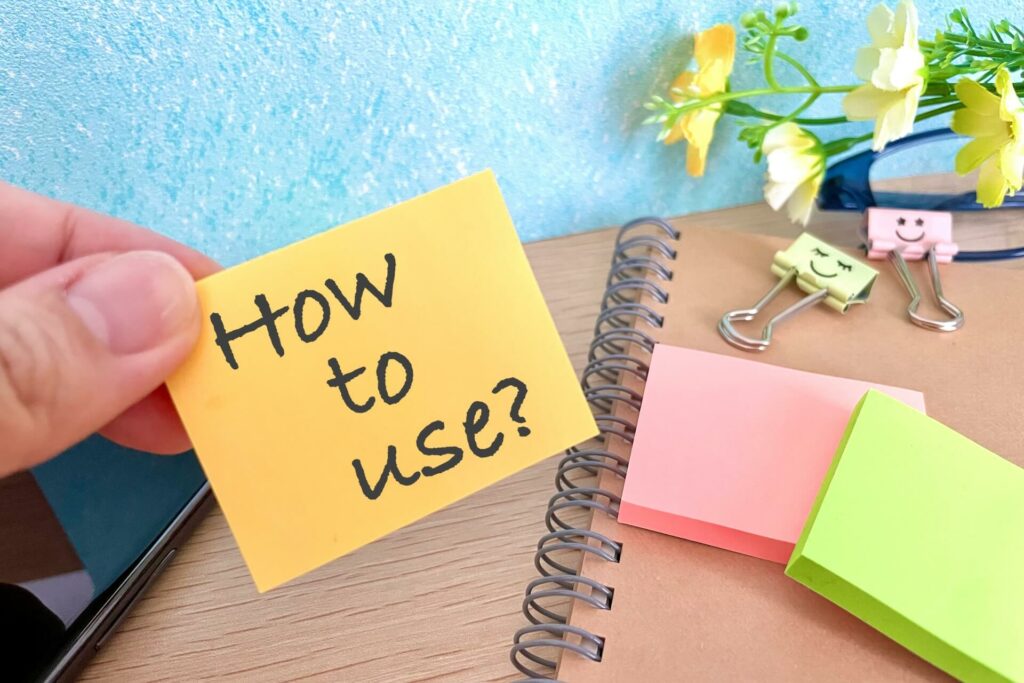
食品交換表の特徴として、単位で計算していきます。
80kcal=1単位 と考えます。
食品のカロリーを覚えなくても、1単位の量を覚えれば食べのもののカロリーの見当がつきます。
消費カロリーを計算して単位に変換する。
1600kcal=20単位 を1日で振り分けて食事をしていきます。
例
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
※主治医の指示や管理栄養士の指導で、食の嗜好や合併症の有無で振り分け単位を決定します。
さらに、上記を3食+間食に分けていきます。
| 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | 表5 | 表6 | 調味料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日の単位 | 9 | 1 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 |
| 朝食 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.8 |
| 昼食 | 3 | 2 | 0.4 | ||||
| 夕食 | 3 | 2 | 0.4 | ||||
| 間食 |
※表1.3.6の食品は朝・昼・夕に分けます
※表5と調味料はその日の調理に合わせて使用し、合計が1日量を超えないようにする
※表2.4の食品は3食に配分するか間食にする
食品の交換は同じグループの食品を同じ単位ずつ交換できますが、違うグループの食品とは交換できません。 [4]
Q&A

糖尿病食事療法の疑問を5つ解説します。
糖尿病の食事療法とは?
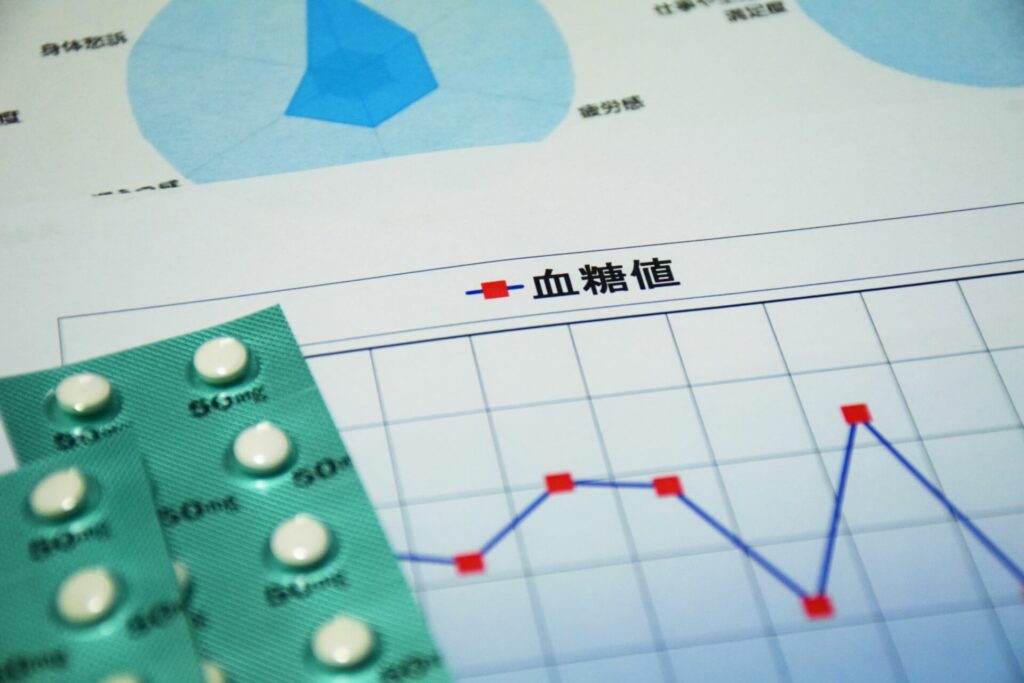
糖尿病の食事療法とは、高くなった血糖値をコントロールするように食生活を改善する治療法です。 2型糖尿病では治療の第一選択になります。
食事療法は食事制限ではなく、規則正しくカロリーと栄養バランスを考えて食べることが大切です。
糖尿病 食事療法で 治る?

2型糖尿病は生活習慣病ともいわれ、食生活の乱れや運動不足、遺伝が重なり糖尿病になると考えられています。
食生活を見直し改善することで、血糖値は安定するでしょう。
完治を目指すという治療ではなく、バランスのよい食事や適度な運動を続けることで合併症を予防することが重要です。
糖尿病の食事療法で大切なことは何ですか?

食事療法で大切なのは、規則正しく、3食バランスのよい食事を継続してとることです。
カロリーや脂質の多いケーキやとんかつなどを、絶対食べてはいけないわけではありません。
たまには、普段がんばっているご褒美として、好きなものを食べる日があってもいいのではないでしょうか。
次の日からまた、食事療法を継続していきましょう。
糖尿病の患者はどんな食事をとればいいですか?

主治医から指示があれば1日のカロリー量を守りましょう。
積極的にとったほうがいい食材は、食物繊維の多い野菜やキノコ類、海藻類です。 食物繊維は血糖値の急激な上昇を防げます。 動脈硬化予防に青魚もおすすめです。
糖尿病の食事療法で食べていいものは?

食物繊維の多い食品:野菜、キノコ類、海藻類、玄米など
良質なたんぱく質:魚、脂身の少ない肉、卵、大豆製品
塩分に注意しましょう。 減塩味噌や醤油を利用し、酢やだしで味付けしてみましょう。
塩は少なめにして、スパイスで味付けするのもおすすめです。
まとめ

糖尿病治療の第一選択肢ともいえる食事療法ですが、食事を制限するのではなく、血糖値を急上昇させない食品や食品を選んで食べましょう。
食事療法のポイントは次の5つです。
- ゆっくり噛んで、腹八分目に食べる
- サラダや汁物から先に食べる
- 積極的に食物繊維の多い食品を選んで食べる
- 食事は抜かず3食同じくらいの時間に食べる
- 炭水化物、タンパク質をバランスよく食べることを心がける
食事療法は継続することで合併症を防ぐことができます。 適度な運動も併せて行うと効果は大きいでしょう。
食事を見直すことは、糖尿病患者さんにだけではなく糖尿病でない人にとっても健康を維持するきっかけになります。
糖尿病の初期症状はほとんどないため、知らないあいだにゆっくり進行していくのが特徴です。糖尿病と診断、または糖尿病の疑いがある人は定期的な受診をしましょう。
参考文献