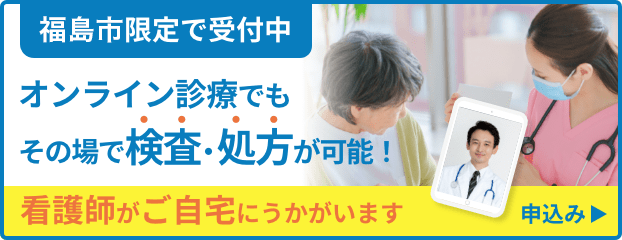認知症の薬物治療とは|薬の種類や効果・作用について解説
「認知症の薬って効くのかな」「いつまで飲むものなのかな」など、認知症の治療薬について疑問を持たれている方はいませんか?
認知症という言葉を聞いて、混乱や不安を感じる方も多いでしょう。しかし、現代医学の進歩により、認知症の症状を緩和し、生活の質を向上させるための多くの治療法が存在します。特に、薬物療法はその中でも重要な位置を占めています。
この記事では、認知症の治療に使用される薬について、その役割、種類、効果、副作用などをわかりやすくご説明します。

名倉 義人 医師
○経歴
・平成21年
名古屋市立大学医学部卒業後、研修先の春日井市民病院で救急医療に従事
・平成23年
東京女子医科大学病院 救急救命センターにて4年間勤務し専門医を取得
・平成27年
東戸塚記念病院で整形外科として勤務
・令和元年
新宿ホームクリニック開院
○資格
救急科専門医
○所属
日本救急医学会
日本整形外科学会
認知症の薬物治療とは
認知症の薬物治療は、大きく2種類に分けられます。
①中核症状に対する治療
中核症状というのは、認知機能の低下に伴う以下のような症状です。
- 記憶障害
- 見当識障害(日付や時間がわからない)
- 理解力の低下
- 失語(ものの名前を忘れるなど)
- 失行(動作のやり方がわからない)
これらは、認知機能低下に伴って悪化していく症状で、程度の差はありますが認知症の方全員にみられます。
②周辺症状に対する治療
周辺症状は「認知症の行動・心理症状」とも呼ばれ、認知機能の低下と直接の関係はないものの、中核症状と心・体・環境などさまざまな要因との関わりの中で生じる症状です。具体的には以下の症状です。
- 気持ちの落ち込み
- あせり、怒り
- 暴力的になる
- 徘徊
- 幻覚、妄想
- 無気力
認知症の方は心も体も繊細な状態です。環境からの刺激が多すぎても少なすぎてもうまく処理できず、結果として怒りっぽく見えたり、暴力的になってしまったりすることがあります。また、ちょっとした要因で気持ちが落ち込んでしまったり、薬の影響が強く出過ぎてしまったりと、あらゆることに過敏に反応してしまうのも特徴です。
周辺症状をうまくコントロールしてあげることで、ご本人も周りの方も生活がしやすくなります。
認知症治療に使われる薬の種類
認知症治療によく使われる薬について、作用や効果をご紹介します。
中核症状に使われる薬
認知症は、脳内の神経細胞の機能が少しずつ低下し、脳が正常な働きを維持できなくなる病気です。
今のところ、神経を再生させることはできません。
認知症そのものを「治す」ことはできませんが、抗認知症薬という分類の薬を使うことで、認知症の進行を遅らせたり、残っている神経細胞の働きを活発にしたりできると言われています。現時点で日本では4種類の薬がありますが、残念ながらいずれも劇的な効果が期待できるというわけではありません。そのため、副作用を心配して内服しないことを選ぶ方もいます。メリットデメリットを知った上で、内服するかどうかを選択することが大切ということです。
<コリンエステラーゼ阻害薬>
「アセチルコリン」という物質の分解を抑え、脳内でアセチルコリンの量が減らないようにする薬です。アセチルコリンは神経伝達物質と呼ばれ、脳内の情報伝達に使われます。アセチルコリンは神経細胞の中で作られるため、神経細胞が機能しなくなった認知症の方では量が減っており、新しい記憶の定着や、昔の記憶を思い出すことに支障が出てしまうのです。アセチルコリンの量を維持することで、記憶にまつわる能力の維持が期待できます。
副作用としては、少し気分が悪くなったり食欲が落ちたりするほか、脈がゆっくりになる、下痢といったものが報告されています。副作用が強い場合には量を減らすか、別の薬に変更することで改善されることが多いです。
・ドネペジル(商品名:アリセプト)
錠剤、粉薬、ゼリーと3種類のタイプがあります。1日1回の服用で、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症に使われます。
・ガランタミン(商品名:レミニール)
錠剤、液体の2種類のタイプがあります。アセチルコリンの働きを強める作用を持っている点が特徴的です。中等度までのアルツハイマー型認知症に使われます。
・リバスチグミン(商品名:イクセロンパッチ)
貼るタイプの薬です。薬を飲むことに抵抗のある方に使いやすいです。中等度までのアルツハイマー型認知症に使われます。
<NMDA受容体拮抗薬>
脳内では、アセチルコリンのほかにグルタミン酸という神経伝達物質も使われています。グルタミン酸は、NMDA受容体というスイッチに結合して、神経から神経へと情報を伝える物質です。
認知症の方は、通常よりもグルタミン酸の量が増えているだけでなく、NMDA受容体が過敏になっているという特徴があります。そのため、グルタミン酸がNMDA受容体と結合すると神経細胞が過剰に働いてしまい、神経が傷ついたり、正しく情報伝達ができなくなったりするのです。
NMDA受容体拮抗薬は、NMDA受容体にカバーをして、グルタミン酸と結合しないようにする働きがあります。神経を保護する作用のほか、情報伝達を穏やかにする作用も期待されます。
・メマンチン(商品名:メマリー)
メマンチンは、錠剤タイプのみです。気持ちを落ち着かせる作用が強いので、怒りっぽさが出ている方によく使われます。中等度〜高度のアルツハイマー型認知症に使う薬で、コリンエステラーゼ阻害薬と併用することもあります。
周辺症状に使われる薬
周辺症状は、ご本人にとっても周りの方にとってもつらさを感じやすい症状です。周辺症状に対しては、周りの方の関わり方を工夫したり、環境を整えたりといった非薬物療法(薬を使わないサポート)をおこなう必要があります。
その上で、なかなか改善がみられない周辺症状をやわらげるために、さまざまな薬が使われます。代表的なものをいくつかご紹介します。
<抗うつ薬>
気持ちの落ち込みが強い場合には、抗うつ薬を使います。薬の種類によっては食欲の改善効果もあるため、認知症によって食事への意欲が失われてしまった場合にも効果的です。
また、前頭側頭型認知症にみられる常同行動(目的のない行動を繰り返すこと)が抗うつ薬によって落ち着くこともあります。
<抗精神病薬>
幻覚や妄想、暴力行為、不穏(落ち着きがない状態)など、神経の興奮が原因と思われるような症状には、抗精神病薬が使われることがあります。
神経の過剰な興奮を抑えることで、症状の緩和が期待されます。一方で、眠気やふらつきといった副作用が出ることもあり、メリット・デメリットを考慮しながら使用を調整しなくてはなりません。
<抗不安薬>
認知症の初期には、ご自身の変化に対して不安な気持ちを抱かれる方が多いです。そういった場合に、抗不安薬を使うことがあります。ただし、進行した認知症には効果が得られにくいとされています。
また、レビー小体型認知症のレム睡眠行動異常(寝ている間に大声を出したり、手足を大きく動かしたりすること)の症状は、抗不安薬によって和らぐ可能性があります。
<睡眠薬>
認知症の方は、1日のリズムが崩れてしまい、睡眠障害を起こすことが多いです。寝つきが悪い、朝の目覚めがすっきりしない、眠りが浅く何度も目が覚めるなど、さまざまなタイプの症状が出ます。
睡眠がうまくとれないと、周辺症状の悪化に繋がってしまいます。きちんと夜に眠って朝に起きるというリズムができるように、サポートが必要です。一方で、睡眠薬の種類によっては、せん妄(意識の混乱した状態)が悪化したり、眠気が残って活動性が下がってしまったりと、よくない影響が出ることもあります。注意深く薬の調整をする必要があります。
睡眠薬を使うだけでなく、デイケアなどへ通って日中の活動を促したり、日光浴をしたり、寝室の環境を整えたりすることも、すすめていきましょう。
<漢方薬>
認知症に伴う不穏(落ち着きがない状態)やせん妄(意識の混乱した状態)、イライラ、不眠などさまざまな症状の改善に、漢方薬の有効性もわかってきています。ご本人の状態や体質によっては、漢方薬も選択肢の1つです。
まとめ
この記事では、認知症の薬について、わかりやすく説明しました。薬は症状を緩和し、生活の質を改善する役割がありますが、副作用もあるため、医師とよく相談することが大切です。
また、薬だけでなく、健康的な生活習慣も認知症の管理に重要です。あなたの理解が深まり、最善の治療を選ぶ一助となればうれしいです。認知症にまつわる症状で何かお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。
参考