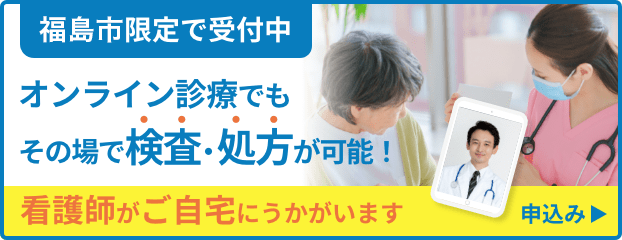アルツハイマー型認知症とは?症状や予防策、ケア方法について解説
アルツハイマー型認知症は、認知症の中でも最も一般的に知られているタイプの一つです。多くの人々がこの名前を耳にしたことがあるかもしれませんが、具体的にどのような症状や進行をとるのか、どのような原因があるのかは意外と知られていません。
この記事では、アルツハイマー型認知症の基本的な特徴や、予防策、ケア方法について詳しく解説します。

名倉 義人 医師
○経歴
・平成21年
名古屋市立大学医学部卒業後、研修先の春日井市民病院で救急医療に従事
・平成23年
東京女子医科大学病院 救急救命センターにて4年間勤務し専門医を取得
・平成27年
東戸塚記念病院で整形外科として勤務
・令和元年
新宿ホームクリニック開院
○資格
救急科専門医
○所属
日本救急医学会
日本整形外科学会
アルツハイマー型認知症とは?
まずは、アルツハイマー型認知症の特徴などについて解説します。
アルツハイマー型認知症の発症メカニズム
認知症全体の40〜60%がアルツハイマー型で、最も多いタイプです。
70歳代からアルツハイマー病の罹患率は急激に上昇し、男性に比べると女性の罹患率がやや高い傾向にあります。アルツハイマー型認知症では、記憶に関わる「海馬」という部分が早期から萎縮するのが特徴です。
高齢発症のアルツハイマー病は、アミロイドβやタウタンパクと呼ばれる異常なタンパク質が、脳内に異常に溜まることが原因で発症します。これらのタンパク質がなぜ溜まってしまうのかは、まだわかっていません。
溜まった異常なタンパク質により、脳神経がダメージを受けて死んでしまいます。死んでしまった脳神経は再生しないため、脳の機能がだんだんと低下して、認知症となってしまうのです。
アルツハイマー型認知症の症状
症状が目立たない早期や発症前の段階、続いて、軽度認知障害(MCI)という中期の段階、そしてアルツハイマー病による認知症という3つのフェーズで進行するとされます。
<軽度認知障害(MCI)の症状>
65歳以上の高齢者では20%前後が軽度認知障害に該当します。
- 少し前のことを忘れてしまう新しいことを覚えられない
- 計画を立てて物事をこなすのが難しくなる
- 気力が低下する
- 家事や仕事で失敗することが増える
- 置き忘れ、しまい忘れが増える
- 日常生活は送れる
<軽度アルツハイマー型認知症の症状>
- お金の取扱いや支払いに問題が生じる
- 質問を繰り返す
- 今までできていた日常作業に手間取るようになる
- 物をなくす、置いた場所を忘れる、それに伴う「もの盗られ妄想」
- 自分の生い立ちについての記憶が減ってくる
- 感情および人格の変化
多くの場合、この段階でアルツハイマー病と診断されます。
<中等度アルツハイマー型認知症の症状>
- 住所や電話番号、日付、曜日などが思い出せなくなる
- 引き算などが難しくなる
- 季節や状況に合った服装を選べない
<高度アルツハイマー型認知症の症状>
- 自分の名前はわかるが、生い立ちについてわからないことが多い
- 家族や友人の名前や顔の見分けが難しくなる
- 食事やトイレの介助が必要になる
- 生活リズムが乱れることがある
- 着替えなど、複数の手順による作業が難しくなる
- 幻覚、妄想の出ることがある
徐々に、コミュニケーションが難しくなったり、体の動きをコントロールできなくなったりする場合もあります。
3つのリスク要因
基本的に、加齢・遺伝・生活習慣の3つが、アルツハイマー型認知症を発症する大きな要因です。
アルツハイマー認知症は、加齢に伴って増える疾患で、70歳以上での発症が多いです。30〜60歳で発症する「若年性アルツハイマー病」はごく稀で、ほとんどの症例は家族性であることが知られています。
また、近年、アポリポ蛋白E(APOE)遺伝子が、アルツハイマー型認知症と関連するらしいとわかってきました。この遺伝子にはいくつかの種類がありますが、その1つであるAPOE ε4は、アルツハイマー型認知症の発症リスクを上昇させると考えられています。
ただし、APOE ε4型を保有していれば必ずアルツハイマー型認知症を発症するわけではなく、またAPOE ε4を保有しない人でもアルツハイマー病を発症しますので、全てのアルツハイマー型認知症の原因とはいえません。
生活習慣としては、喫煙がアルツハイマー型認知症を悪化させることがわかっています。禁煙すると、認知症の発症リスクは非喫煙者と同等になりますので、禁煙がおすすめです。また、中年期の高血圧・脂質異常症・糖尿病も、アルツハイマー型認知症のリスクを高めます。こうした疾患は、食事や運動が関連したものですので、定期的に健康診断を受け、見つかった疾患の治療をし、食事や運動に気を配ることが大切です。
アルツハイマー型認知症の検査
アルツハイー型認知症の診断のためには、問診と認知機能検査が重要です。記憶や注意力、計算能力、言語能力などさまざまな分野の能力をまんべんなく検査し、認知機能の状態を確認します。
そのほか、脳の形状をみるCT/MRI検査、脳の血流などをみるSPECT検査、血液検査、交感神経の働きを調べる心筋シンチグラフィ検査などをおこない、総合的に判断します。
アルツハイマー型認知症の治療法
今のところ、アルツハイマー型認知症を「治す」ことはできず、進行を遅らせたり、認知症に伴う症状を和らげたりする治療をおこなっています。アルツハイマー型認知症の進行を抑える代表的な薬は2種類です。
<コリンエステラーゼ阻害薬>
「アセチルコリン」という物質の分解を抑え、脳内でアセチルコリンの量が減らないようにする薬です。アセチルコリンは神経伝達物質と呼ばれ、脳内の情報伝達に関わります。アセチルコリンは神経細胞の中で作られるため、神経細胞が減少した認知症の方では量が減っており、新しい記憶の定着や、昔の記憶を思い出すことに支障が出てしまうのです。アセチルコリンの量を維持し、記憶にまつわる能力の維持が期待できます。
副作用として、少しムカムカしたり食欲が落ちたりするほか、脈がゆっくりになる、下痢といったものが報告されています。副作用が強い場合には量を減らすか、別の薬に変更することで改善されることが多いです。
ドネペジル(商品名:アリセプト)
錠剤、粉薬、ゼリーと3種類のタイプがあります。1日1回の服用です。
ガランタミン(商品名:レミニール)
錠剤、液体の2種類のタイプがあります。アセチルコリンの働きを強める作用を持っている点が特徴的です。中等度までのアルツハイマー型認知症に使われます。
リバスチグミン(商品名:イクセロンパッチ)
貼るタイプの薬です。薬を飲むことに抵抗のある方に使いやすいです。中等度までのアルツハイマー型認知症に使われます。
<NMDA受容体拮抗薬>
脳内では、グルタミン酸という神経伝達物質も使われます。グルタミン酸は、NMDA受容体というスイッチに結合し、神経から神経へと情報伝達を担う物質です。
認知症の方は、通常よりもグルタミン酸の量が増えているだけでなく、NMDA受容体が過敏になっているという特徴があります。そのため、グルタミン酸がNMDA受容体と結合すると神経細胞が過剰に働いてしまい、神経が傷ついたり、正しく情報伝達ができなくなったりするのです。
NMDA受容体拮抗薬は、NMDA受容体をカバーして、グルタミン酸と結合しないように働きます。神経を保護する作用のほか、情報伝達を穏やかにする作用も期待されます。
メマンチン(商品名:メマリー)
メマンチンは、錠剤のみです。気持ちを落ち着かせる作用が強いので、怒りっぽさが出ている方によく使われます。高度のアルツハイマー型認知症にも使うことができ、コリンエステラーゼ阻害薬と併用することもあります。
そのほか、気持ちの落ち込みや不安、睡眠障害、幻覚など、認知症に伴う周辺症状に対して、さまざまな薬が使われます。リハビリも効果的です。体を動かすリハビリのほか、音楽鑑賞や創作活動に取り組むことも脳神経の活性化によいとされます。
まとめ
今回は、アルツハイマー型認知症についてご紹介しました。
アルツハイマー型認知症は、記憶障害をはじめとするさまざまな認知機能の低下を引き起こす疾患です。脳内に異常なタンパク質が溜まることで、記憶が失われ、徐々に日常生活にも支障をきたす病気です。
症状の進行は徐々にとなり、初期には日常生活におけるちょっとした忘れ物や繰り返しの行動が見られることが多いです。現在のところ、根本的に治すための方法は見つかっておらず、内服薬で進行を遅らせるしかありません。
予防としては、高血圧・脂質異常症・糖尿病などの疾患をきちんと治療することや、禁煙が効果的です。また、健康的な食生活や適度な運動、知的活動を続けることも重要です。現在も研究が続けられており、早期発見や適切なケアによって、患者さんとその家族の生活の質を高める努力が続けられています。
参考
・日本精神神経学会. 認知症疾患診療ガイドライン2017.
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html
・T Ohara et al. Glucose tolerance status and risk of dementia in the community: the Hisayama study. Neurology. September 20, 2011; 77 (12)
・May A Beydoun et al. Epidemiologic studies of modifiable factors associated with cognition and dementia: systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2014 Jun 24;14:643.