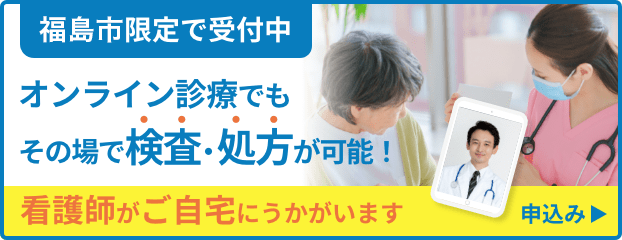レビー小体型認知症の原因や症状、なりやすい人や治療法を解説
レビー小体型認知症は、名前からは一見なじみのない疾患に思えるかもしれませんが、認知症の中でも比較的よく知られるタイプの1つです。症状の一部はアルツハイマー型認知症と似ていますが、特有の症状や進行の様子が異なります。
早期発見と適切なケアが患者さんの生活の質を向上させる鍵となることも知られています。この記事では、レビー小体型認知症の特徴や原因、日常での対応方法などについて詳しく説明していきます。

名倉 義人 医師
○経歴
・平成21年
名古屋市立大学医学部卒業後、研修先の春日井市民病院で救急医療に従事
・平成23年
東京女子医科大学病院 救急救命センターにて4年間勤務し専門医を取得
・平成27年
東戸塚記念病院で整形外科として勤務
・令和元年
新宿ホームクリニック開院
○資格
救急科専門医
○所属
日本救急医学会
日本整形外科学会
レビー小体型認知症とは?
まずは、レビー小体型認知症の原因や症状について詳しく解説します。
レビー小体型認知症の発症メカニズム
レビー小体型認知症は、実はアルツハイマー型認知症、脳血管型認知症に次いで日本で3番目に多い認知症です。65歳以上の高齢者に多く発症しますが、30〜50代で発症する場合もあります。また、比較的男性に多いのも特徴の一つです。
主な原因は、脳内の神経細胞に蓄積する「レビー小体」というタンパク質です。レビー小体は体のあらゆる部位に溜まって細胞を壊しますが、大脳皮質に溜まって神経細胞が破壊されると、レビー小体型認知症となります。
レビー小体が蓄積する原因はまだわかっておらず、現在のところ、加齢による自然な変化と考えられています。
レビー小体型認知症の症状
症状の初期は比較的認知機能が維持されています。中期になるとパーキンソン症状(パーキンソン病に似た症状)が強くなり、歩行が困難になるなど体の動きが悪化すると同時に、記憶の低下や見当識障害(日にち・曜日などが把握できなくなる)も見られはじめます。
1日の中での意識レベルの変動や幻視・妄想の症状も強いです。後期になると、日常生活(食事・トイレ・着替えなど)に介助が必要となります。
レビー小体型認知症に特徴的な症状
次に、レビー小体型認知症に特徴的な症状をご紹介します。みなさんがイメージされる認知症とは少し異なる症状が多いかもしれません。
<認知機能の変動>
認知機能は、日によって、また、1日の中でもムラがあるのが特徴です。調子がよいときには通常通りの会話が成立しますが、日時や場所などが把握できなかったり、集中力や注意力が低下したりするときもあります。症状が進行するに従い、徐々に症状が一定となり、意識レベルが低い状態が続くようになっていきます。
<幻視・錯視>
初期から幻視・錯視の症状がみられます。
「そこに知らない人がいる」「虫が飛んでいる」など、実際には存在しないものがはっきりと見えたり、「(小さなゴミが)虫にみえる」「(壁の模様が)女の子にみえる」と実際とは別のものに見えたりするような症状です。
<パーキンソン症状>
レビー小体が、脳内の「脳幹」という部位にまで広がっていくと、パーキンソン症状がみられるようになります。パーキンソン症状は、パーキンソン病に似た運動の障害で、以下のような症状が代表的です。
- 手が震える
- 歩きにくくなる
- 姿勢が取りにくく、前かがみになる
- 急に止まることができない
このように、体の動きがスムーズにいかない症状が出るため、レビー小体型認知症の方は転倒のリスクが高く、注意しなくてはなりません。
パーキンソン病と診断されて1年以内に認知機能障害を生じた場合には「認知症を伴うパーキンソン病」、パーキンソン症状が出る前あるいは同時に認知症を発症した場合には「レビー小体型認知症」として、区別します。
<自律神経症状>
レビー小体は、脳内だけでなく、体中の自律神経内にも出現します。そのため、自律神経によるさまざまな調節がうまくいかなくなり、便秘や尿失禁、汗が出る、起立性低血圧(立ちくらみ)などの症状があらわれます。便秘症状は、7割以上の方で記憶障害が出始めるよりも前からみられるようです。
<レム睡眠行動異常>
眠っている間に大声で叫んだり暴れたりする「レム睡眠行動異常」が見られることもあります。この症状は、認知症を発症する何年も前からみられる場合も少なくありません。
睡眠の後半に出現することが多く、本人や同居家族が怪我をしたり、睡眠が阻害されたりするために治療が必要です。
発症に関与するリスク要因
レビー小体型認知症に関しては、アルツハイマー型認知症と比べると、リスク要因があまり判明していません。現在のところ、関わりがあると考えられているのは以下です。
- 加齢
- 遺伝的要因
- 不安障害やうつ病の既往
- パーキンソン病
パーキンソン病の診断を受けている方は、そうでない方と比べて認知症を発症するリスクが4〜6倍高いことがわかっています。
レビー小体型認知症の検査
レビー小体型認知症の診断のためには、問診と運動症状(パーキンソン症状)の確認が重要です。パーキンソン症状が出る疾患はいくつかあるため、断定するためにはさまざまな検査が必要となります。
認知機能検査、脳の形をみるMRI検査、脳の血流などをみるSPECT検査、血液検査、交感神経の働きを調べる心筋シンチグラフィ検査などをおこない、総合的に判断します。
レビー小体型認知症の治療法
レビー小体型認知症を根本的に治す治療法は見つかっていません。進行を遅らせたり、症状を抑えて過ごしやすくするための治療をおこないます。
薬物療法
認知機能の低下を抑える治療のほか、お困りの症状ごとに内服薬の調整をおこなって対処します。
<コリンエステラーゼ阻害薬>
「アセチルコリン」という物質の分解を抑え、脳内でアセチルコリンの量が減らないようにする薬です。
アセチルコリンは、脳内の情報伝達に使われます。アセチルコリンは神経細胞の中で作られるため、神経細胞が機能しなくなった認知症の方では量が減っており、新しい記憶の定着や、昔の記憶を思い出すことに支障が出てしまうのです。アセチルコリンの量を維持することで、記憶にまつわる機能の維持が期待できます。
副作用として、少しムカムカしたり食欲が落ちたりするほか、脈がゆっくりになる、下痢といったものが報告されています。副作用がつらい場合には、服用しないことも選択肢となります。
・ドネペジル(商品名:アリセプト)
錠剤、粉薬、ゼリーと3種類のタイプがあります。
<パーキンソン病治療薬>
手の震えや体の動かしにくさなど、パーキンソン症状が現れてくると、日常生活に支障が出ます。症状を抑えるために、パーキンソン病の治療薬が有効な場合があります。
<レム睡眠行動異常の治療>
レム睡眠行動異常では、壁を叩いて怪我をしてしまったり、大声を出してご家族の睡眠が阻害されたりしてしまうため、薬を服用して症状を抑えることをおすすめしています。
・クロナゼパム(商品名:リボトリール、ランドセン)
筋肉の緊張をほぐし、不安をやわらげる作用の薬です。レム睡眠行動異常によく使われますが、ご高齢の方では効果が強すぎてしまう場合もあり、量を調整しながら服用します。
・ラメルテオン(商品名:ロゼレム)
体内時計をコントロールしている「メラトニン」というホルモンの働きを整える作用の薬です。ご高齢の方にも比較的安全に使えます。
また、ストレスやアルコール、カフェインのとりすぎなどがレム睡眠行動異常を悪化させると考えられていますので、日常生活にも気を配ってみてください。
<その他>
ここでご紹介した以外にも、便秘や幻覚など、お困りの症状があれば薬や環境調整などで対応します。
リハビリテーション
レビー小体型認知症の方は、パーキンソン症状の進行によって歩行が難しくなることが多いです。
歩行の能力を維持するため、リハビリテーションをおこないましょう。ストレッチやウォーキングなど、個々人の状態に合わせたリハビリテーションの計画を立てることが重要です。
体を動かす運動療法のほかにも、アルバムなどを使って記憶を強化する「回想法」、馴染みの音楽を聴いて精神安定をはかる「音楽療法」、パズルや計算などで脳を刺激する「認知機能訓練」など、さまざまなリハビリテーションが有効とされます。
まとめ
今回は、レビー小体型認知症についてご紹介しました。レビー小体型認知症は、神経細胞内に「レビー小体」と呼ばれる特異的なたんぱく質の塊が蓄積することで起こる認知症です。
主な症状としては、思考の混乱、幻覚、運動機能の障害などが挙げられます。また、認知機能の低下を自覚する何年も前から便秘・レム睡眠行動異常といった症状が出るのが特徴です。
早期発見と適切なケアが患者さんの生活の質を向上させる鍵となります。患者さんとその家族は、医療専門家と連携しながら、症状の管理とサポートを受けることで、より良い状態を保ちましょう。
参考
・日本精神神経学会. 認知症疾患診療ガイドライン2017.
https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html
・立花 久大. パーキンソン病の認知機能障害. 精神雑誌(2013) 115巻 11号.
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1150111142.pdf
・森 悦朗. Lewy小体型認知症の治療. 神経治療 37: 32-38, 2000.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsnt/37/1/37_32/_pdf/-char/ja