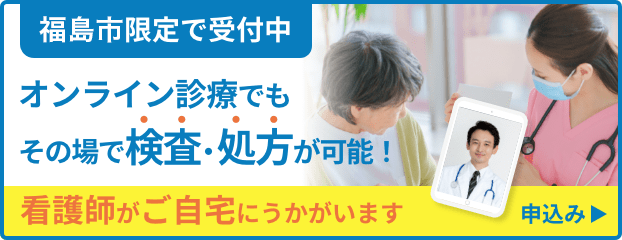インスリンの単位とは?投与量の決め方や計算方法も解説!
インスリンは、糖尿病の治療において欠かせない存在です。
インスリンを使用するうえでは、インスリンの種類や特徴、その管理方法など一定の知識と正確な理解が必要不可欠と言えます。
また、インスリンの単位や使用する量の決め方、計算方法なども知っておくと血糖コントロールの強い味方となるでしょう。
今回の記事では、インスリンの単位や決め方、計算方法を中心に、インスリンの正しい使い方や管理方法、インスリン製剤の種類などを紹介します。
インスリンの正しい知識を得ることで、安定した血糖コントロールを目指しましょう。

名倉 義人 医師
○経歴
・平成21年
名古屋市立大学医学部卒業後、研修先の春日井市民病院で救急医療に従事
・平成23年
東京女子医科大学病院 救急救命センターにて4年間勤務し専門医を取得
・平成27年
東戸塚記念病院で整形外科として勤務
・令和元年
新宿ホームクリニック開院
○資格
救急科専門医
○所属
日本救急医学会
日本整形外科学会
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
インスリンの単位と1単位で下がる血糖値

インスリンの単位と、インスリン1単位で下がる血糖値について解説します。
インスリンの単位とは
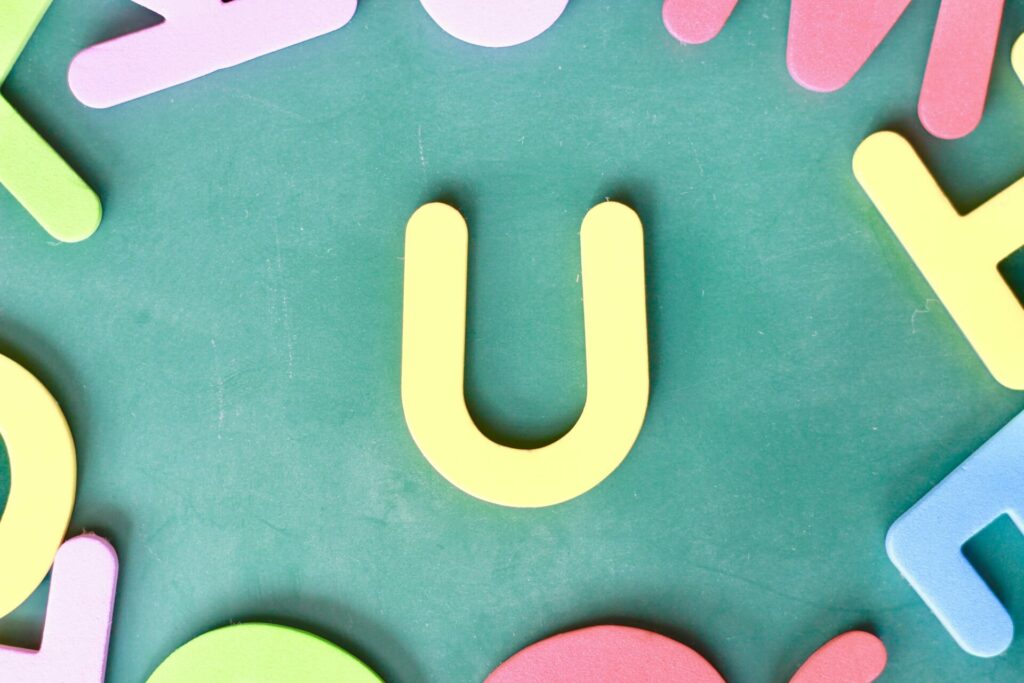
医薬品のインスリンは、重量ではなく生物学的力価である「単位(Unit)」という単位で表現され、「U」という記号で表します。
インスリンの単位換算では1単位が0.01mlです。
誤解や勘違いをしていると、過剰摂取や過少摂取に繋がり、危険です。正しく認識しておきましょう。
インスリン1単位で下がる血糖値
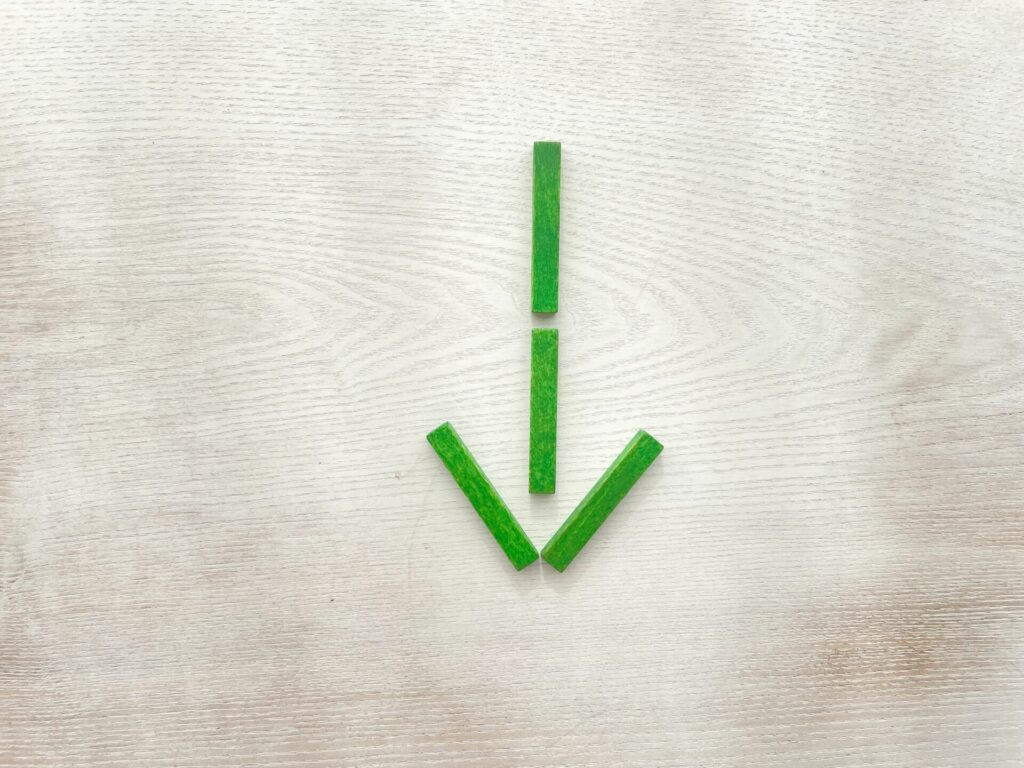
インスリン1単位でおおよそ50mg/dL、血糖値が下がるとされています。
しかし、これはあくまで目安なので、個人差があります。また、個人でもその日の体調や状態によっても異なってくるでしょう。
また、腎機能が悪い方は、インスリンの排泄が悪く、血中にとどまる傾向です。
そのような場合、1単位で血糖値が予想より下がる場合があるため注意しましょう。
ちなみに、インスリン1単位で10gの糖質を処理できるとされています。
目安として参考程度に考えておきましょう。
インスリン投与量(単位)の決め方と計算方法

インスリンの投与量の決め方と計算方法を紹介します。
インスリンの計算方法を知っていれば、血糖コントロールの役に立つでしょう。
インスリン投与量(単位)の決め方
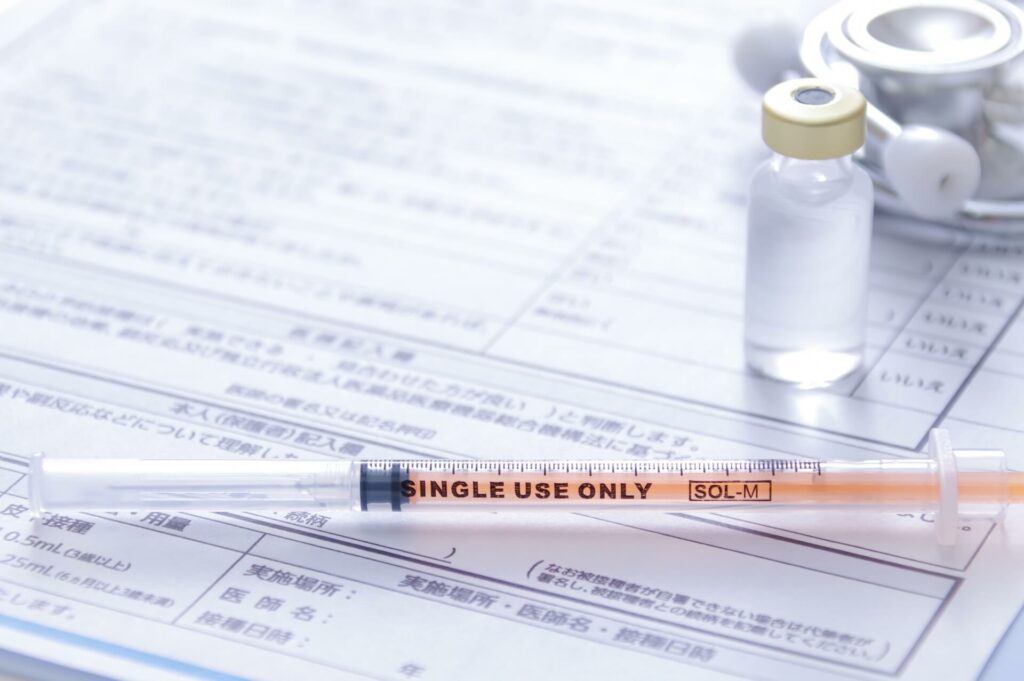
目安としては、体重1㎏に対し0.8〜1.0単位のインスリンが必要とされています。
また、健康な人の1日に分泌されるインスリン量は24〜37単位(平均31単位)程度です。
まずは、患者の状態に合わせ、目標血糖値を設定します。
それに応じてインスリン製剤の種類や投与方法を選択し、注射量は医師が決定します。
インスリン療法は毎日継続していくことが大切です。
インスリン製剤によって投与回数やタイミングが異なるため、自分のライフスタイルに取り入れやすいものを医師と相談して決めましょう。
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
インスリン計算方法のカーボカウントとは

インスリン計算方法にカーボカウントというものがあります。
食事に含まれる糖質量を把握してインスリン量を調節し、食後の血糖値をコントロールする方法です。
どの程度食べたら、どの程度のインスリンが必要になるのかが分かるようになるため、食後の血糖値を安定させやすくなります。
以下の表は、食品に含まれる糖質が多いものと少ないものの分類です。
| 糖質が多い食品 | 糖質が少ない食品 |
|---|---|
| ・穀物・くだもの・牛乳・チーズを除く乳製品・みそ・みりん・カレーのルウ・ジュース・菓子類 | ・魚介類・卵・肉・チーズ・油脂類・海藻・きのこ・こんにゃく |
市販の総菜やお弁当は、食品成分表示を参考にすると良いでしょう。
カーボカウントは、「基礎カーボカウント」と「応用カーボカウント」に分けられます。
| 基礎カーボカウント | 応用カーボカウント |
|---|---|
| ・毎食の糖質を一定にする・糖尿病の人全員が対象になる・一日の摂取エネルギーのうち50~60%程度を糖質で摂取するよう調節する | ・食事の糖質量を一定にする必要はない・食前の血糖値と摂取する糖質により投与するインスリン量を決める・1型糖尿病の方やインスリン依存状態の2型糖尿病が対象 |
カーボカウントをする際に、必要な数値が3つあります。
- インスリン/カーボ比
- インスリン効果値
- 食前に投与するインスリン量
インスリン/カーボ比は、1カーボの糖質に対して必要な超速効型または速効型インスリン量です。1カーボは、糖質10gとされています。
インスリン/カーボ比は、「1日の総インスリン量÷50」で求めることができます。
インスリン効果値は、超速効型または速効型インスリン1単位で、どのくらい血糖値が下がるかという効果を表す数値です。
インスリン効果値は、「1800÷1日の総インスリン量」で求めることができます。
「インスリン/カーボ比+インスリン効果値」で、食前に投与するインスリン量が算出できます。
ただし、この計算で算出されるものは、あくまで目安です。個人差がありますので、治療を行っていく中で、担当の医師と相談してすすめましょう。
カーボカウントができれば、食事の幅が広がり、楽しめるようになります。
しかし、糖質ばかりに注目しがちで、脂質やタンパク質、カロリーが過剰となる場合があります。
糖質に注意しつつも、バランスの良い食事を心掛けましょう。
スライディングスケールとは
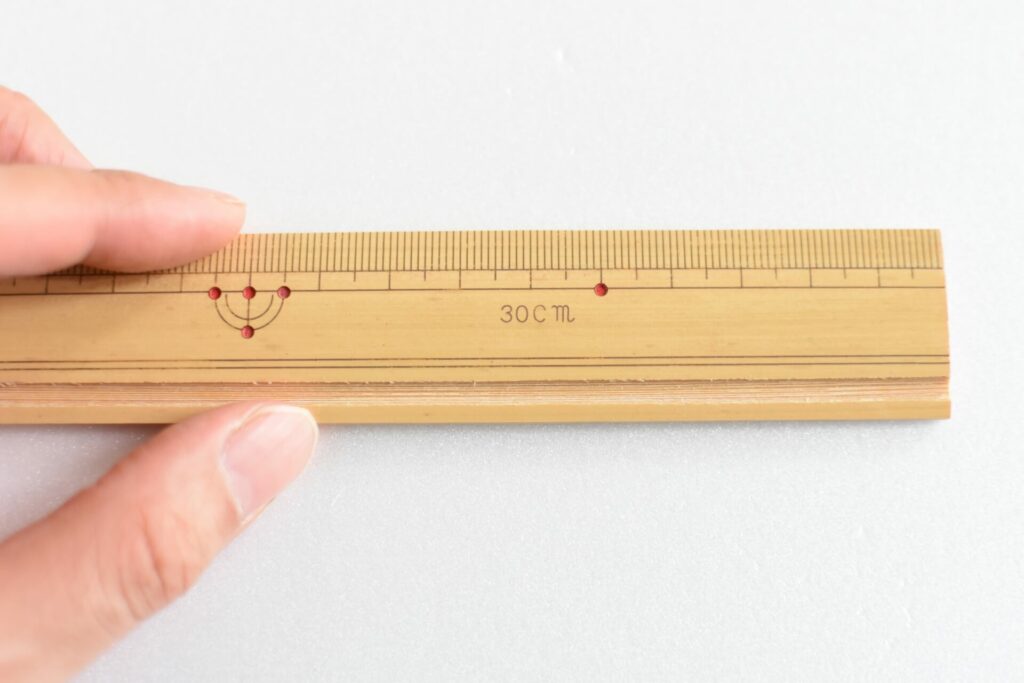
スライディングスケールとは、直前の血糖値によってインスリンの投与量を加減するための目安です。
個々の病状や血糖値の変動パターン、体重当たりのインスリン必要量によって、医師がスケールの数値設定を行います。
測定した血糖値の数値によって、スライディングスケールに沿ったインスリン量を投与します。
食前血糖値目標によって、インスリン量を調節することで、より良好な血糖コントロールができることがメリットです。
スライディングスケールを利用する場合、超速効型インスリンあるいは速効型インスリンを使うのが一般的とされています。
インスリンの働きと血糖値を下げる仕組み
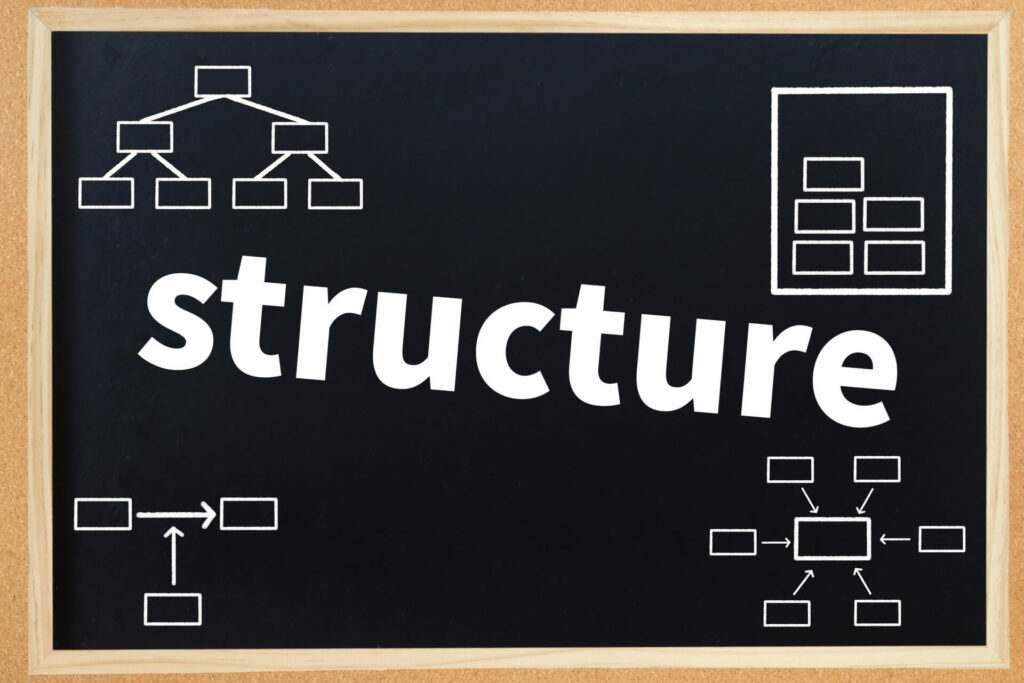
インスリンの働きと血糖値を下げる仕組みを解説します。
インスリンの働き
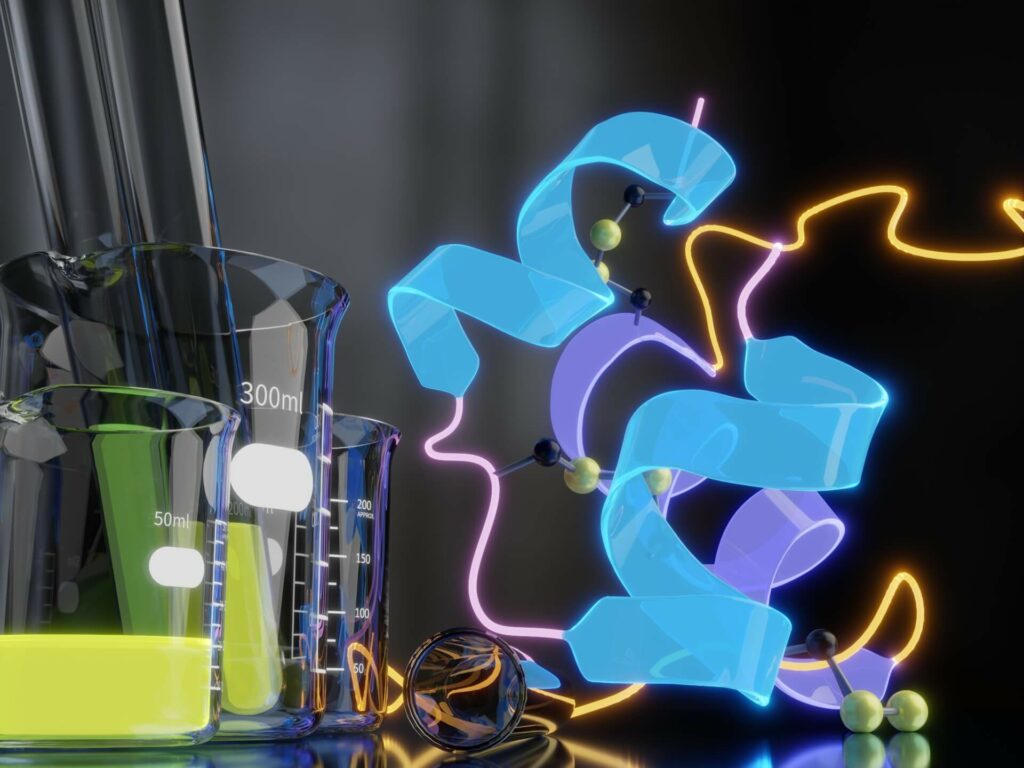
インスリンは膵臓から分泌される、血糖を下げる働きのあるホルモンです。糖の代謝を促し、血糖値を一定に保つよう作用します。
すい臓にランゲルハンス島と呼ばれる細胞の集まりがあり、その中のβ細胞からインスリンが分泌されています。
何らかの原因により、インスリンの分泌が完全に障害されている病態が1型糖尿病です。
また、インスリンの分泌障害が生活習慣病として引き起こされるものが2型糖尿病です。
人間は、食物を摂取すると血液中にブドウ糖が吸収され、血糖値が上昇します。
少量のインスリンは、絶えず分泌されています。しかし、血糖値が上昇すると、追加でインスリンが分泌され始め、血糖値を下げるよう作用します。
インスリンは血糖値を下げる唯一のホルモンです。
血糖値を下げる仕組み

糖を含む食べ物を摂取すると、消化酵素によってブドウ糖に分解されます。
ブドウ糖は、小腸から吸収され、血液で全身に運ばれます。
このとき、血液中にブドウ糖が多くなっているのが「血糖値が上がった」状態です。
上がった血糖値を下げるため、すい臓のβ細胞からインスリンが分泌されます。
インスリンは、血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませ、エネルギーとして利用するよう促します。
また、過剰なブドウ糖は中性脂肪や肝臓のグリコーゲンに合成して体の中に蓄えるように作用するため、血糖値が下がるのです。
インスリン注射とは

インスリン注射とは、インスリン療法で行うインスリンの自己注射です。
不足しているインスリンを補うことで、血糖値を下げます。
絶えず少量分泌されているインスリンを「基礎分泌」、食物の摂取後に血糖の上昇に対応して分泌されるのを「追加分泌」と言います。
1型糖尿病の方には、インスリン注射が必ず必要です。
1型糖尿病では「基礎分泌」と「追加分泌」がともに障害されている状態のため、インスリンの自己注射をして補う必要があります。
2型糖尿病では早期から、特に「追加分泌」が障害され、進行すると「基礎分泌」も障害される場合があります。
進行具合によって、インスリンの自己注射が必要です。
インスリンの自己注射のやり方

自己注射と聞くと「大丈夫かな?」「ちゃんとできるかな?」と不安になりますよね。
インスリン自己注射の開始前には、病院で教育入院をしたり、外来で医療従事者から扱い方や使い方の指導があったりするので安心してください。
インスリンの自己注射はペン型の専用注入器が主流になっています。
ここでは、ペン型注入器での自己注射の方法を紹介します。
- 必要な物を準備(インスリンペン型注入器、針、アルコール綿)
- 手を洗う
- インスリンペン型注入器、針、インスリンの種類を確認
- インスリン量が空打ち分と投与予定量があるか確認
- インスリンが懸濁している種類は上下に振るか手のひらで転がす
- 振りすぎると気泡だらけになるので注意
- ゴム栓をアルコール綿で消毒し針を付ける
- 針キャップをはずす
- インスリンペン型注入器を空打ちの必要単位数に合わせる
- 針先を上に向け2~3回はじいて気泡を集める
- 注入ボタンを押して空気を出す(空打ち)
- 薬液がしっかり出たことを確認
- 単位ダイヤルが0であることを確認して指示された単位に合わせる
- 注射する部位をアルコール綿で消毒
- 皮膚をつまみ上げ針を垂直に刺す
- 注入ボタンを押す
- 注射後5~6秒経過してから針を抜く
注射部位に適した部位は以下の4ヶ所です。
- おなか
- 上腕の外側
- おしり
- 太ももの外側
連続して同じ場所に注射しないよう、注射部位はローテーションし、2〜3㎝以上ずらしましょう。
針は、自治体によって回収方法が異なりますので確認してから捨ててください。
通院している医療機関で回収してもらえる場合があるので、相談してみるのもいいでしょう。
インスリン注射の副作用
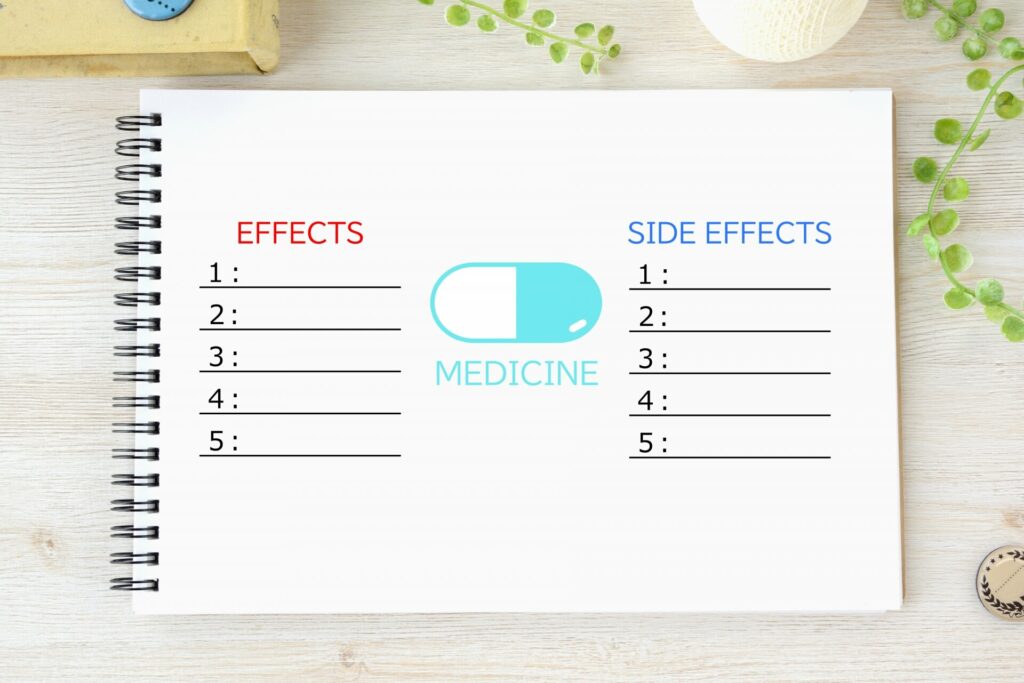
インスリンの注射で起こる主な副作用は、以下の3つです。
- 低血糖
- リポハイパートロフィー
- インスリンアレルギー
低血糖は、インスリンの効果で血糖値が下がり過ぎた状態です。
手の震えや冷や汗、動悸、眠気、めまい、頭痛などの症状が現れます。
重篤な場合、もうろうとして意識を消失する可能性があり、危険な副作用と言えます。
リポハイパートロフィーは、インスリンボールとも言われる皮膚病変です。
同じ場所や近い場所に何度もインスリンを打っていると、皮下の脂肪細胞が増大します。
その脂肪細胞が、ボールのような柔らかい腫瘤になったものや、かたく硬結したものを指します。
リポハイパートロフィーができた部分は注射をしても痛みを感じにくく、インスリンの吸収も悪くなり十分な効果が発揮できません。
結果、血糖コントロールの不良に繋がるため、同じ場所への注射は避け、リポハイパートロフィーができないよう注意しましょう。
もしリポハイパートロフィーができてしまったら、その部分を避けて注射をします。
数ヶ月で自然に消失し、徐々にインスリンの吸収も改善するでしょう。
インスリンアレルギーは、まれに起こる副作用です。注射部位に、発赤や腫脹、発疹、かゆみが出現します。
重症例では全身に薬疹が出現し、血糖コントロールも不良になります。
低血糖とリポハイパートロフィーは、インスリンの適切な使用と対処法で予防することができるでしょう。
インスリンの管理方法
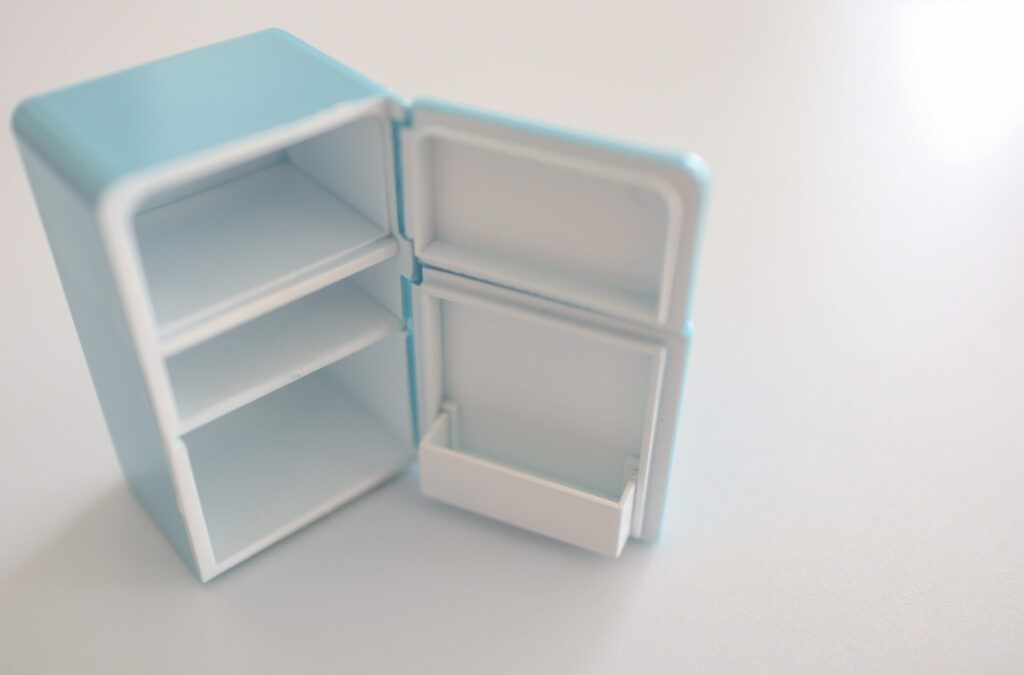
インスリンの管理は温度が重要です。
未使用のインスリンは2〜8℃での保管が適切なため、冷蔵庫で保管します。凍結しないように注意しましょう。
冷却風が当たらない、ドアポケットに保管するのがおすすめです。
万が一、インスリンが凍結してしまった場合、以下のようなリスクがあります。
- 凍結したことによる品質や成分の変化
- ゴム栓のふくらみやカートリッジの破損
- カートリッジ内に大きな気泡が発生
凍結してしまったインスリンは使用しないようにしましょう。
使用中のインスリンは、室温または涼しい所で保管してください。
冷蔵庫で保管すると、注射のたびに冷蔵庫から出し入れするため、温度の変化が著しくなります。
温度変化が著しいと、注入器が結露する可能性があり、結露は故障の原因になります。
また、冷たいままのインスリンを注射すると、痛みが強くなりやすいためおすすめできません。
注意したいのが、外出の際に、インスリンを携帯する場合です。
30℃を超えるような真夏は、インスリンを断熱バッグに入れて携帯しましょう。保冷剤と一緒に入れておくと安心です。
ただし、断熱バッグに入れて保冷剤を一緒に入れていても、高温になる車内に放置したり直射日光が当たるような場所に置いたりしないようにしましょう。
また、寒冷地や気温が2℃以下になる真冬は、インスリンが凍結しないよう注意が必要です。
乾いたタオルで巻いて携帯したり、夏同様に断熱バックを使用すると、凍結の心配がなく安心でしょう。
インスリン注射の費用
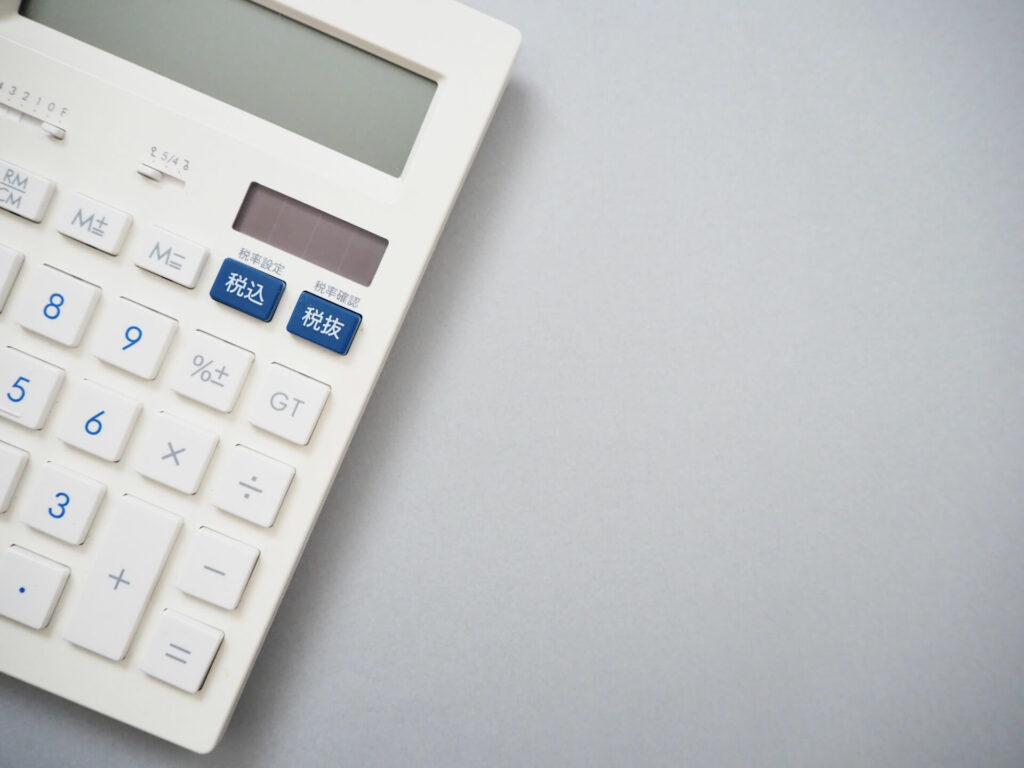
インスリン注射にかかる医療費は、使用しているインスリンの種類や、注射量により個人差があります。
また、インスリン注射を行う場合、同時に血糖測定も始まるため、それにかかる費用も上乗せになります。
在宅自己注射指導管理料や血糖自己測定指導加算も加わるのです。
インスリン注射と内服薬、血糖測定を行うと、月額の医療費は約3万6,000円。自己負担額(3割)は約1万1,000円。年間の自己負担は約13万2,000円と試算が出ています。
(参考:糖尿病ネットワークより)
インスリンの自己注射が始まることで、経済的な負担を感じる人もいるでしょう。
インスリン製剤の種類を単価が低いものに変更したり、内服薬をジェネリック医薬品に変えたり、経済的な負担を減らす方法もあります。
まずは、担当の医師に相談してみましょう。
インスリン製剤の種類と特徴

インスリン製剤は、以下の6つに分けられます。
- 超速効型インスリン製剤
- 速効型インスリン製剤
- 中間型インスリン製剤
- 混合型インスリン製剤
- 配合溶解インスリン製剤
- 持効型溶解インスリン製剤
インスリン製剤の注射タイミングや作用時間、特徴を以下の表にまとめました。
| 超速効型 | 速効型 | 中間型 | 混合型 | 配合溶解 | 持効型溶解 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射タイミング | 食直前 | 食前 | 朝食直前、又は朝食前30分以内 | 朝食直前、又は夕食直前30分以内 | 食直前1日1回、又は朝食直前と夕食直前の1日2回 | 食直前、又は就寝前 |
| 作用発現時間 | 10~20分 | 30分~1時間 | 30分~3時間 | 10分~1時間 | 10~20分 | 1~2時間 |
| 作用持続時間 | 3~5時間 | 5~8時間 | 18~24時間 | 18~24時間 | 42時間以内 | 24時間 |
| 特徴 | インスリン分泌を補う | インスリン分泌を補う | インスリンの基礎分泌を補う | インスリンの基礎分泌と追加分泌を補う | インスリンの基礎分泌と追加分泌を補う | インスリンの基礎分泌を補う |
(参考:サノフィ株式会社 患者向け糖尿病情報サイト、糖尿病リソースガイドより)
インスリン注射のトラブル対処法

インスリンの自己注射をしていると、焦る場面も出てくるでしょう。
そのような時に困らないよう、よくあるトラブルと対処法を紹介します。
インスリンを多く打ってしまった時

インスリンを多く打ってしまった場合、低血糖になる可能性があります。
「低血糖かも」と感じたら、すぐに対処しましょう。
- ブドウ糖10g
- 砂糖20g
- ブドウ糖を含む清涼飲料水150~200mL
- アメ玉、チョコレート
以上のようなものをすぐに摂取しましょう。
人工甘味料では血糖を上げることはでません。清涼飲料水を飲む際には注意が必要です。
インスリンを打ち忘れた時

インスリンを打ち忘れた場合、使用しているインスリンの種類や打ち忘れた経過時間、病状によって対応が異なります。
担当の医師に、打ち忘れた時の対応を確認しておきましょう。
また、忘れないようアラームをかけたり、目に付くところにインスリンを置いておくなど、工夫が必要です。
また、インスリン忘れ防止アプリや、市販のものでタイマー機能付き交換キャップなど、便利な物も売られています。
タイマー機能付き交換キャップは、前回投与からの経過時間が表示されているので分かりやすく、二度打ちや打ち忘れの防止に役立ちます。
対策をしても頻回に打ち忘れてしまう場合、担当の医師に相談してみましょう。
空打ちを忘れた時

空打ちは毎回必要な作業です。以下の4つの目的があります。
- 空気を抜く
- 針のつまりはないか
- 針は正しく装着されているか
- 注入器が正常に使えるか
空打ちをしないと、必要な量のインスリンが投与できない可能性があります。
空打ちを忘れて、インスリン注射をしてしまった場合、体調の変化がないか気を付けておきましょう。
空打ちを忘れてしまったときや、忘れたかもしれないときの、対処法と対策を担当の医師と話しておくと安心です。
Q&A

インスリン注射について、よくある質問をまとめました。
インスリンの空打ち単位数は?

インスリンやGLP-1受容体作動薬の自己注射の前には、「空打ち」という作業が必要です。
その空打ちに必要な単位数は、使用する製剤によって異なります。インスリン製剤の場合、基本的な空打ち単位数は2単位です。
しかし、空打ち単位数が、2単位ではないインスリン又はGLP-1受容体作動薬を以下の表で紹介します。
| インスリン製剤名 | 空打ちのタイミング | 空打ちに必要な量 |
|---|---|---|
| ランタスXR | 毎回 | 3単位 |
| ゾルトファイ | 毎回 | 2ドーズ |
| ビクトーザ | 毎回 | 空打ちメモリあり(0.12㎎) |
| バイエッタ | 新しいペンの使い始めに1回 | 1回分 |
| フォルテオ | 新しいペンの使い始めに1回 | 1回分 |
間違った使い方をすると、うまく空打ちができなかったり、予定よりも早く薬液がなくなったり、トラブルの原因になります。
空打ちのタイミングや量は製剤によって異なるため、使用する前にしっかり確認しておきましょう。
インスリン療法を始めるとやめられない?

1型糖尿病の場合は、インスリン療法をやめることができません。
体内でインスリンが分泌されていないので、インスリン療法は一生続けていきます。
2型糖尿病の場合は、状況に応じてインスリン療法をやめられる場合があります。
血糖のコントロールが良好な場合は、インスリン治療が不要になり、経口血糖降下薬へ戻すことも検討できるかもしれません。
ただし、自己判断でやめると危険なため、かならず担当の医師の指示にしたがいましょう。
インスリン注射は痛い?

インスリンの自己注射に使われる針は、とても細く短いため痛みを感じにくいです。
針先も、特殊なカットをされているため、痛みが少ないデザインに工夫されています。
病院で行う採血の針とは違いますので、安心してください。
インスリン療法を始めたら運動療法と食事療法はやめてもいい?

運動療法と食事療法は基本になるため、インスリン療法をしていても継続して行いましょう。
運動療法や食事療法をおろそかにすると、肥満が助長される可能性があります。
肥満が助長されると、インスリンの投与量が増える悪循環になります。
また、その他の生活習慣病の予防にも繋がるため、運動療法と食事療法は続けていきましょう。
病気になった時もインスリンを打つ?

糖尿病の方は、抵抗力が低下しているため、感染症にかかりやすいとされています。
インスリン治療をしている方が、感染症にかかり発熱や下痢、嘔吐、食欲不振などにより食事ができない状態になることを、「シックデイ」と言います。
普段は血糖コントロールが良好な方でも、高血糖になったり低血糖になったりし、危険な状態になりやすく注意が必要です。
担当の医師とシックデイの時の対応について話しておきましょう。
シックデイのときの対応方法を「シックデイルール」と言います。
このシックデイルールについては、家族や同居している人と共有しておくことが大切です。
自己判断で注射をやめたり、減らしたりすることはやめましょう。
シックデイで対応に困った場合、電話でかかりつけの病院へ相談したり、医療機関を受診してください。
インスリン注射を人に見られたくない時は?

人前で血糖を測定し、インスリンを打つことに抵抗がある人も多いですね。
しかし、インスリン治療をしている人は、外出していてもインスリンの注射をしなくてはいけません。
学校や会社の場合、保健室や医務室、空いている部屋などがあれば、そこでインスリンを打つことができます。
しかし、必ずしもそのような場所が確保できない場合、トイレの個室でインスリンを打つ人も多いです。
また、手技に慣れてくれば、テーブルの影で素早く打つことができる人もいます。
外出の際には、インスリンを打つスペースを確保できるのか確認しておくと安心です。
インスリン治療をしていても子どもを産める?

インスリン治療をしていても、出産は可能です。
ただし、妊娠前からの血糖が胎児に影響することが分かっていますので、妊娠前からの血糖コントロールが重要です。
そのため、「計画妊娠」が推奨されています。妊娠を希望した時点で、合併症の有無や程度の検査を行い、医師から妊娠しても大丈夫な状態か判断してもらいます。
糖尿病の合併症で網膜症と腎症がありますが、これらの合併症は妊娠によって悪化しやすいとされています。
妊娠前に検査をしておくことで、安心してお産を迎えられるでしょう。
また、普段は飲み薬でコントロールしている人も、妊娠を期に一時的にインスリン治療に切り替えます。
経口糖尿病薬は、胎盤を通して胎児へ運ばれるためです。インスリンは胎盤を通らないため胎児に影響はありません。
また、インスリン治療をしていても、合併症がなく血糖コントロールが良好な場合は、帝王切開とは限らず自然分娩をすることができます。
妊娠を希望している場合は、早めに担当の医師と話をしておきましょう。
まとめ
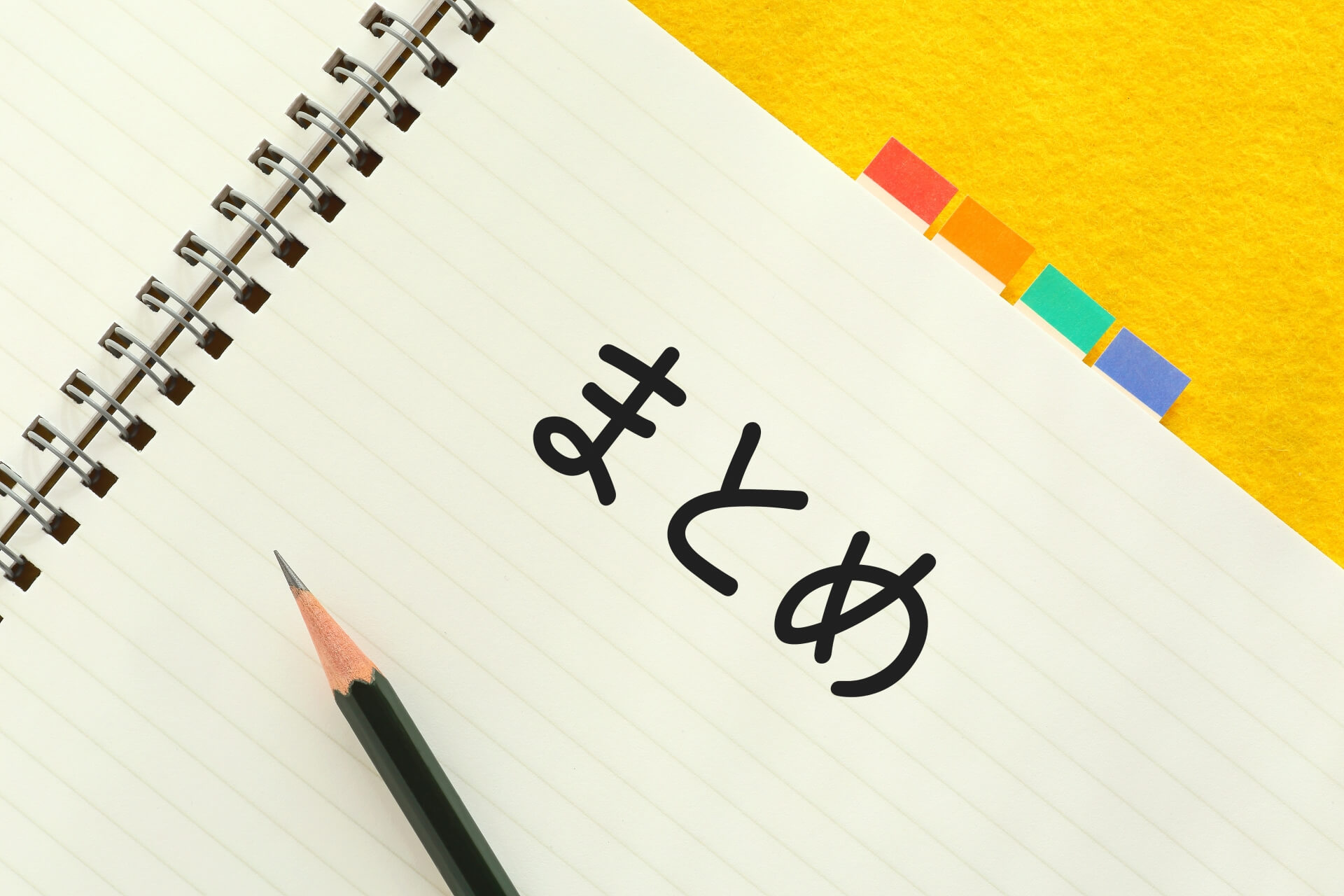
インスリンの投与量には「単位」というものが使われており、1単位が0.01mlです。
インスリン製剤の種類によっては、作用時間や特徴、使用方法が異なります。
また、カーボカウントやスライディングスケールなど、血糖値とインスリン投与の管理方法も知っておくと役に立つでしょう。
自分の使用しているインスリン製剤を理解することで、安全なインスリン使用と血糖コントロールに繋がります。
インスリン治療は、毎日のことであり、精神的にも身体的にも経済的にも、負担に感じる場合があるかもしれません。
インスリン治療が上手く自分のライフスタイルに取り入れることができるよう工夫も必要です。
困った場合は、些細なことでも担当の医師に相談してみましょう。
糖尿病の患者や医師、看護師、栄養士が集まったサークルに参加してみるのもいいかもしれません。
インスリン治療で、よりよい血糖コントロールを目指しましょう。