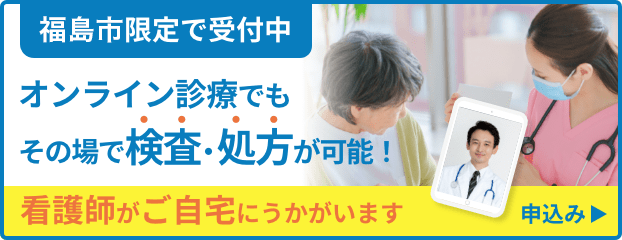糖尿病の食事療法のポイントは?良い食べ物・悪い食べ物について解説
「食事療法が必要だけど、何を食べたら良いのかわからない」「糖尿病に良い食べ物や、悪い食べ物を知りたい」という方もいるのではないでしょうか。
糖尿病は進行すると、さまざまな合併症を発症するおそれがあります。糖尿病の合併症は失明や透析の原因にもなり、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
糖尿病の進行を抑え、合併症を予防するためには、血糖コントロールが大切です。血糖コントロールで重要となるのが、糖尿病の治療法のひとつ「食事療法」です。
そこで今回は、糖尿病の食事で気をつけるポイントや、糖尿病に良い食べ物、糖尿病を悪化させる食べ物について解説します。
また、毎日の食事作りに役立つ献立アプリついても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

名倉 義人 医師
○経歴
・平成21年
名古屋市立大学医学部卒業後、研修先の春日井市民病院で救急医療に従事
・平成23年
東京女子医科大学病院 救急救命センターにて4年間勤務し専門医を取得
・平成27年
東戸塚記念病院で整形外科として勤務
・令和元年
新宿ホームクリニック開院
○資格
救急科専門医
○所属
日本救急医学会
日本整形外科学会
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
糖尿病の食事のポイント9つ

食事療法は、糖尿病の疑いがあると診断されたときから開始します。食習慣を改善し、血圧や体重、血糖値のコントロールが目的です。
糖尿病で血糖値の高い状態が続くと、全身の血管が傷付き、さまざまな合併症を引き起こします。進行すると命にかかわる合併症もあるため、予防のための食事療法は非常に重要です。
しかし、糖尿病だからといって、食べてはいけないものはありません。血糖値をコントロールするための食事のポイントは以下の9つです。
- 栄養バランスのとれた食事を摂取する
- 1日3回規則正しく食べる
- 適切エネルギー量を守る
- 1食あたりの脂質の適量を把握し、良質の油を摂取する
- 食物繊維は1日20gを目標に積極的に摂取する
- アルコールは控える
- 塩分を控える
- 間食は控える
- ゆっくり食べる
ただし、控えるべき食品や摂取量など、細かい食事のポイントは一人ひとりの身体の状態によって異なります。食事療法は、主治医の指示のもと適切に行うことが大切です。
栄養バランスのとれた食事を心がける

糖尿病の食事療法というと、「厳しい制限がある」というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。
糖質や脂質、塩分などを控える必要はありますが、ただ制限すればよいというものではありません。偏食をせず、色々な食品を組み合わせて必要な栄養素をバランス良く摂取をすることが重要です。
食品に含まれる栄養素は以下の5種類です。
- 炭水化物
- タンパク質
- 脂質
- ビタミン
- ミネラル
バランスの良い食事を適正なエネルギー量の範囲内で摂取するために参考になるのが、「糖尿病食事療法のための食品交換表」です。
食品交換表は、食品を栄養素によって6つのグループに分け、80kcalを1単位として、食品の重さを掲載しています。それぞれの食品のカロリーを覚えなくても、1単位の分量によってカロリーを把握できるため、カロリーの管理がしやすいです。
医師や栄養士による食事指導では、この食品交換表をもとに1日の単位と栄養素の振り分けを指示します。たとえば1日20 単位の指示が出たら、指示された栄養素の表の中から20単位分の食品を選んで摂取します。
適正カロリーを守りながら、栄養バランスのとれた食事の献立が手軽にできるように作られているため、非常に便利です。
規則正しい時間に食べる

食事の回数が少ないほど、食後の血糖値は高くなります。血糖値の上昇を避けるために、1日3食の食事時間をおおまかに決め、規則正しく食事をとりましょう。
食事の間隔を5〜6時間空けると、血糖値が安定し、インスリンを分泌する膵臓の負担が軽減します。食事の間隔が大きく空いてしまう場合は、膵臓の負担を軽減するために、補食で補うようにするとよいです。
朝食を食べなかったり、遅い時間帯に夕食をとったりすると、血糖コントロールが難しくなります。遅い時間の食事は肥満にもつながります。朝食を必ず食べ、夜遅くに食べないようにしましょう。
適正エネルギー量を守る

適正エネルギーを守れば肥満を改善でき、血糖値の上昇を抑えられます。適正エネルギーの範囲内で、朝・昼・晩と規則正しく食べ、間食は避けましょう。
仕事などで規則的な食事ができない場合、適正エネルギーの範囲内で間食として摂るなどの工夫をするとよいでしょう。
膵臓への負担を避けるためです。
適正エネルギー量は、年齢ごとの目標体重や、活動量などによって異なります。エネルギー摂取量は以下の計算式から算出できます。
| エネルギー摂取量(kcal)=目標体重(kg)×身体活動量 |
目標体重と身体活動量は以下を参考にしてください。
| 目標体重 ・65歳未満:身長(m)×身長(m)×22 ・65歳以上:身長(m)×身長(m)×22~25 身体活動量 ・軽い労作(大部分が座位の静的活動):25~30kcal/kg ・普通の労作(通勤・家事、軽い運動を含む):30~35kcal/kg ・重い労災(力仕事、活発な運動習慣):35kcal/kg〜 |
例えば、身長165㎝でデスクワークが多い方の場合
| ・目標体重:1.65(m)×1.65(m)×22=59.9(kg) ・身体活動量:軽い労作となるため、25~30 (kcal/kg) よって、1日に必要なエネルギー摂取量は 59.9(kg)×25〜30kcal/kg=1,498〜1,797kcalです。 |
年齢や性別、血糖コントロールの状況、合併症の有無などによっては、計算式に当てはまらない方もいます。実際の適正エネルギー量については、主治医に相談しましょう。
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
脂質を控える

脂質の多い食事は脂質異常症を引き起こし、動脈硬化の原因になります。動脈硬化は、糖尿病合併症の発症リスクを高めるため、注意が必要です。
1日あたりの脂質は摂取エネルギーの20〜30%を目標とします。さらに、脂質異常症の重症化予防を目的に、コレステロールを200mg/日未満に留めることが望ましいとされています。
また、脂質異常症を予防するためには、飽和脂肪酸の多い食品を控え、不飽和脂肪酸の多い食品へ置き換えが必要です。不飽和脂肪酸は、糖尿病の死亡リスクを低下させるという研究結果もあります。
脂身の多い肉など、飽和脂肪酸を多く含む食品を控え、脂質異常症を予防します。飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸の働きは以下の通りです。
- 飽和脂肪酸:血液中の悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を上昇させる
- 不飽和脂肪酸:悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を下げる
飽和脂肪酸が多く含まれる食品と不飽和脂肪酸が多く含まれる食品は以下の通りです。
| 飽和脂肪酸 | 肉、乳製品(牛乳、バター)、卵黄、チョコレート、ココナッツ、パーム油など |
| 不飽和脂肪酸 | 魚油(青魚)、植物油(トウモロコシ油・大豆油・サラダ油等)、クルミ、えごまなど |
食物繊維を積極的に摂取する

糖尿病を改善し、合併症を予防するために、食物繊維の積極的な摂取が勧められています。
食物繊維には、以下の働きがあります。
- 消化・吸収を緩やかにし、血糖値の上昇を抑える
- 満腹感が得られ、食べ過ぎを抑える
一日あたり24g以上の食物繊維を摂取することで、2型糖尿病をはじめ、脳卒中や心筋梗塞、大腸がんなどの発症リスクを低下させるという研究報告もあります。
食物繊維の 1 日平均摂取量は 20gを越えた時点から、これらのリスクの低下傾向が認められています。
そのため、「糖尿病診療ガイドライン 2019」では、糖尿病における食物繊維の目標量を1日あたり20g以上とすることを推奨しています。
食物繊維は魚や肉などの動物性食品にはほとんど含まれておらず、植物性食品に多く含まれます。食物繊維を多く含む食品は、以下の通りです。
- そば
- ライ麦パン
- しらたき
- さつまいも
- 切り干し大根
- 野菜(かぼちゃ、ごぼう、たけのこ、ブロッコリー、モロヘイヤ、いんげん、おから、しいたけなど)
これらの食品には、食物繊維が1食あたり2〜3gも含まれています。毎日の食事の中に上手に取り入れ、効率的に食物繊維を摂取しましょう。
塩分を控える

高血圧を予防するために、塩分の摂りすぎに注意が必要です。高血圧は動脈硬化の原因になり、糖尿病の合併症が進行しやすくなります。
塩分を控えるためには、素材の味を活かした味付けにしたり、減塩調味料を使用したり、酸味を活用するなど、毎日の食事に工夫が必要です。
「糖尿病診療ガイドライン 2019」では「現時点では、糖尿病患者の食塩摂取量について、 特別な推奨基準を設定するまでの根拠にはいたっていないと考えられる」と示しています。
そのため、糖尿病においても「日本人の食事摂取基準」の食塩摂取量が目標です。また、高血圧がある方、顕性腎症がある方は日本高血圧学会が示している塩分摂取量を目標にします。
食塩摂取目標量は以下の通りです。
- 男性 7.5g/日未満
- 女性 6.5g/日未満
高血圧がある方、顕性腎症がある方
- 6.0g/日未満
間食を控える

血糖コントロールのためには、間食はできるだけ控えたほうがよいです。食事の間隔が短いと、血糖値が下がらないうちにまた間食をすることになるため、食後の血糖値がさらに高くなります。
どうしても食べたいときだけ、1日1回、昼食と夕食の間(午後3時頃)に取り入れましょう。
1日の適正エネルギー量の範囲内で、糖質の多いスナック類や清涼飲料水は避け、果物やヨーグルトを適量とるとよいです。
最近では、糖尿病の患者さん向けのカロリーコントロール食品や、血糖値の上昇を抑える機能性表示食品なども販売されています。
管理がしやすいように、1食で1単位(80kcal)に調整されてるものもあり、摂取量が把握しやすいのも嬉しいポイントです。どうしても間食が必要な場合は、これらの食品を上手に活用し、血糖コントロールを行うとよいでしょう。
アルコールを控える

アルコールを摂取すると、塩気の強い食べ物や脂の多い食べ物が欲しくなります。お酒がすすむとだらだらとたべてしまい、食事摂取量も多くなりがちです。
アルコールは肝臓に脂肪がたまる原因にもなります。また、インスリン抵抗性を引き起こし、食後の血糖値が下がらず、合併症のリスクも高まります。
アルコールは控え、できるだけ節酒を心がけましょう。
時間をかけてゆっくり食べる

時間をかけずに急いで食べると、急激に血糖値が上昇し、血糖コントロールが難しくなります。
ゆっくりと時間をかけて食べ、血糖値の急上昇を抑えることが大切です。また、ゆっくりよく噛むと満腹感が得られるため、食べ過ぎを抑えて肥満を予防できるというメリットもあります。
ほかにも、唾液の分泌が促進され、消化・吸収機能が向上し、胃腸への負担が軽減されたり、糖尿病の方の口渇感を和らげたりする効果もあります。
糖尿病に良い食べ物

糖尿病は、血糖値を下げる「インスリン」というホルモンが不足したり、十分に働かなかったりして、血糖値が高い状態が慢性的に持続する疾患です。
糖尿病に良い食べ物は、血糖値の上昇を抑え、エネルギーのコントロールに適した食材です。具体的にどのような食べ物が糖尿病に良いのか、みていきましょう。
水溶性食物繊維が豊富な食べ物

食物繊維は血糖値の上昇を抑える働きだけでなく、満腹感が得られ、食べ過ぎ防止にも良いです。低脂肪で肥満の予防にも効果的です。食物繊維の中でも「水溶性食物繊維」は、食後の血糖値や、血中の中性脂肪の上昇をおだやかにする働きがあります。
水溶性食物繊維を含む食べ物は以下の通りです。
- 大麦
- オートミール
- 納豆
- 野菜
- きのこ
ビタミン・ミネラルを含む食べ物

ビタミン・ミネラルは、身体の機能を正常に維持するために必要な栄養素です。体内で合成できないため、毎日の食事から摂取する必要があります。ビタミン・ミネラルを含む食べ物は以下の通りです。
水溶性ビタミン
水溶性ビタミンは、体内のさまざまな代謝に必要な酵素の働きを補う栄養素です。血液などに溶け込み、余分なものは尿として排泄されます。そのため、体内の量が多くなり過ぎることはあまりないと考えられています。
水溶性ビタミンは、以下の種類に分けられます。
- ビタミンB群(B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)
- ビタミンC
水溶性ビタミンは以下の食品に多く含まれています。
- 肉
- 魚
- 野菜
- 果物
- 卵
- 豆類
水に溶ける性質があるため、野菜や果物は調理せずに食べるか、スープで食べるのがおすすめです
脂溶性ビタミン
脂溶性ビタミンは脂溶性のため、水に溶けません。主に脂肪や肝臓に貯蔵されます。身体の機能を正常に維持する働きをしていますが、多く摂りすぎると過剰症を起こす場合があるため、摂取量には注意が必要です。
脂溶性ビタミンは、以下の種類に分けられます。
- ビタミンA
- ビタミンD
- ビタミンE
- ビタミンK
大豆や海藻、うなぎ、レバー、緑黄色野菜などに多く含まれています。油で調理すると吸収率が良くなるため、炒め物や揚げ物で食べるのがおすすめです。
ミネラル
ミネラルとは、生体を構成する主要な4つの元素(酸素、炭素、水素、窒素)以外のものの総称です。無機質ともいわれる栄養素で、代表的なものはカルシウム、リン、カリウムです。
ミネラルはインスリンの糖代謝作用を助け、血糖値を下げるサポートをします。体内で合成できないため、食事からの摂取が必要です。
ミネラルが不足すると、貧血や骨粗しょう症、味覚障害などのさまざまな不調を引き起こします。反対にとりすぎた場合も、過剰症や中毒を起こすため、適正量を守って摂取することが大切です。
ミネラルは互いの働きや吸収に影響をあたえるため、バランスよく摂取しましょう。ミネラルの種類と、多く含む食品は以下の通りです。
| 種類 | 多く含む食品 |
|---|---|
| ナトリウム | 食塩、みそ、しょうゆ |
| 塩素 | 食塩、みそ、しょうゆ |
| カリウム | 野菜類、果物類、いも類 |
| カルシウム | 牛乳・乳製品、野菜、小魚、海藻、大豆製品 |
| マグネシウム | 多くの食品に含まれるが、特に緑黄色野菜や海藻類などの植物性食品 |
| リン | 多くの食品に含まれるが、特に食品添加物など |
| イオウ | たんぱく質を含む食品に多く含まれる |
| 鉄 | 緑黄色野菜、レバー、卵黄、貝類、ひじき |
| 亜鉛 | 肉類、小麦胚芽、かき |
| 銅 | 野菜、肉類、穀物(特にピーナッツ) |
| マンガン | 野菜、穀類、種実、抹茶 |
| コバルト | 肉類、葉菜類 |
| クロム | 食品中に広く含まれるが、特に野菜、肉、魚、穀物 |
| ヨウ素 | 海藻、貝類 |
| モリブデン | 乳製品、レバー、豆類、穀類 |
| セレン | 魚肉、鶏肉、小麦、大豆 |
糖尿病で腎機能が低下している方では、カリウムとリンの摂取に制限がある場合があります。適正量については、主治医や管理栄養士とよく相談しましょう。
糖尿病を悪化させる食べ物

糖尿病を悪化させないためには、血糖値を上げやすい食品のとり過ぎに注意が必要です。糖質が多い食品、とくに甘いものを食べると血糖値が急激に上昇します。
たとえば、パンやごはん、麺類、ケーキやせんべいなどの菓子類です。これらを食べ過ぎると、急激な血糖値の上昇を招くため注意しましょう。
血糖を上げやすい食べ物は以下の通りです。
- ご飯
- パン
- 麺類(うどん・そば・ラーメン・パスタなど)
- とうもろこし
- いも類(じゃがいも・サツマイモなど)
- かぼちゃ
- 菓子類
ただし、糖尿病の食事療法では、絶対に食べてはいけない食べ物はありません。血糖値が上がりやすい食品をとり過ぎないようにすることが大切です。適正カロリーを守り、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。
食事療法に役立つ献立アプリの活用

食事療法を行う患者や家族にとって、毎日の献立を考えるのは特に大きな負担です。「どんな物を作ったら良いのかわからない」とお悩みの方は少なくありません。
近年、食事療法の負担を軽減するために、食事管理を助けてくれるアプリが複数登場しています。
栄養のプロである管理栄養士監修の献立や、糖尿病の診療ガイドラインの食事基準に基づいた献立などが掲載されているものもあります。
献立だけでなく、適切な栄養管理を誰でも手軽に実践できるような、さまざまな機能が付いており非常に便利です。
ここでは、食事管理アプリの主な機能をご紹介します。
カロリー計算

食事療法では、適正カロリーを守るのが重要です。食事管理アプリでは、面倒なカロリーや栄養素の計算を自動で行う機能がついているものもあり、非常に便利です。
カロリーや栄養素の計算は難しく、患者さんや家族にとって負担になります。アプリを活用することで、専門的な知識がなくても、誰でも簡単に摂取カロリーや栄養を把握できます。
糖尿病に良いおかずレシピ

食事療法は、継続することで効果が現れます。食事療法の大切さをわかっていても、糖尿病に良いおかずを毎食、何品も考えるのは大きな負担です。
食事管理アプリでは、糖尿病に良いおかずのレシピも豊富です。和食や洋食、中華など、その日の気分に合ったおかずのレシピを検索できます。
また、血糖値をはじめ血圧や内臓脂肪、中性脂肪など、お悩み別で検索できるものもあり、身体の状態に合わせてレシピを見つけられるため非常に便利です。
健康管理アプリを活用することで、健康状態や好みに合わせたレシピを検索でき、楽しく食事療法を続けられるでしょう。
糖尿病の1週間の食事メニュー

糖尿病の方向けの食事管理アプリでは、1週間の献立を作ってくれるものもあります。1週間を通して献立が考えられているため、バランスの良いメニューで食事管理を行えるのがメリットです。
毎日献立を考える手間が省け、食事管理の負担を大幅に低減できます。また、メニューに必要な材料をまとめた材料リストも掲載されており、買い物の際に非常に役立ちます。
食事療法の悩みや工夫を共有

患者や家族が実際に作ったレシピを投稿できるアプリもあります。食生活の悩みや、実際に行なっている工夫などを共有できます。
同じ悩みを抱える方と支援し合えるため、前向きに食事療法に取り組むきっかけ作りにもなるでしょう。
Q&A

糖尿病の食事療法について、よくある質問にお答えします。
糖尿病で食べてはいけないものは何ですか?

糖尿病の食事療法では、食べてはいけないものはありません。適正エネルギーの範囲内で栄養素バランスのとれた食事を摂取することが大切です。
糖尿病に良い食べ物は?

糖尿病は、血糖値を下げる「インスリン」というホルモンが、不足したり、十分に働かなかったりして、血糖値が高い状態が慢性的に持続する疾患です。
糖尿病に良い食べ物は、血糖値の上昇を抑える食べ物や、エネルギーのコントロールに適した食べ物です。
食物繊維の中でも「水溶性食物繊維」は、血糖値を下げ、中性脂肪の上昇を穏やかにします。
水溶性食物繊維を含む食べ物は以下の通りです。
- 大麦
- 納豆
- 野菜
- オートミール
糖尿病に一番良い飲み物は何ですか?

糖尿病に良い飲み物は、糖質が少なく、血糖値の上昇を抑える飲み物です。甘いジュースや砂糖の入ったコーヒー・紅茶などは、血糖値を急激に上昇させるため注意が必要です。
血糖値の上昇を抑える飲み物を3つ紹介します。
- 牛乳
牛乳に含まれるホエイプロテインは、インスリンの働きをサポートする働きがあります。また、血糖値の急上昇を抑える効果も報告されています。朝食時にコップ半分(100ml)を目安に牛乳を飲む習慣をつけると良いでしょう。
- 緑茶
緑茶に豊富に含まれるカテキンには、糖の吸収を抑える働きがあります。1日6杯飲む方は、週1杯以下しか飲まない方よりも糖尿病になりにくいという報告もされています。
食前に緑茶を飲むのを習慣にして、血糖値の上昇を防ぎましょう。
- コーヒー
コーヒーに含まれるカフェインは、血糖値の急上昇を抑える働きがあります。砂糖を入れてしまうと、血糖値が上がりやすくなるため、無糖のコーヒーを選ぶようにしましょう。
血糖値を下げるには何を食べたらいいですか?

血糖値を下げるには、血糖の吸収が緩やかな食べ物を選ぶと良いでしょう。食物繊維の中でも「水溶性食物繊維」は、糖質の吸収を遅らせ、血糖値の上昇を抑える働きがあります。
水溶性食物繊維は、大麦や納豆、野菜、きのこなどに含まれています。食物繊維の1日の摂取目安は、20〜25gです。
血糖値を下げるには、食生活を見直すことが大切です。偏食せずに、色々な食材をバランスよく食べましょう。
まとめ
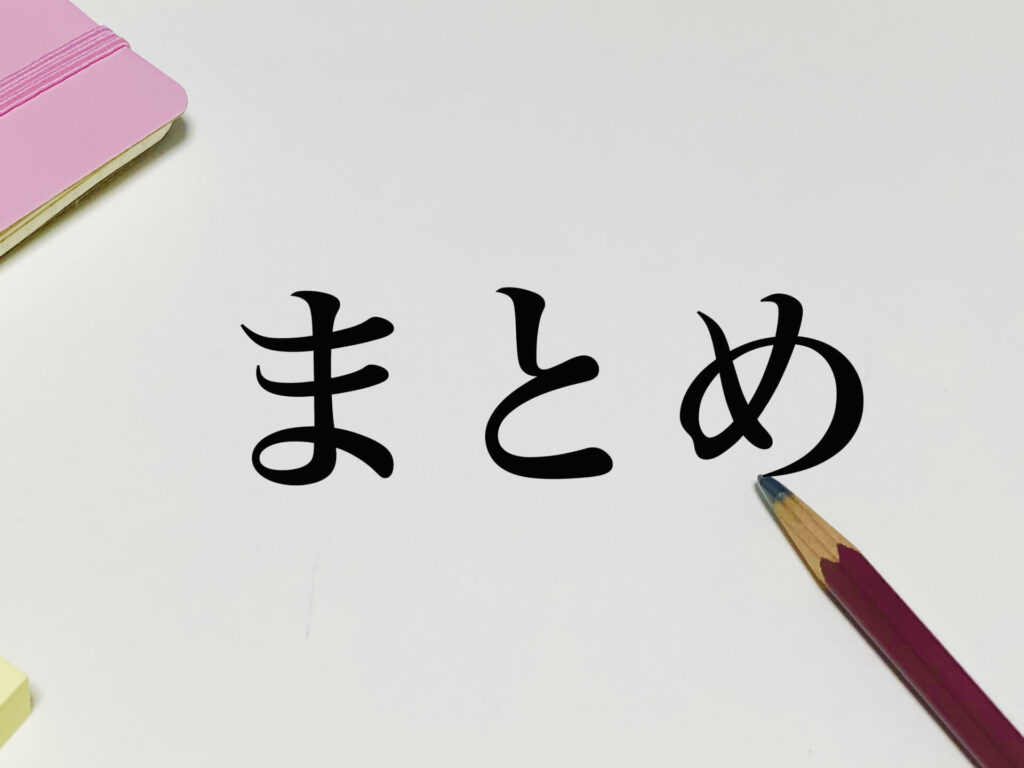
糖尿病の食事療法の目的は、血糖値をコントロールして糖尿病の進行を抑え、合併症の発症を予防することです。
一般的に厳しいイメージのある食事療法ですが、特別な食事を用意する必要はありません。極端な食事制限は、かえって糖尿病の進行を悪化させる可能性もあります。
適正なエネルギーの範囲内で、栄養バランスのとれた食事をするのが重要です。毎日の食事管理に便利な食品交換表やアプリなどを活用し、負担を軽減しながら上手に食事療法を行うと良いです。
糖尿病の状態によって、適正なエネルギーや食事制限の内容が異なります。食事療法は、必ず主治医の指示のもと行いましょう。