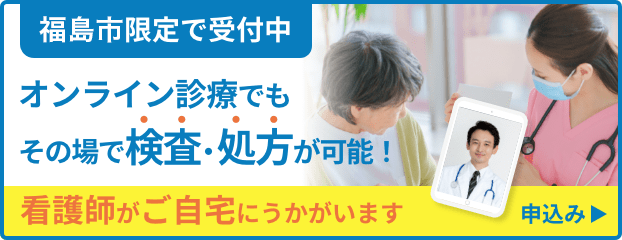糖尿病の人におすすめの血糖値の上がりにくい朝食メニューは?食事療法中でも満足できる朝ごはんをご紹介!
血糖値を上げないためには糖質を制限することが必要ですが、それは単に食事を減らせば良いわけではありません。バランスの悪い食事は逆に糖尿病の進行を早めてしまいますよ。
糖質制限食と聞くとお腹いっぱい食べられないのでは?と思う方もいるでしょう。
実は糖質制限食とカロリー制限は別なので、糖質以外のタンパク質や脂質の量を減らす必要はなく、比較的満足感は得られやすいんです。
この記事では、糖尿病と朝ごはんの関係や簡単で栄養豊富な朝ごはんのメニューをご紹介します。
糖尿病の食事療法中の方で、食事のメニューに困っている方はぜひご参考にしてください。

名倉 義人 医師
○経歴
・平成21年
名古屋市立大学医学部卒業後、研修先の春日井市民病院で救急医療に従事
・平成23年
東京女子医科大学病院 救急救命センターにて4年間勤務し専門医を取得
・平成27年
東戸塚記念病院で整形外科として勤務
・令和元年
新宿ホームクリニック開院
○資格
救急科専門医
○所属
日本救急医学会
日本整形外科学会
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
糖尿病と朝ごはんの関係を解説!

糖尿病の治療目標のひとつとして、血糖値の急激な変動を抑え、膵臓の機能を維持することがあります。インスリンは膵臓でしか作られないので、膵臓の機能を維持することは重要なのです。
ここでは、朝ごはんを抜くと膵臓にどのように負担がかかるのか解説します。
糖尿病で朝ごはんを食べないとどうなる?
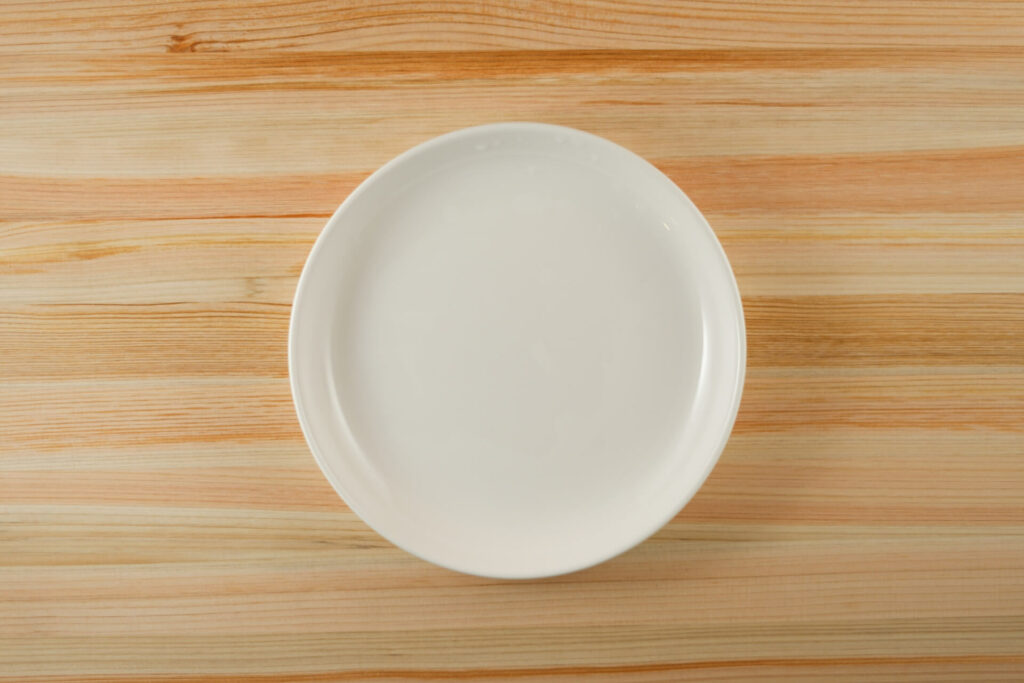
摂取カロリーを減らすために朝食を抜く方がいらっしゃいますが、これは間違いです。
長時間空けた後の食事で身体は糖分をしっかりと吸収しようとするため、昼食後に血糖値が急上昇してしまいます。
急激に上がった血糖値を下げようとして身体はインスリンを大量に分泌します。すると、肝臓には大きな負担がかかってしまうのです。
また、朝食を抜くと身体は糖分が不足するため、なるべく血糖値を下げまいとインスリンに対抗するインスリン拮抗ホルモンが働きます。
昼食を摂取した際に大量のインスリンが分泌されますが、インスリン拮抗ホルモンが働いているせいで、普段の身体と比較してさらにインスリンの効果が効きにくい身体になってしまっているのです。
これにより身体はさらに多くのインスリンを分泌しようと働くので、負のスパイラルに陥っていきます。
糖尿病の人が朝ごはんを食べるメリット

糖尿病の方が朝ごはんを食べるメリットの1つ目は昼食後の血糖値の急上昇を防ぐことができることですが、
実はもう1つ大きなメリットがあります。
それが「セカンドミール効果」です。
セカンドミール効果とは、1日の最初に摂った食事が次に摂った食事の後の血糖値にも影響することです。
つまり、朝食を低GI食品や食物繊維が多く含まれた献立にすると、昼食後の血糖値の上昇もコントロールできるということになります。
昼食は会社の同僚とランチに出かけたり、外で済ませたりする人も多いのではないでしょうか。
昼食に糖質が多い食事を摂ってしまったとしても、朝食さえ気をつけていれば血糖値の急上昇を防ぐことができるのです。
糖尿病でお困りの方は、ファストドクターのオンライン診療を頼ってください。
[糖尿病]は
ご自宅での診察(オンライン診療)
もご相談可能です
糖尿病の人が朝ごはんの食べ方で注意すること

糖尿病の方は糖質の量に注意する必要がありますが、血糖値を上げることのないタンパク質や脂質は健康な人と同じ量を摂取することができます。
糖尿病の人が朝ごはんの食べ方で注意することは以下の3つです。
①糖質の量は一食あたり40〜50gにすること
②はじめに食物繊維の多い食材やタンパク質を食べること
③午前8時半までに朝食を摂取すること
この3つのポイントについて、詳しく解説します。
①糖質の量は一食あたり40〜50gにすること
糖尿病を患っていない、健康な人の1日の糖質摂取量は約250〜300gです。
糖尿病の方はこの半量が目安となりますので、一食あたりの糖質摂取量は40〜50gです。
ご飯80gには約32g、6枚切り食パン1枚には約30g、ゆでうどん1玉には約48gの糖質が含まれます。
主食に比べて副菜の糖質量は少ないとは言え、0になることは不可能ですので主食はこのくらいの量にとどめておくのがベストです。
②はじめに食物繊維の多い食材やタンパク質を食べること
忙しいと、どうしても1品料理になりがちですが、ゆで卵や野菜、みそ汁などおかずも一緒に食べるように意識すると良いです。
タンパク質や、インスリンの効果を上げるサポートをしてくれます。また、食物繊維は小腸で糖の吸収スピードを緩やかにする働きがあります。
1日のスタートとなる朝食は、バランスも考えながらしっかり食べるよう心がけましょう。
③午前8時半までに朝食を摂取すること
米国内分泌学会が、朝食を早い時間に食べる人は血糖値が低く、インスリンへの抵抗性も低いという研究結果を発表しました。
一般的にエネルギー代謝やホルモンの分泌などは午前の早い時間には良好で、午後になって時間の経過とともに低下してきます。つまり、朝食を摂る時間はなるべく早いほうが代謝効率が良いのです。
代謝効率が良いということは最小限のインスリンで血糖値を下げることができるので、肝臓への負担が小さくなります。
食べ方だけでなく、食べる時間も意識することが大切なのです。
糖尿病の人は朝ごはんにフルーツを食べてもいい?
日本糖尿病学会は、1日に80kcal分のフルーツを摂取するよう推奨しています。
フルーツは、ビタミンCやカリウム、食物繊維の含有量が高く、制限された食事の中で必要な栄養素を効率よく摂れる食品です。
しかしフルーツには糖質も多く含まれているため、摂取量には注意が必要とされています。
おすすめのフルーツは、ブルーベリー、ブドウ、リンゴです。
ブルーベリーは1粒1kcalなので、ブルーベリーだけ食べるのであれば最大80粒摂取することができます。
食後のデザートとして、3食に分けて食べるのも良いですね。
ブドウは10〜15粒程度、りんごは1/2個程度が好ましいです。
その他比較的糖質の少ないフルーツは、いちご、グレープフルーツ、プラム、ラズベリー、ブラックベリー、桃、レモン、梨が例として挙げられます。
摂取量に注意して、多くの種類のフルーツを組み合わせて食べるとより多くの栄養素が摂取できます。
また食べ方にもポイントがあります。皮や切れ端なども含めて、丸ごと食べることがおすすめです。
これは皮や切れ端に、ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素が多く含まれているためです。
フルーツジュースは100%ジュースだとしても、加工の過程で熱を加えることで栄養素が失われていたり、砂糖を入れられたりしているので、飲むのはおすすめできません。
低血糖になりやすい人の朝ごはんのおすすめはこれ!

糖尿病を患っていない人でも、寝起きは血糖値が低い状態になっています。
これは夕食から朝食までは時間がかなり空くため、身体がエネルギー不足となっているからなのです。
しかし、ここで甘いものを食べて糖分を補おうとするのは間違いです。
前述した通り、血糖値が急激に上昇すると身体は血糖値を必死に下げようとします。
すると、肝臓に負担がかかってしまいます。
つまり、朝ごはんで摂取するべきなのは、緩やかに血糖値を上昇させてくれる食品なのです。
これは低GI食品と呼ばれます。GIとは食後血糖値の上昇度を示す指標のことです。
代表的な例をあげると大豆食品、さつまいも、きのこ、そばなどがあげられます。
これらを朝食に取り入れると、血糖値の急激な上昇を抑えることができ、肝臓への負担を抑えられます。
そのほか、食事に関する注意点は以下の4つです。
①きのこ類、海藻、野菜、タンパク質を炭水化物の前に摂取しましょう。
きのこ類、海藻、野菜などの食物繊維はブドウ糖の吸収を緩やかにしてくれます。
また、タンパク質は消化に時間がかかるため、血糖値の上昇が緩やかです。
②食間を長くしないようにしましょう。間食には、豆乳、ナッツ類、小魚がおすすめです。
③よく噛んで食べましょう。よく噛むことで、消化液の分泌が促され、ブドウ糖の急激な吸収を抑えることができます。
④天然の調味料(粗製糖、粗製塩、昆布、煮干し)などを使い、血糖値を上げやすい人工甘味料、香料、色素、化学調味料は避けるようにしましょう。
糖尿病の人の朝ごはんの簡単メニューを紹介!
血糖値を上げない食事メニューはこれ!

朝ごはんでは、セカンドミール効果を得やすい食事を取ると良いとされています。
セカンドミール効果の得やすい食事のポイントは、食物繊維が多く含まれる低GI食品であることです。
以下でご紹介する食品はセカンドミール効果を得やすいものです。
普段は白米を食べている方は玄米に、普通の食パンを食べている方は全粒粉の食パンにするだけでも効果がありますので、試してみてください。
【主食】玄米、雑穀ごはん、全粒粉のパン、蕎麦、玄米ブランやグラノーラ、オートミール
【主菜】魚、鶏肉、鶏卵、低脂肪の乳製品やチーズ、納豆、豆腐、牛乳
【副菜】玉ねぎ、トマト、オクラ、わかめやのりなどの海藻類
【その他】ナッツ、無糖ヨーグルト、アマニオイル、エゴマオイル
糖尿病の人の朝ごはんにシリアルはおすすめ!

玄米ブランやグラノーラは、食物繊維が多く含まれたシリアルのひとつです。
シリアルは手軽で栄養価も高いので、糖尿病の方の朝食には最適なのですが、商品の選び方が大切です。
スーパーで売られているシリアルの多くは砂糖を多く含み、甘くなっています。
糖尿病の方がシリアルを選ぶ時には、ブランを材料にできているものがおすすめです。
ブランは小麦ふすまとも呼ばれ、小麦の外皮部分のことで、食物繊維がたくさん含まれています。
その他にも、糖質オフと書かれている商品や血糖値対策ができる商品も販売されているため、そのようなシリアルを選びましょう。
ブランのシリアルを食べるときには、キャベツやレタス、海藻の入ったサラダをプラスして食べるようにするとさらに食物繊維が増え、血糖値の急上昇を防ぐことができます。
また、シリアルには牛乳をかけて食べる方が多いと思いますが、牛乳に含まれるホエイプロテインにはインスリンの働きをサポートし、血糖値の上昇を抑える効果があります。
牛乳を飲む習慣のない方も、朝ごはんをシリアルにすると必然的に牛乳を摂取することになるので、一石二鳥です。
糖尿病の人の朝ごはんにオートミールはおすすめ!

あらゆる穀物をベースに作られたシリアルとは違い、オートミールはオーツ麦のみを食べやすく加工したものです。
オートミールは低カロリー、低糖質に加えて食物繊維が豊富に含まれているためGI値が低く、血糖値の上昇を抑えるのに効果が大きい食品と言われています。
前述しましたが、GI値はどれくらいの速度で血糖値が上がるのかを数値化したものです。
低血糖のときに摂るブドウ糖を基準値の100としており、この数値に近いほど血糖値の上がる速度は速く、低い数値ほどその速度は遅いので、GI値が低い食品を選ぶと血糖値の急上昇を防ぐことができるのです。
比較すると、オートミールのGI値は55、白米のGI値が76なので白米よりも膵臓への負担が小さいことがわかります。
オートミールの選び方
一般的によく出回っているオートミールは、ロールドオーツ、インスタントオーツ、クイックオーツの3種類です。
この中で、白米の代わりにオートミールを食べる方へおすすめするのは、ロールドオーツです。
ロールドオーツは、オートミールを蒸した後にプレスして作られるもので、粒がしっかりとしているので食べ応えや食感を楽しむことができます。
プチプチ、モチモチとした食感で、お腹も心も満足しやすいですよ。
少しの水を加えるとご飯のような状態になるので、白米の代わりには最適です。
しかしオートミールの独特の匂いを感じやすいので、味をつけて料理に使うのがおすすめです。
以下では、オートミールを使った簡単レシピをご紹介します。
オートミールはまずくて苦手だと思っている方、ぜひ試してみてください。
オートミールで作る納豆チャーハン
こちらは、調味料なしで作ることができるチャーハンです。
納豆の効果については後述しますが、オートミール×納豆は糖尿病の方の朝ご飯に最適な組み合わせなのです。
とても簡単なので、ぜひ作ってみてください。
【材料】
- オートミール30g
- キムチ
- 納豆1パック
- 卵1個
- のり、ごま
【作り方】
- オートミールは深めのボウルに入れて、水をひたひたまで注ぎ、600Wのレンジで1分〜1分半ほど加熱する。
- フライパンを熱し、ごま油を入れ、キムチを少々炒める。
- 2に1を入れて水分を飛ばしながら炒める。
- 3に卵を入れて火を通し、最後に納豆を入れて軽く炒める。
- お好みでのりやごまを散らす。
オートミールで作るお好み焼き
ソースやは一般的に糖質量が高い調味料とされていますが、お好み焼きにソースは欠かせませんね。
糖質オフの商品が売られているためそちらを選び、使用は少量にしましょう。
また、マヨネーズは比較的糖質が低い調味料ですが、使用は最小限にできると良いです。
お好み焼きはキャベツもたくさん食べられるので、一食で多くの食物繊維が摂れます。
【材料】
- オートミール30g
- 卵1個
- キャベツ2枚
- 豚肉50g
- だしの素
- お好みソース(大さじ1)
- マヨネーズ
- 青のり
【作り方】
- 深めのボウルにオートミールとオートミールが浸るくらいの水を入れ、600Wのレンジで1分半加熱する。
- キャベツは細切りにする。
- 1の粗熱が取れたら、卵・キャベツ・だしの素を入れて菜箸で混ぜる。
- フライパンを熱し、油を入れる。
- 4に3を入れ、豚肉を広げるように乗せたら、蓋をしてじっくり焼く。
- 焼けてきたら、表裏を返し、蓋なしのままもう5分焼く。
- お皿に盛り、少量のソース・マヨネーズ・青のりをかける。
糖尿病の人の朝食にスープは良い!

朝は忙しくて、ゆっくり朝食を食べる時間もない方におすすめなのが、マグカップスープです。
特に血糖値の急上昇を抑える効果がある野菜は玉ねぎ、トマト、オクラの3つなので、毎朝いずれかを摂取できると好ましいです。
また、野菜以外にもタンパク質や海藻を入れると満足感も高まります。作り方はとても簡単で、3分で完成します。
【材料】
- 減塩表示のあるインスタントみそ汁
- 玉ねぎ
- トマト
- オクラ
- 木綿豆腐
- もずくやわかめなどの海藻類
【作り方】
- 豆腐をサイの目に切り、マグカップに入れる。
- お好みの野菜や海藻類を加える。
- ラップをして600Wの電子レンジで2分加熱する。
- 3にインスタントみそ汁を加え、お湯を注ぐ。
糖尿病の人が朝ごはんをコンビニで済ませるときに購入すべきものはこれ!

朝ごはんを食べずに家を出てしまったときには、コンビニが頼りになりますね。
コンビニで朝ごはんを済ませるときには、以下の組み合わせで購入すると血糖値が上がりにくいです。
- おにぎり+ゆで卵+野菜サラダ
- 野菜サンドイッチ+牛乳やヨーグルト
ポイントはタンパク質と食物繊維を摂り、主食1品にならないようにすることです。
食前の血糖値は正常で、食後の短時間だけ血糖値が急上昇することを血糖値スパイクと言いますが、おにぎり単品といった糖質がメインの食事をすると、この現象が起こりやすくなります。
糖尿病の方は食前の血糖値も高い状態にあるため、糖質単品の食事をすることで血糖値が高いところからさらに急上昇してしますので、十分注意が必要です。
サンドイッチはパンと具材がセットなので栄養素が偏りにくそうですが、具材の味付けが濃く糖質量も高くなっています。
カツサンドや照り焼きチキンサンド、フルーツサンドなどは控えましょう。
ブロッコリー、えび、レタス、卵が入っているものがおすすめです。
前述しましたが、牛乳にも血糖値の上昇をコントロールする効果があるため、朝ごはんに追加できるとなお良いです。
糖尿病の人が朝ごはんとして食べられるおにぎりはあるのか?
タンパク質や野菜を追加すれば白米のおにぎりももちろん食べられますが、おすすめは玄米・雑穀米・もち麦を使用したおにぎりです。
これらには食物繊維が多く含まれるので、白米のおにぎりに比べて糖質量が少ないのです。
自宅で玄米を炊いている方はなかなかいないでしょうから、コンビニで食べるときには玄米を買うというルールを作っておくのもひとつの手だと言えるでしょう。
また、冷たいおにぎりもおすすめです。
コンビニのおにぎりは冷蔵保存されているので、この点で言えばどのおにぎりを選んでも大丈夫です。
冷たいおにぎりは温かいものに比べて、血糖値の上昇が穏やかになります。
これは、ご飯が冷める過程でレジスタントスターチという難消化性デンプンができるからです。
レジスタントスターチとは食物繊維と似たような働きを持つ成分で、血糖値の上昇を抑制したり、血中コレステロールの濃度を下げたりする働きがあります。
糖尿病の人が朝ごはんでご飯(白米)を食べるときはこうすると良い!

白米を食べる際は、納豆と組み合わせて食べると良いです。
納豆には、食物繊維とナットウキナーゼが豊富に含まれており、血糖値を下げたり、糖尿病の合併症を防いだりする効果があります。それぞれについて詳しく解説します。
【食物繊維】
何度も述べてきたように、食物繊維には血糖値の上昇を抑える効果があります。
血糖値の上昇が穏やかになると、膵臓も急いでインスリンを分泌する必要がなくなるため、膵臓の負担が小さくなるのです。
納豆には1パックあたり3.3gの食物繊維が含まれています。
日本人が1日あたりで摂取する食物繊維量の目標は、18-69歳の男性で21g以上、女性は18g以上です。
1食あたりに換算すると、男性は7g、女性は6gですので、納豆を1パック食べると必要量の半分は摂取できるのです。
【ナットウキナーゼ】
ナットウキナーゼは、納豆のネバネバ部分に含まれる酵素のことを言います。
酵素とは食べ物の消化や吸収、分解などに必要不可欠な物質です。
ナットウキナーゼには、血液中の血栓の元になるフィブリンという成分を分解する作用があります。
糖尿病は血糖値が高い状態が続く病気であるため、その状態が長く続くと血管は徐々に傷ついていきます。
傷がついたところに血液中の脂肪の塊が付着し、それが破裂したときに血管を塞ぐ血栓ができてしまうのです。
血管が塞がれることで、脳梗塞や心筋梗塞などの発症リスクが一気に高まります。
ナットウキナーゼは血栓融解酵素であり、血糖値に直接作用するわけではありませんが、糖尿病の合併症を予防することに効果がある酵素です。
糖尿病の人が朝ごはんで納豆を食べるときの注意点
血液をサラサラにする作用があるワルファリンを内服している場合は、納豆を摂取することは控えてください。
血液が固まるためには、ビタミンKが必要なのですが、ワルファリンはそのビタミンKの働きを妨げ、血液を固まりにくくさせる薬です。
納豆にはビタミンKが含まれているため、ワルファリンの作用を弱めてしまうのです。
糖尿病の人が朝ごはんでパンを食べるときはこうすると良い!

糖尿病の方が、朝ごはんにパンを食べる時には胚芽やライ麦入りのものを選びましょう。
胚芽やライ麦が入っていることで、パンから食物繊維が取れるからです。
目玉焼きや、野菜・海藻などの具沢山のスープを添えられるとより良いです。
前述した、マグカップスープのレシピをぜひご参考にしてください。
妊娠糖尿病と診断されたときの朝ごはんはどうする?

妊娠糖尿病とは、妊娠中に発見または発症した糖尿病ほどではない軽い糖代謝異常です。
妊娠すると、胎盤から出るホルモンの働きでインスリンの働きが抑えられること、また胎盤でインスリンを壊す働きの酵素ができるため、妊娠していないときと比較してインスリンが効きにくい状態になり、血糖が上がりやすくなります。
このため妊娠後期には高血糖になる場合があり、一定の基準を超えると妊娠糖尿病と診断されます。
妊娠中はお腹も空きますし、胎児のために栄養は取らないといけないので、妊娠糖尿病と診断された場合は食事が難しいと感じるでしょう。
妊娠糖尿病の妊婦さんが摂るべき栄養は、1日の摂取カロリーのうち炭水化物が50〜60%、たんぱく質が20%以下、脂質が20〜30%とされています。
1日3回の食事を「主食+主菜+副菜」の組み合わせにし、1日の中で果物や牛乳・乳製品、油を適度に取り入れると、自然とそのバランスがとりやすくなります。
ただ妊娠中は何かと体調が優れない時も多く、またお腹が大きくなってくると料理するのも辛くなったりします。
手軽に食べられる食品は便利ですが、妊娠糖尿病と診断されたときに食べてもいいのか気になりますよね。
以下で解説していきますので、ご参考にしてください。
妊娠糖尿病で朝ごはんにパンを食べたいときはどうしたらいい?

朝ごはんはパン派の方におすすめなのが、ライ麦パンや全粒粉入り食パン、ブランパンです。
普通の食パンとは違い、これらのパンには食物繊維が豊富に含まれているため、血糖値の急上昇を防ぐことができます。
パンを食べるときは6枚切りを1枚程度にし、野菜スープなどをパンの前に食べると良いです。
最近では低糖質パンと表示された商品がスーパーやコンビニにも多く置かれるようになったので、それを選んでみても良いでしょう。
妊娠糖尿病のとき、朝ごはんにバナナを食べてもいい?

バナナに含まれるカリウムは、血糖値の急上昇を抑える働きがあります。
食物繊維やビタミン、ミネラルも多く含まれているので、食べても構いません。
ただ他のフルーツと比較して糖質も多く含まれているため、1回の食事で3分の1本、1日1本程度にしましょう。
Q&A
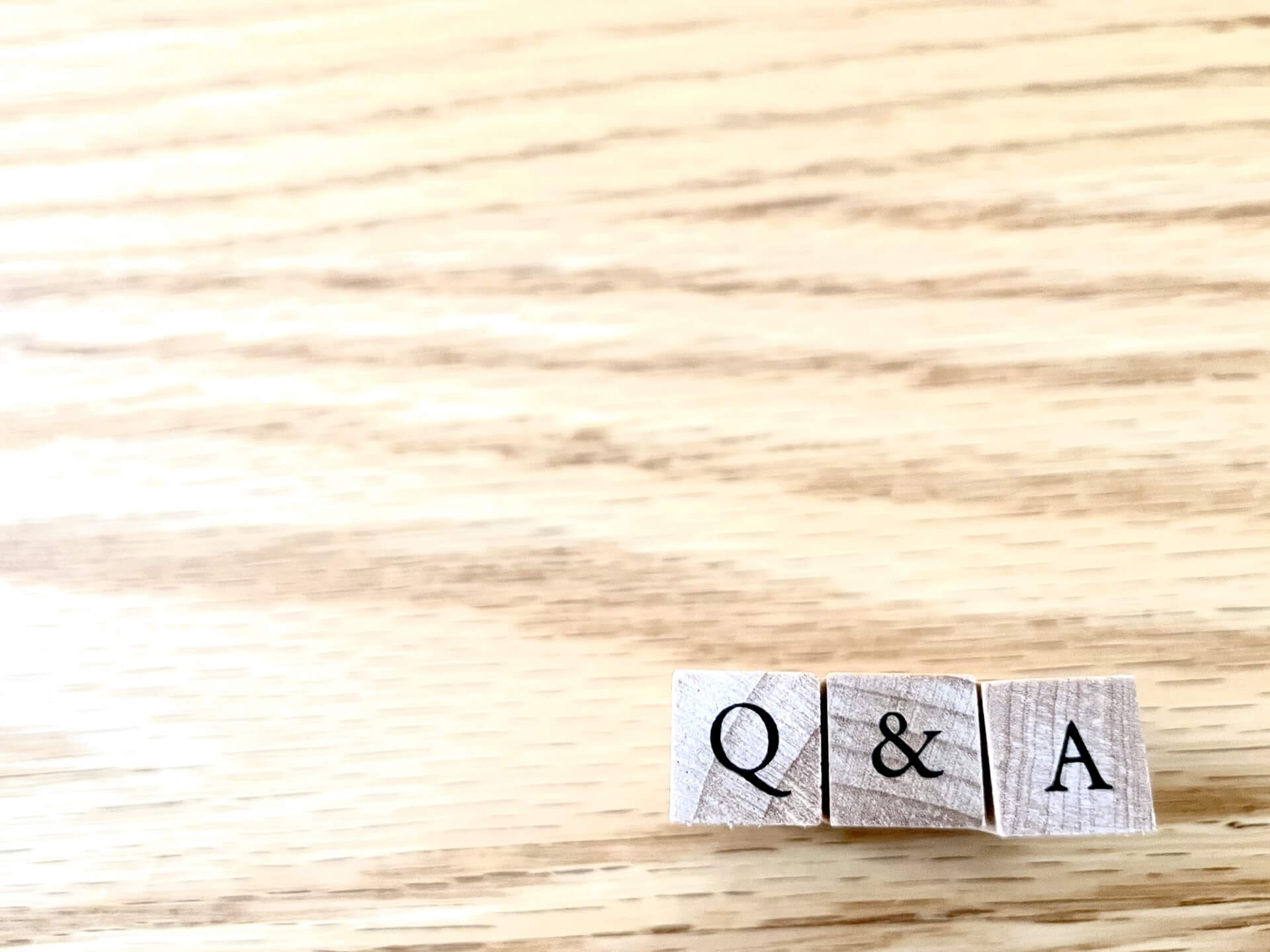
糖尿病の朝ごはんは何がいい?

糖尿病の方の朝ごはんにおすすめなのが、血糖値の急上昇を防ぐ低GI食品です。
主食には、玄米や雑穀などの食物繊維が多く含まれているご飯やパンを食べるのがおすすめです。
食物繊維と言うと、野菜を想像する方も多いのではないでしょうか。もちろん野菜も欠かせないのですが、わかめ、昆布、ひじき、もずく、めかぶなどの海藻類もおすすめです。
海藻類には、食物繊維以外にもミネラルとタンパク質も多く含まれるため、低カロリーなのに腹持ちが良いです。
また、食べる順番にも注意する必要があります。
炭水化物を食べる前に食物繊維を多く含む食品を食べると、GLP-1と呼ばれる消化管ホルモンの分泌が促され、胃の動きを緩やかにすることで、食後高血糖を改善できます。
海藻類を先に食べ、その後主食を食べることを意識しましょう。
糖尿病の人が朝食を抜くとどうなる?

長時間空けた後の食事で体は糖分をしっかりと吸収しようとするため、昼食後に血糖値が急上昇してしまいます。
糖尿病の治療目標のひとつとして、血糖値の急激な変動を抑えて膵臓の機能を維持することがありますが、朝食を抜くことで結果的に大量のインスリンが分泌されることになります。すると、膵臓の負担が大きくなるため糖尿病の悪化に繋がってしまうのです。
糖尿病の方は1日の中で食事のボリュームを均等にし、血糖値をなるべく一定範囲内に保つことが重要です。
血糖値を上げにくい朝食は?

血糖値の上昇を緩やかにすると言われる食物繊維を多く含む食品を食べるようにしましょう。
野菜、納豆、海藻類、きのこ類は食物繊維を多く含みます。
また、玄米や雑穀の入ったご飯やパンにすると、さらに食物繊維を摂取することができます。
納豆や海藻類(めかぶ、もずくなど)は調理の手間がないので、忙しい朝食に取り入れやすい食品です。
また、低GI食品もおすすめです。
代表的な例をあげると大豆食品、さつまいも、きのこ、そばなどがあげられます。
これらを朝食に取り入れると、血糖値の急激な上昇を抑えることができ、肝臓への負担を抑えられます。
血糖値を上げない朝食は納豆ですか?

納豆の主原料である大豆ですが、この大豆タンパクは肉類のタンパク質と比較して血糖値を下げる効果が大きいです。
大豆タンパクに含まれる水溶性ペプチドは、血液中の糖の吸収を促す作用があります。
さらにこの水溶性ペプチドは、血液中の糖分濃度が必要以上に低下したときには、血糖値が下がりすぎないようにホルモンのバランスを整える働きもします。
つまり、納豆は糖尿病の方の朝食としては最適であると言えます。
ご飯の量に注意して、朝食に取り入れると良いでしょう。
まとめ

血糖値の上がりにくい食品でも、工夫次第で満足できる食事を摂ることができます。
糖尿病の食事療法の目的は、正しい食習慣により過食を防ぎ、偏食せずに規則正しい食事をすることです。
正しい食事が習慣化することで糖尿病の悪化を防ぐことができるのはもちろん、インスリンの分泌能力や働きが改善し、血糖値が適正な範囲に保たれることもあります。
また、正しい食生活を共有することで、ご家族の糖尿病リスクを減らすこともできます。
ぜひこの記事を参考にしていただき、手軽に正しい食事習慣を手に入れてください。